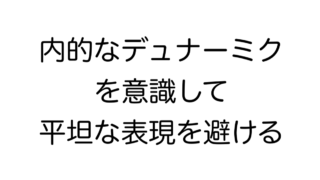 ダイナミクス
ダイナミクス 【ピアノ】内的なデュナーミクを意識して平坦な表現を避ける
「内的なデュナーミク」を意識すると、
表現の奥行きが出てきます。
sempre mf で弾いてしまう表現をはじめ、
いつも平たい音楽表現を
よく耳にします。
これを脱する方法は
過去にも記事に...
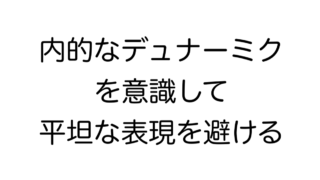 ダイナミクス
ダイナミクス 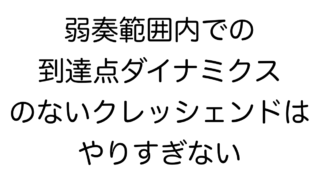 ダイナミクス
ダイナミクス 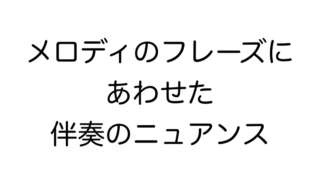 ダイナミクス
ダイナミクス 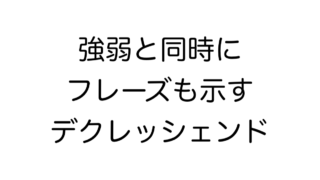 譜読み
譜読み 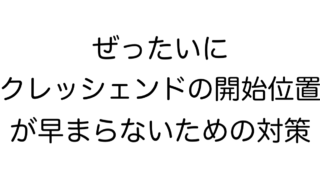 ダイナミクス
ダイナミクス 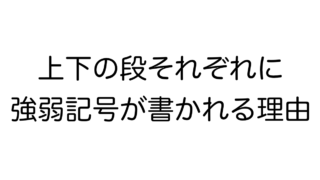 ダイナミクス
ダイナミクス 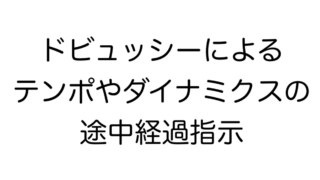 ダイナミクス
ダイナミクス 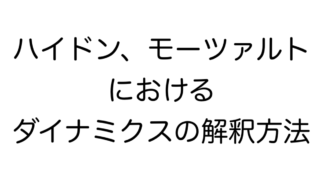 ダイナミクス
ダイナミクス 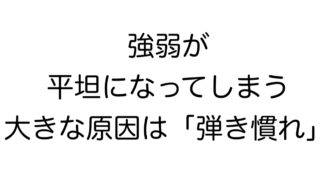 ダイナミクス
ダイナミクス 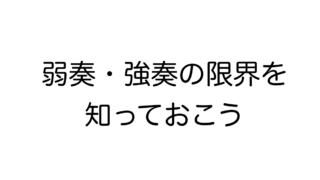 ダイナミクス
ダイナミクス 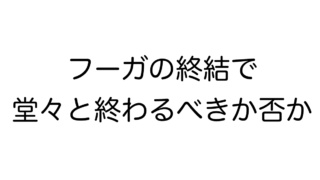 J.S.バッハ
J.S.バッハ 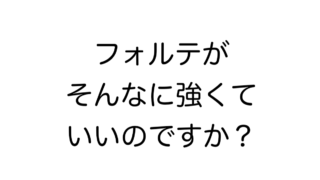 ダイナミクス
ダイナミクス