■フォルテがそんなに強くていいのですか?
♬ f 単独よりもさらに上のダイナミクス
ダイナミクスは
「ff」、「fff」、
f 以上のダイナミクスにつけられた
「各種アクセント」、
f 以上のダイナミクスにつけられた
発想標語である「marcato」などをはじめ、
f 単独よりもさらに上のダイナミクスが
たくさん存在します。
「強く」いう言葉を聞くと
頑張りたくなる気持ちはわかりますが、
相対的に考えると
「まだまだ冷静な自分がいなければならない段階の強さ」
ということです。
♬ ダイナミクスの天井は、あっという間
ピアノを演奏する場合、
その楽器の特性上
「クライマックスのつくりかた」
つまり
「1番のヤマのつくりかた」
に思っている以上に気をつけないと、
あっという間にダイナミクスの天井に行き着いてしまいます。
f で天井に行き着いてしまったら
それ以上のダイナミクスは表現しようがありません。
(参考:【ピアノ】誰でもできる「クライマックスの活かし方」)
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
♬ 音の厚みで自然と音響も厚くなる
一般的に f の箇所というのは
f 以下のダイナミクスのところに比べて
重厚な和音が使われていたりと、
「音の厚み」も増していることが大半。
つまり、
仮にそれまでと同じ強さで弾いたとしても
それまでよりも音響的には充実するのです。
したがって、
頑張りすぎなくても結果的に f になります。
♬ 最大ダイナミクスが f までの楽曲
ここでひとつ問題がでてきます。
「最大ダイナミクスが f までしか出てこない楽曲では、そこをマックスで弾いていいのか」
というもの。
答えは簡単でして、
「ノー」です。
ダイナミクス記号というのは
単純な音量だけでなく
「テンション(緊張度)」にも影響します。
つまり、
f が書かれているところでは
仮にそこが楽曲の最高音量だったとしても
ff や fff のようなテンションは求められていないのです。
「最小ダイナミクスを p まで、最大ダイナミクスを f まで」
として取り組みやすくする意図がある初級教材などはあり、
そういった楽曲は例外となります。
♬ それぞれの作曲家による、ダイナミクスニュアンスの差
ここでもう一つ問題が出てきます。
「それぞれの作曲家による、ダイナミクスニュアンスの差」
について。
作曲家によってダイナミクス記号の意味合いは異なり、
例えば、
「モーツァルトの f 」と「プロコフィエフの f 」
の性格はまったく異なります。
また、
fff が初めて用いられたのは
ベートーヴェン「交響曲 第7番」の中だと言われています。
それまではまだ fff が無かったですし、
ベートーヴェンの他の作品を見ても
「 ff +sf 」でfff を表現しています。
(参考:【ピアノ】スフォルツァンドの解釈)
これらのようなことからも、
一概にダイナミクスについての決まりを作ることはできませんし、
それは意味のないこととも言えるはず。
しかし、
少なくとも
今現在の記譜にかなり近づいてきたロマン派以降では
基礎として
ここまでの内容を踏まえていないといけません。
その上で、
それぞれの楽曲を「一曲一曲別の顔」として捉えて
解釈を考えていきましょう。
【ピアノ】ハイドン、モーツァルトにおけるダイナミクスの解釈方法
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
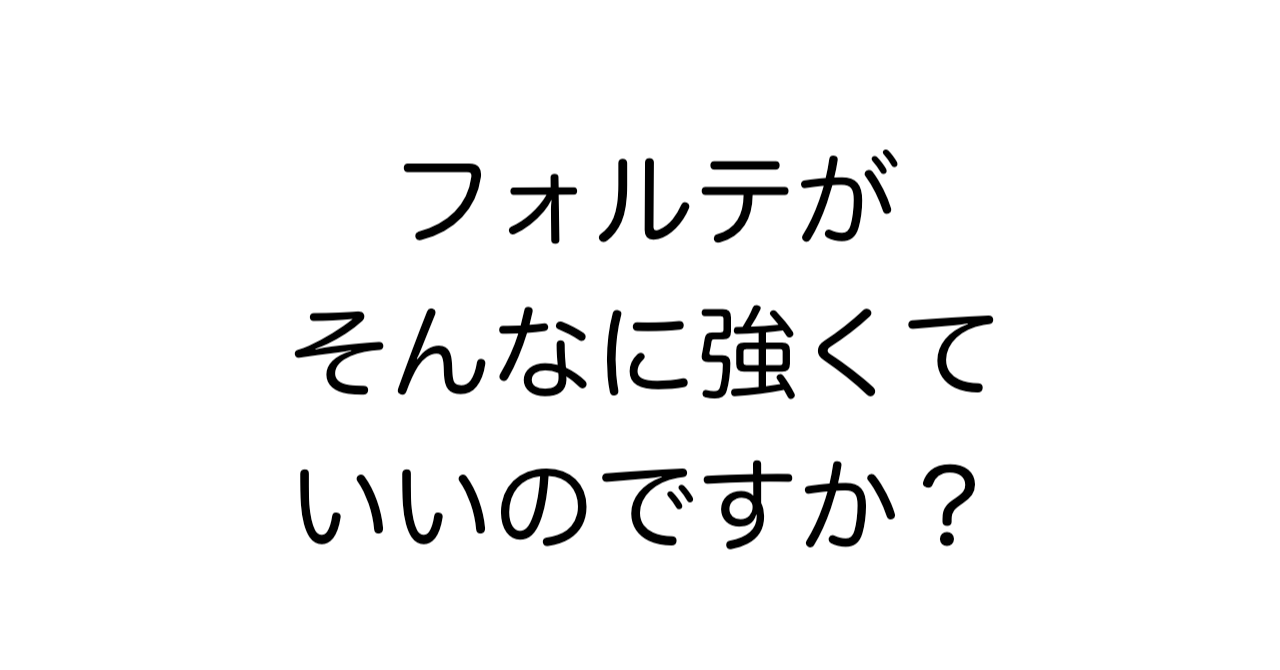
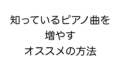
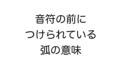
コメント