♬ ソナチネからショパンエチュードへ最短で接続できる手順は?
♬ ショパンエチュードはどの曲から取り組むべき?
♬ 独学に最適のオススメの参考書は?
これらの疑問、本記事ですべて解決します。
今回は、「約1年間」という期間で
「入門が終わった段階(ソナチネ程度)」から
どのような手順を踏めば
ショパンのエチュードへ接続できるかを解説していきます。
自分で自由に教材を選べる「独学」の方を対象とし、
「楽典の基礎の基礎はすでに理解できている方」
を対象に書いていきます。
正直、ショパンのエチュードの中でも
取り組みやすいと言われている数曲であれば、
「入門が終わった段階(ソナチネ程度)」から
いきなり挑戦しても何となくは弾けるようになるでしょう。
ただ今回は、
「自分の演奏レベル自体を引き上げてショパンのエチュードへ接続すること」
を目指すこととします。
■ソナチネからショパンエチュード入門までのロードマップ
♬ ちなみに、王道のルートは?
まず最初に、
あくまで比較参考として
気が遠くなるような「王道のルート」を紹介します。
比較的定番化されているルート。
↓
「ツェルニー30番」(ツェルニー100番、110番と入れ替えて使用し始める)
↓
「ツェルニー40番」(この辺りから「ソナタアルバム」を併用)
↓
「ツェルニー50番」
↓
「モシュコフスキー」や「近現代のエチュード」などから抜粋
↓
「ショパンのエチュード」
実に気が遠くなりますね。
筆者自身もこのルートをたどりましたが、
特に「ツェルニー30番〜ツェルニー40番の前半あたり」は
楽曲自体にも興味をもてず、
楽しさを感じられませんでした。
実際に同じような意見を言う学習者も多いのです。
また、ツェルニーなどは曲数も非常に多く、
ほんとうにそんなにたくさんやる必要があるのかは疑問です。
ましてや独学でやるのはムリ。
この時期は「たくさんの楽譜を読む」ということも必要ですが、
将来を考えると、それは「浅く読むこと」ではないのです。
♬ ショパンのエチュードにムリなく効果的に接続する方法
これから紹介する方法で、
今までに何人もの知人がショパンのエチュードに入門できました。
全員、大人の社会人。
王道のルートをとることは時間的に厳しかったんです。
結論から言います。
それは、
3声は入れずに「2声の全15曲のみ」に取り組みます。
そして、これらの作品から
しぼりとれるだけしぼりとる練習をします。(やり方は後述します。)
まず、「バッハ : 2声のインヴェンション(全15曲)」の教材としての優秀さは、
ショパンのエチュードを弾く上での土台となる基礎テクニックが
しっかりと学べること。
例えば、
◉ さまざまな調性での練習
◉ さまざまなテンポでの練習
◉ カンタービレの表現、速いパッセージ
◉ 片方の手にかたよらない練習
など。
また、他にも利点があります。
◉ 1曲あたりがコンパクトなので練習しやすい
◉ 有名な楽曲のため、独学で困った時に参考にできる教材が多くある
◉ 曲が魅力的で退屈しない
◉ 一部の練習曲と違ってそれ自体がレパートリーになるので、弾き込む意味がある
など。
では次に、
「ショパンのエチュードで求められるけれども、インヴェンションにほとんど出てこない要素」
に注目しておきましょう。
主には、
◉ ペダリング
◉ 和音演奏
この3点でしょう。
「手を大きく開く技術」に関しては、
ショパン「エチュード op.10-9」などの
入門で多く使用されるエチュードでも出てきますが、
逆に、「ショパン : エチュード op.10-9」の練習課題がこの部分なわけです。
したがって、
このテクニックはショパンで学ぶことを念頭に置いて、
それ以前の基礎をしっかりと固めておくことに注力しましょう。
それぞれのテクニックはつながっています。
「ペダリング」に関しては、
インヴェンションにおいても
ピアニストは「音色」や「ビート」のコントロールの観点から
ペダルをある程度使っていますが、
確かに多用はしませんね。
一方、これはツェルニーや古典派の一部のソナタでも
詳細には学べませんし、
結局「1曲1曲を別の顔」として見ていかなければいけないので、
ショパンのエチュードへ入門した段階で
「コルトー版 ショパンエチュード集」などの
ペダリングが詳細に書かれている教材を参考にして補えばOKです。
「和音演奏」に関しても
「手を大きく開く技術」と同様に、
ショパンで学ぶことを念頭に置いて、
それ以前の基礎をしっかりと固めておくことに注力しましょう。
♬ どうやって取り組んでいくか(オススメ教材など)
「J.S.バッハ : 2声のインヴェンション(全15曲)」に
一点集中で取り組む際のポイントに入ります。
まず、ヘンレ版などではアーティキュレーションが書かれていませんので
独学の方には向きません。
したがって、「解釈版」をそのまま使って学習してしまいましょう。
おすすめの楽譜は、
「園田高弘 校訂版 J.S.バッハ インヴェンション BWV772−786(春秋社)」
こちらの解釈版です。

「アーティキュレーション」はもちろん、
「運指」や「装飾音符の入れ方」まで
幅広くカバーできます。
解釈版の中でも詳しい印象があるということと、
必要であれば
校訂者の参考演奏音源も手に入れられることが信頼のポイント。
この楽譜の解説では、
それぞれの番号をどの順序で取り組んでいくのがベストなのかも書かれていますので、
基本的にはその順序で練習していけばOK。
レヴェルも加味した上で
インヴェンションの中における効果的な取り組み順序が考えられています。
ちなみに、この楽譜は
「3声は含まず、2声の全15曲だけで1冊になっている」
というのも嬉しいところ。
さて、確認しておきたいのが、
「このロードマップは大切な要素をショートカットするためではなく、ほんとうに必要な部分にしぼって濃く学ぶためにある」
ということ。
したがって、
1曲1曲は徹底的に仕上げることが必要です。
まず、1曲を3週間かけて細かく学んでいきます。
そうすると全15曲は「45週間(約1年間)」で終わります。
これをおおむね弾けるようになったからといって短縮してしまっては
まったく効果が上がりませんし、
わざわざ音楽的な教材を選んでいる意味がありません。
解釈版に書かれている解釈をしっかりと学び、
快活な楽曲はきちんとテンポまで上げて、
ICレコーダーで録音してチェックし、
演奏会でも問題なく弾ける程度まで徹底的に仕上げます。
スパルタ的に聴こえるかもしれませんが、
それを唯一できるのが、大人の独学の方の特権。
◉ 先生に決められたスケジュール以外の計画で練習できる
こういったことは、
「大人」でなおかつ「独学」でないとできません。
あと必要なのは「ショパンのエチュードを弾きたいという熱意」だけです。
♬ ショパンのエチュードはどの楽曲から取り組むべきか
入門曲としてよくあげられるのは、
「op.25-1,2,7」
この辺りですが、
「音楽面」「テクニック面」から考えると、
「op.10-9もしくはop.25-2から取り組むのがベター」です。
「op.25-1(エオリアン・ハープ)」から取り組むのは
おすすめしていません。
この楽曲に取り組んでいる多くの方は
関節をベタッと伸ばして演奏しており、
非常に良くないクセがつきやすい楽曲でもあるから。
ここまでで、必要な情報はそろったはずです。
あとは一歩踏み出すだけ。
ぜひ挑戦してみましょう。
今回は、
【ピアノ:独学】ソナチネからショパンエチュード入門までのロードマップ
という内容でご覧に入れてきました。
ショパンエチュードに挑戦したい独学の方に
参考にしていただけると幸いです。
最後に、もうひとつ。
「ピアノを練習する」というのは、
テクニックなどを学ぶだけではなく、
「楽式や様式を学んでいく」
ということも含まれています。
その観点で考えると、
今回のロードマップでは
「古典派の作品の楽式や様式」が抜けてしまっています。
ショパンエチュードに入門してからでも構いませんので
「ベートーベンのピアノソナタ(特に初期のもの)」
にも取り組んでみましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
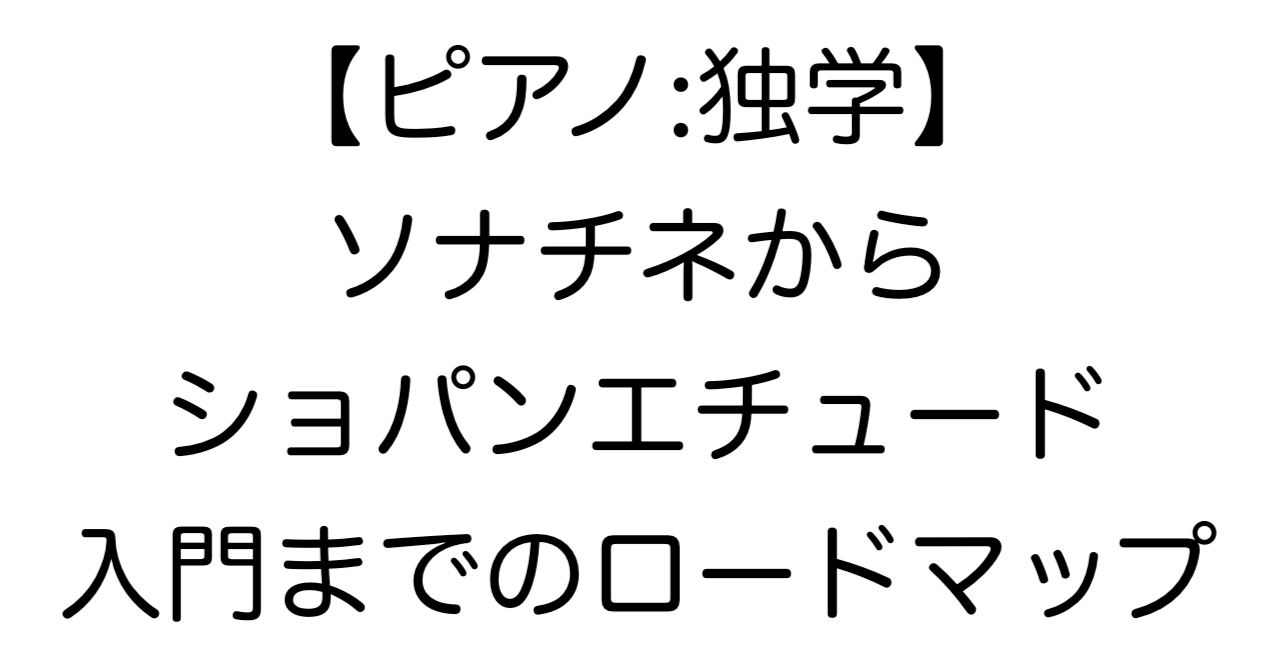
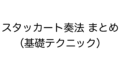
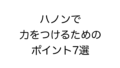
コメント