■インヴェンション入門! 第1番「全運指」公開
インヴェンション入門に最適の楽曲
インヴェンションでは、
第1番、第4番、第8番、第13番あたりが
入門に使われる傾向にありますが、
これらの中でも
特に第1番は入門に適していると感じます。
理由としては、
♬ テンポが速い楽曲ではないので、練習しやすい
♬ 有名な楽曲なので、知っている楽曲ということで練習しやすい
♬ 使われている対位法の技法が分かりやすく、技術的に困難なところもない
などが挙げられます。
「全運指」公開
この楽曲はパブリックドメインになっています。
運営者自身がFinaleで作成したもので、
権利に関わる部分は表示しておりません。
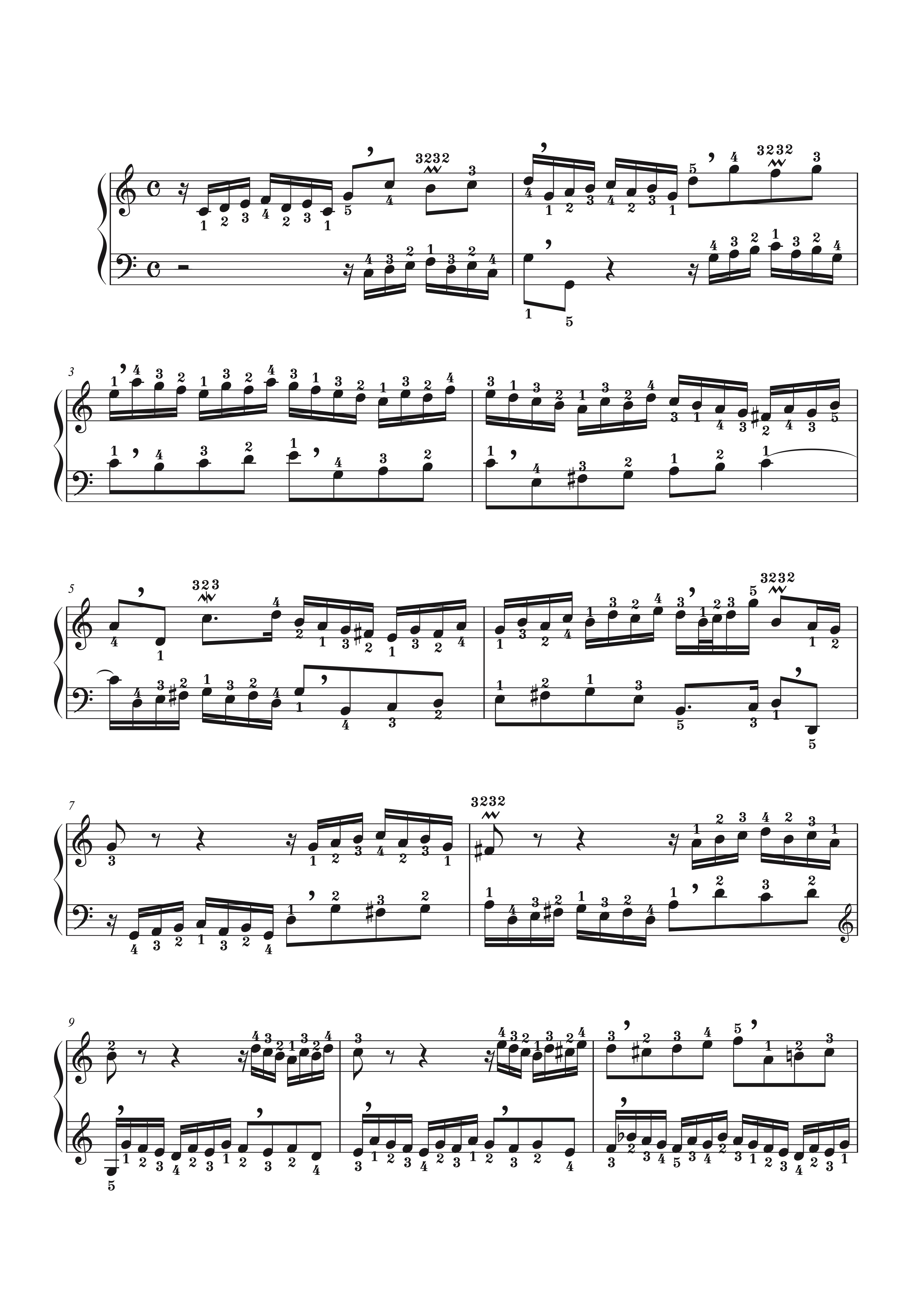
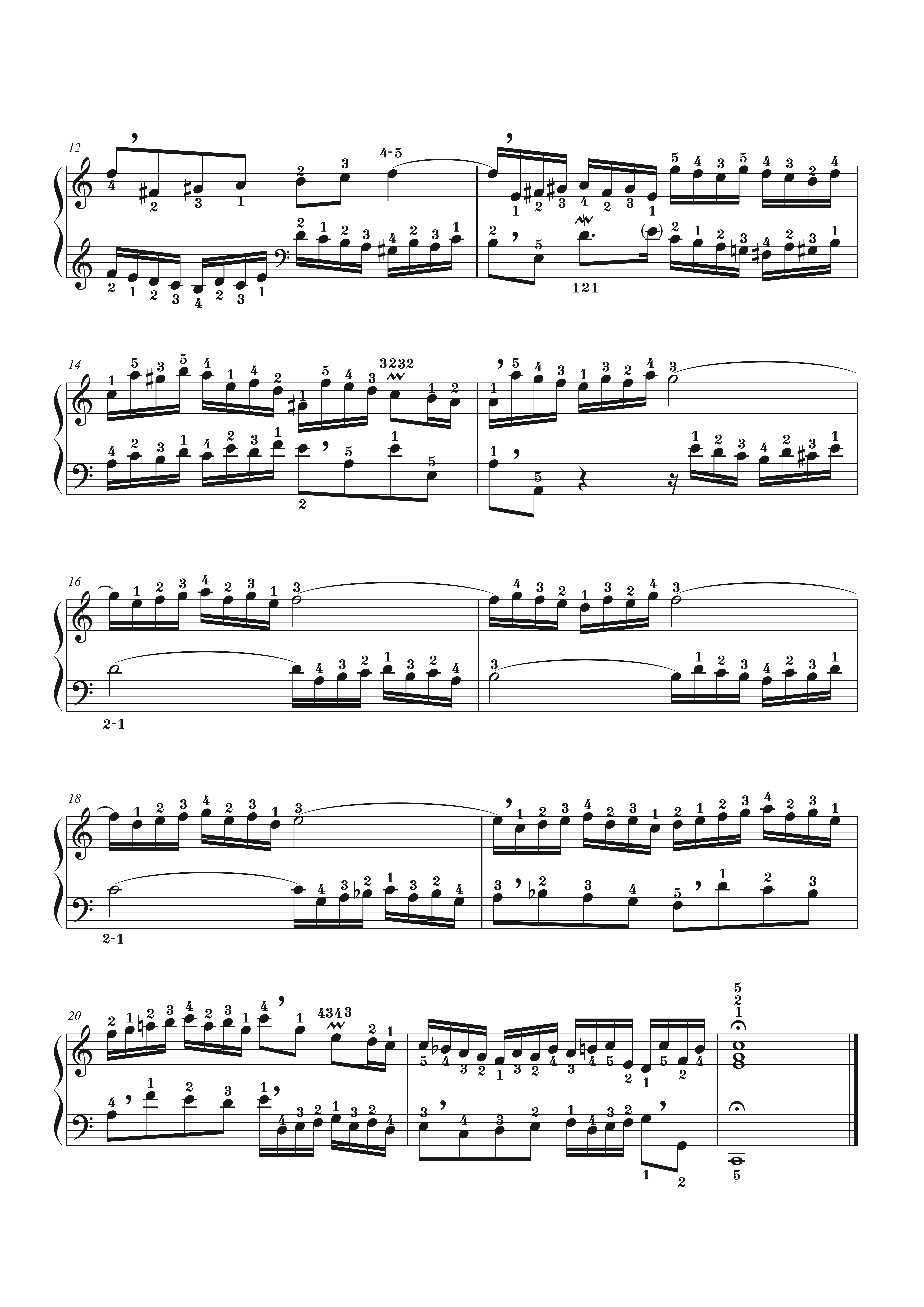
「全運指」を書き込みました。
これが唯一の方法というわけではありませんが、
多くの学習者にとってやりやすいものとなっているはずですので
学習の参考にしてください。
’ の記号書き込んだところは、
少なくとも作曲の観点からすると切るべきところです。
解釈次第では、もっと細かく切るべきところはありますが、
最低限の箇所として認識してください。
こういった切るところが変わると、
運指まで変わってくるのは当然ですよね。
もちろん、
ご自身で良い別の運指を思いついた場合は変更しても構いません。
あわせて読みたい参考記事:
【ピアノ】J.S.バッハの作品で、全ての音に運指を書き込んでみる
具体的な練習の仕方
練習のポイントを3点ほど挙げておきましょう。
インヴェンションのどの番号においても応用できる内容です。
♬ 片手づつピカピカにしてから両手で合わせてバランスをとる
こういった対位法でできている楽曲では、
それぞれの声部が「線」でできています。
「メロディに対して和音で伴奏をつける」
などといった楽曲と異なることは、
楽譜を見れば明らかですよね。
したがって、
まずは片手だけで音楽を作ることが大切。
そして、片手ごとにピカピカになったものを両手で合わせて
全体のバランスをとっていくといいでしょう。
難しいことを言っているようですが、
要するに、
「片手練習をしっかりしましょう」
ということです。
♬ 切る8分音符は跳ねすぎないこと
作曲当時の楽器の特性も考慮されてきた結果、
「J.S.バッハの作品における8分音符は切って演奏する」
このようにするのが慣例となっています。
少なくとも ’ マークを入れたところは必ず切りましょう。
しかし、
8分音符をピッとあまりにも短く切ってしまうのは厳禁。
それでは音楽の性格が変わってしまいます。
「テヌートスタッカート」のようなイメージで
置いていくように打鍵していくといいでしょう。
♬ プラルトリラーやモルデントは拍の前に出さないこと
バロックや古典派時代の作品に出てくる装飾音符は
「拍の前に出さずに、拍の頭と入りの音を合わせて素早く入れる」
このようにするのが慣例です。
J.S.バッハ「インヴェンション第1番 BWV772」の場合は
「プラルトリラー」や「モルデント」が該当します。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
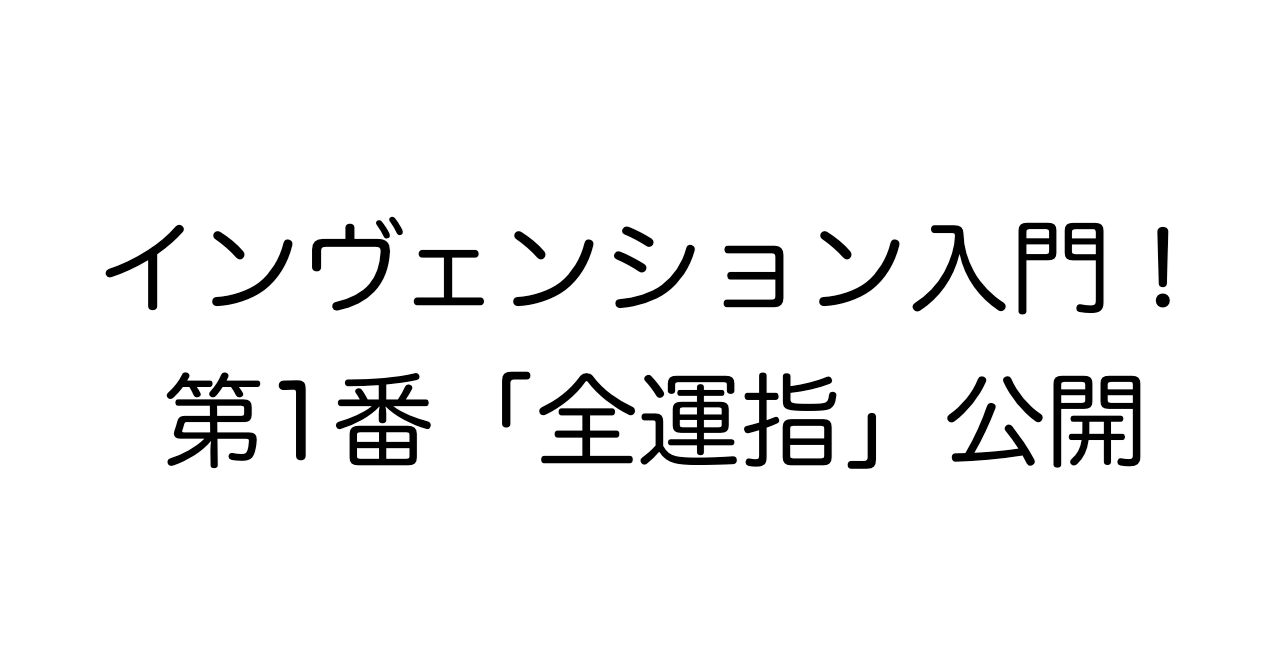
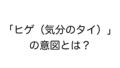
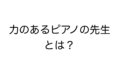
コメント