J.S.バッハの作品の場合、
解釈版を使わない限り
ダイナミクスは自分で判断していくことになります。
しかし、
「平均律クラヴィーア曲集 フーガ」の「終結部分」を考えてみても
堂々と終わるべきか、おさめてやさしく終わるべきか
迷うことはありませんか?
「斎藤秀雄 講義録(白水社)」
という書籍の中にも
以下のような斎藤秀雄氏の指導コメントが載っています。
バッハの音楽にはメロディーがあったにしても、
それが喜怒哀楽に通じるメロディーじゃない。
大体がそうじゃないもんで、
バッハの演奏っていうのはフォルテで終わった方がいいか、
何で終わった方が良いか非常に不明確なんです。
(引用終わり)
判断材料のひとつを挙げておきましょう。
「最終和音の音の厚み、音域」
に注目してください。
具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 BWV 871 ハ短調 より フーガ」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最終小節では、
左手で弾くバスの音域が
このフーガの中で「いちばん低い位置」にきています。
加えて、
右手とあわせて「6音」も同時発音し、
このフーガの中で「いちばん同時発音数が多いところ」になっています。
したがって、
エネルギーとしては非常に高いところであると言えるでしょう。
おさめて静かに終わってしまうと
エネルギーの逆を行くことになりますよね。
まずは
「終止和音の音の厚み、音域」
に注目してみてください。
一部のフーガを除いては
解決策が見つかると思います。
それすらハードルが高く感じる場合は
とりあえず、解釈版に頼ってしまいましょう。
【J.S.バッハ : 平均律クラヴィーア曲集】「入門最適曲」と「楽譜の選び方」
という記事の中で
オススメの解釈版を紹介しています。
◉ 斎藤秀雄 講義録(白水社)
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
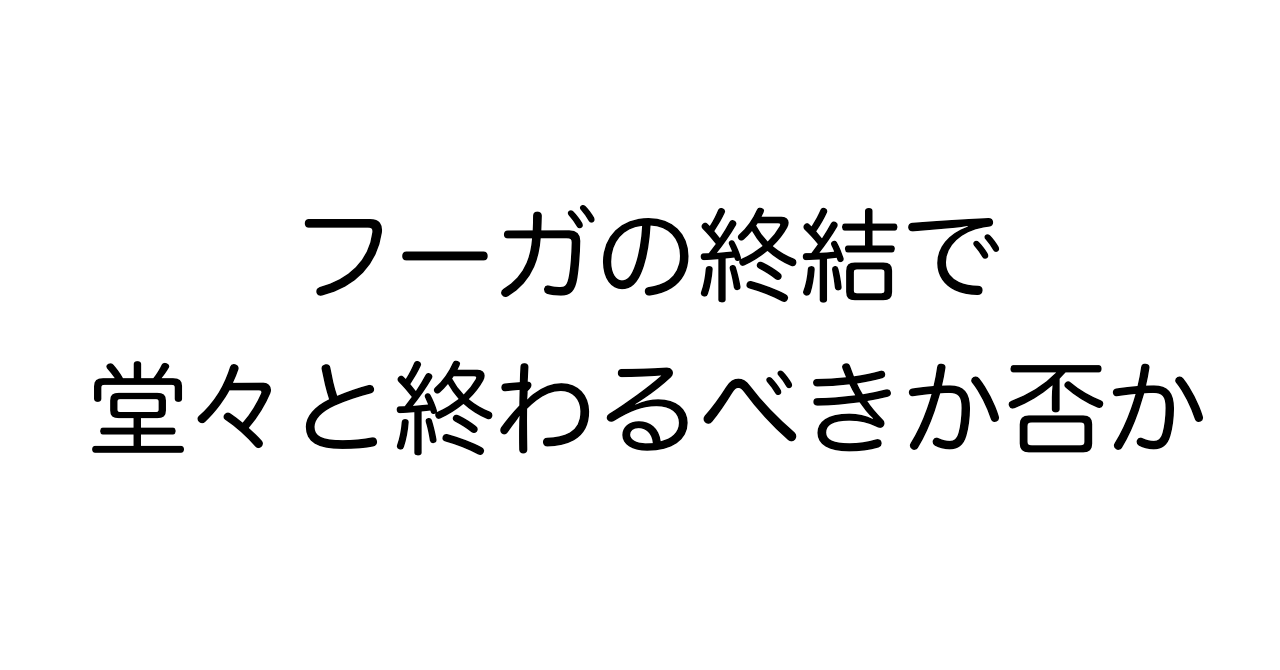

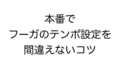
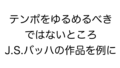
コメント