具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、25-27小節)
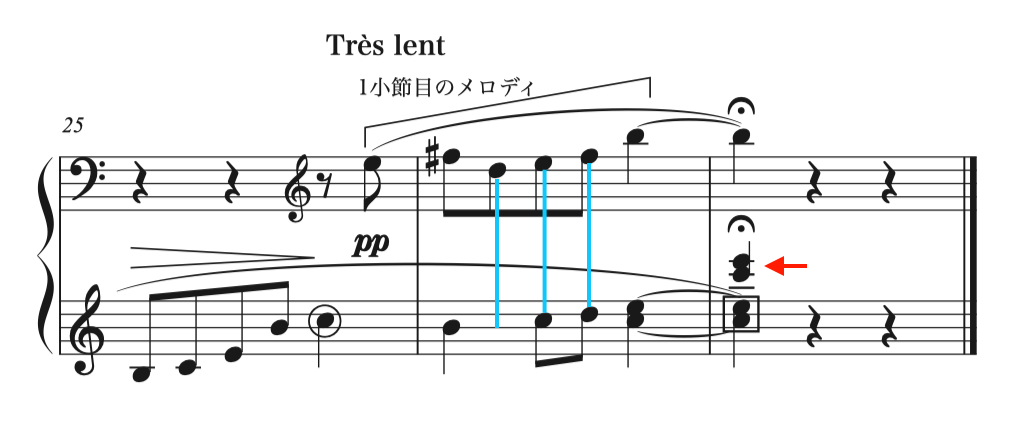
赤矢印で示した、
27小節目の高く鳴らされる「3度音程の和音」は
「エコー」のようなイメージで。
① メロディなどとは関係なく、別の音域で単発で小さく鳴らされる
② あるパッセージが「同じ形」で尚且つ「小さいダイナミクス」で繰り返される
色々なパターンがありますが、大きくはこの2つに分類されます。
譜例のエコーは、①に該当します。
譜例のエコーは、
遠くで鳴っているイメージを持って、極めて軽く演奏すると音楽的です。
このエコーは
オーケストラで演奏するとしたら、
絶対にメロディとは ”別の楽器” で演奏するはずです。
イメージしてから音を出すことの重要性は
以前から記事にしていますが、
イメージすることで
打鍵の仕方に無意識のコントロールが入るのです。
したがって、
遠くで鳴っているような音を出すためには
どのように打鍵すればいいかを知っていなくても
無意識のコントロールで
結局は音色を近づけることができます。
少し、難しい話をしてしまいました。
もっと簡単な言い方をすると、
「遠くで鳴っているような音を出したい」
と思いながら、バシン!という打鍵をする人はいません。
反対に、
「すぐ目の前に音像があるような音を出したい」
と思いながら、フワッという打鍵をする人はいません。
イメージは、自分の打鍵の仕方に直結しています。
だからこそ、イメージすることは馬鹿にできないのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
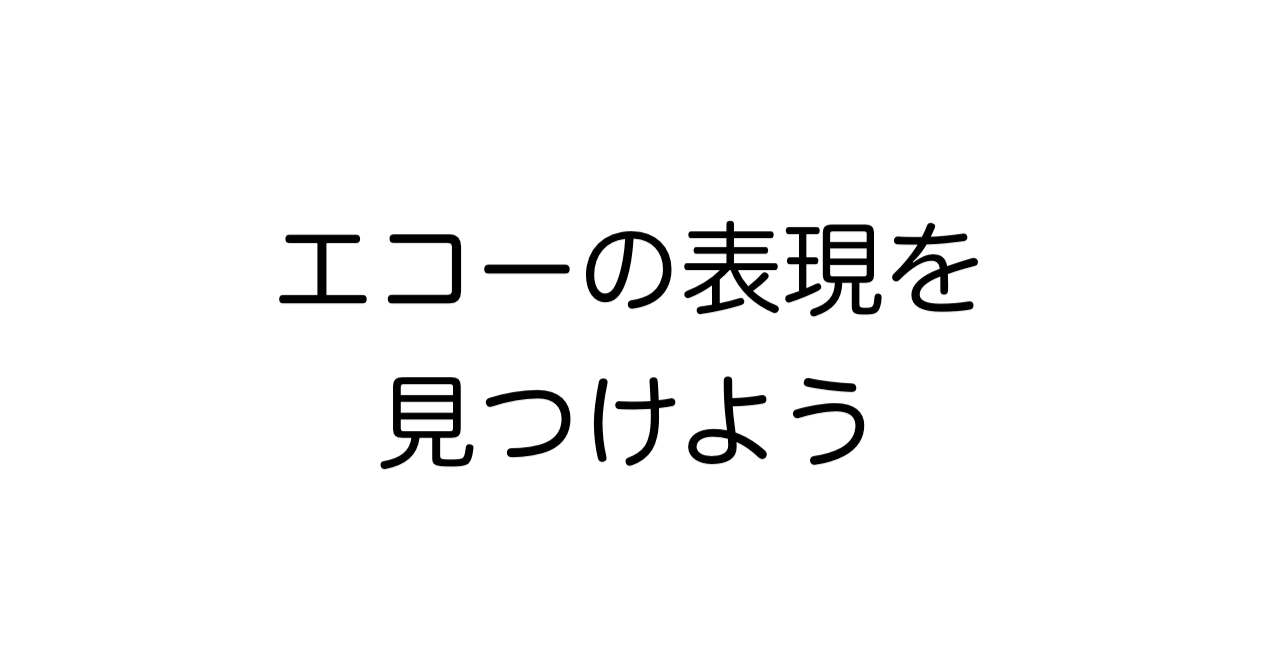

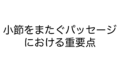
コメント