注 : 本記事で譜例を取り上げている作品は
パブリックドメインになっている作品です。
出版社が独自につけたアーティキュレーションなど
権利に関わる部分は一切表示しておりません。
譜例はFinaleで作成したものです。
この楽曲は「ソナタ形式」です。
ソナタ形式の詳細については以前に記事を書いていますので割愛します。
以下の内容を参考にしてください。
【対話形式で学ぶ】誰でもわかる「ソナタ形式」/ 書籍無料公開
本記事では第1段階として、1-7小節目までを解説します。

♬ 1-4小節目のメロディ
1-4小節目のメロディから。
1-2小節目は、和声音(C-E-G)のみを使った「分散和音」でメロディができています。
それに対して、3-4小節目は非和声音も使って順次進行で動くメロディです。
(3-4小節目で)丸印をつけた音が「和声音」で、それ以外が「非和声音」です。
(バス音を見ると「和声音」と「非和声音」の区別の参考になります。)
このように、
まずは「1-2小節目のメロディと3-4小節目のメロディとの違い」を理解しましょう。
(再掲)

♬ 1-4小節目の左手
次に1-4小節目の左手について。
低音というのは非常に「リズム要素」を感じるパートです。
その観点で考えると、
1-2小節目は「1小節 1パルス」
3-4小節目は「1小節 2パルス」となっています。
(4小節目の左手は8分音符で動いていますが、
これは一息で演奏するので8分音符全体で1つ分のパルスのみを感じます。)
つまり、
1-2小節目と3-4小節目ではリズム骨格のつくりが異なるのです。
仮に、1-4小節目までずっと「1小節 1パルス」だったとしたら、
おそらく退屈した音楽になってしまうでしょう。
作曲家はさりげなく多くの工夫をしているのです。
(再掲)

♬ 4小節目の「追っかけ」
4小節目のカギマークで示した箇所を見てください。
右手で演奏した動きを直後の左手で「追っかけ」しています。
この左手の動きは「追っかけ」であることと同時に、
4小節目から5小節目へ音楽をつなぐ「ブリッジの役割」になっています。
♬ 変則的な「経過句」
5-7小節目は「経過句」ですが、
「3小節間のみ」という点が少し変則的です。
この楽曲は基本的に「2小節単位」や「4小節単位」で音楽が進行していきますので、
「3小節間のみ」の経過句が挟み込まれることで
音楽の流れが変わる効果が出ています。
(再掲)

♬ 6-7小節目のメロディ
6-7小節目のメロディメイクについては、
「軸の音」を見抜けるかどうかがポイントです。
丸印をつけた音が「軸の音」です。
つまり、これらの音を軸に装飾されているだけなので、
「裏の音」を丸印の音よりも目立たないように演奏すると
音楽的には自然に聴こえます。
…といったように、分析を演奏にも活かしていきましょう。
♬「第2主題」に向けてとられている工夫
先ほどリズムの解説で、
1-2小節目は「1小節 1パルス」
3-4小節目は「1小節 2パルス」
と書きました。
5-7小節目も考えてみましょう。
5小節目は「1小節 1パルス」
6小節目は「1小節 2パルス」
7小節目は「1小節 4パルス」
となっています。
したがって、7小節目は「音楽の進行感」が強いのです。
ハーモニーも移り変わりが細かくなっていますね。
ここまでを読みとれれば、
「8小節目からの第2主題に向かって音楽の進行感を強めてせきこんでいる」
ということがわかります。
もちろん、テンポを速めるという意味ではなく、
音楽の成り立ちの話です。
(再掲)

♬ 1-7小節目のハーモニー
1-7小節目のハーモニーを見ていきましょう。
ひとまずは、
「T(トニック)」「D(ドミナント)」「S(サブドミナント)」
の表記のみで考えればOK。
1-3小節目まではずっと「T(トニック)」、それにずっと同じ和音です。
4小節目は「D(ドミナント)」、それが5小節目で「T(トニック)」に解決します。
6小節目も「T(トニック)」ですが、
点線で示した箇所からはト長調(G-dur)になります。
点線で示した箇所の直後に「Fis音」が出てきますよね。
これが転調を見抜くカギ。
臨時記号というのは、大きく次の2つのパターンで出てきます。
◉「転調」、もしくは一時的な「部分転調(調性の拡大)」をしたとき
ここでは「2」ですね。
ト長調(G-dur)に転調をする目印になっています。
楽曲分析をする際に臨時記号を見つけたら
「なぜ出てきた臨時記号なのか」
これを考えるクセをつけるといいでしょう。
今回の記事はここまでです。
最後にワンポイントアドヴァイス。
「和声記号」をつけることが分析だと思っている方も多いようですが、
「ピアノ演奏に活かしていく」ということを考えると
それほど効果的ではありません。
記号を書き込むことで分析した気になってしまうからです。
むしろ、今回取り上げたような、
◉ リズムの骨格
◉ メロディメイクの理解
など、こういったことを細かく分析していくほうが
ニュアンスを考えていくきっかけになります。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
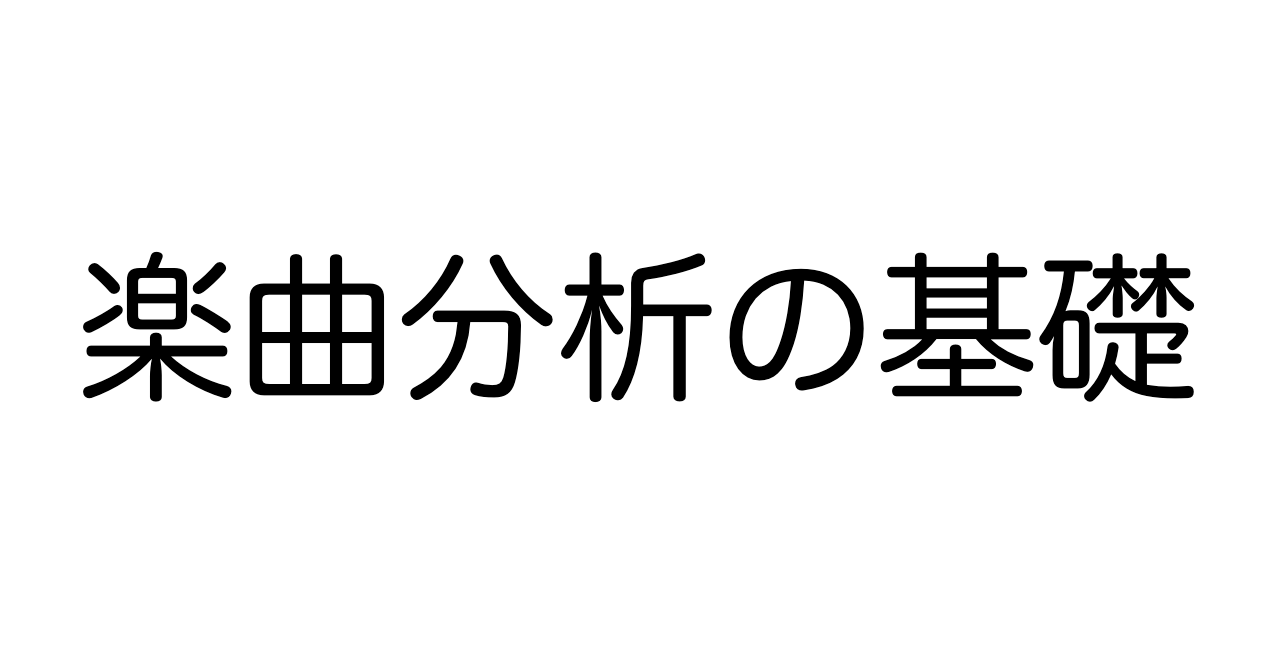
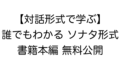
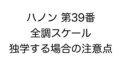
コメント