譜例を見てください。
ドビュッシー「前奏曲集 第2巻より 第2曲 枯葉」
譜例(Finaleで作成、17-22小節)
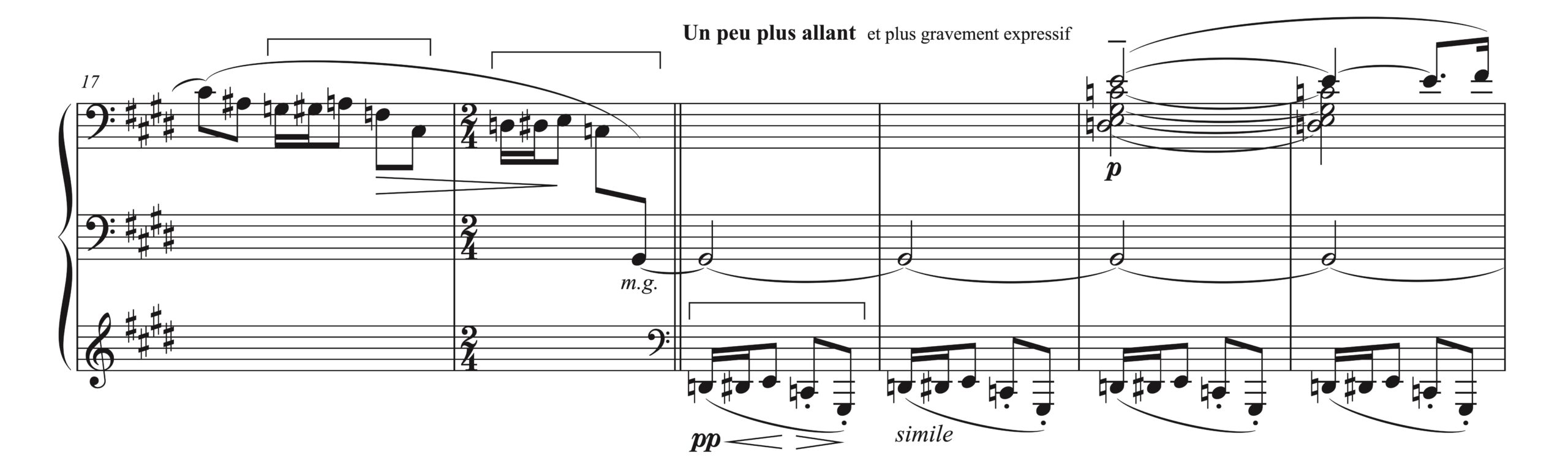
17-18小節目のメロディに対して
カギカッコで示した素材に注目してください。
そのメロディの断片が
19小節目では一番下の段へ移されます。
そしてオスティナートとして繰り返されます。
オスティナートのような「繰り返し」というのは
音楽的な観点で言えば「主役的な独立性」には欠けます。
音は動いていても、音楽的には「スタティック(静的)」ということ。
つまり、
「すでに伴奏的役割に移行した」とも考えられるのです。
(再掲)
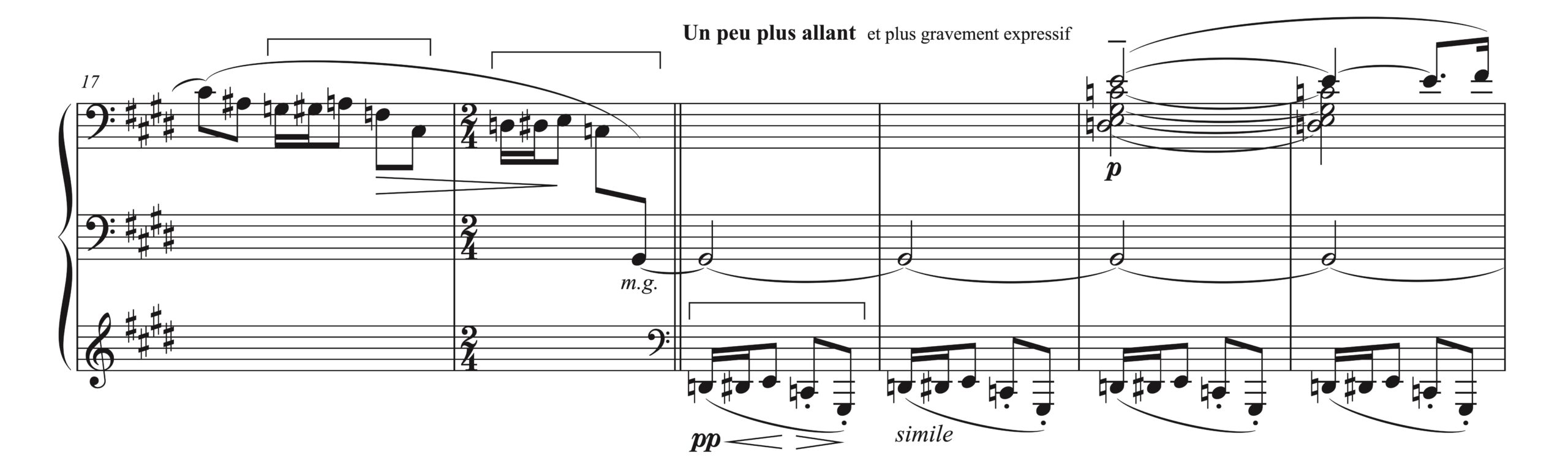
さらによく見てください。
21小節目では
一番上の段にメロディが出てきます。
つまり、
ここまでメロディだった素材は
やはり、伴奏へ移行していたということなのです。
よくあるやり方ではありますが、
音楽的かつ、面白い音楽演出ですよね。
これが分かれば、
演奏においてどちらの動きを目立たせるべきかは明白。
ドビュッシーの楽曲は多層的であり、
必ずしも
「メロディ+伴奏」
というような単純な役割分担になっていない楽曲もあります。
しかし、
ここでは明らかに
新しく出てきたメロディの方に重要度が感じられます。
何となく楽譜を読んで音を出しているだけではなく、
譜読みでこういった楽曲分析的なことを読み取るのが
音楽を深く理解するための第一歩です。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
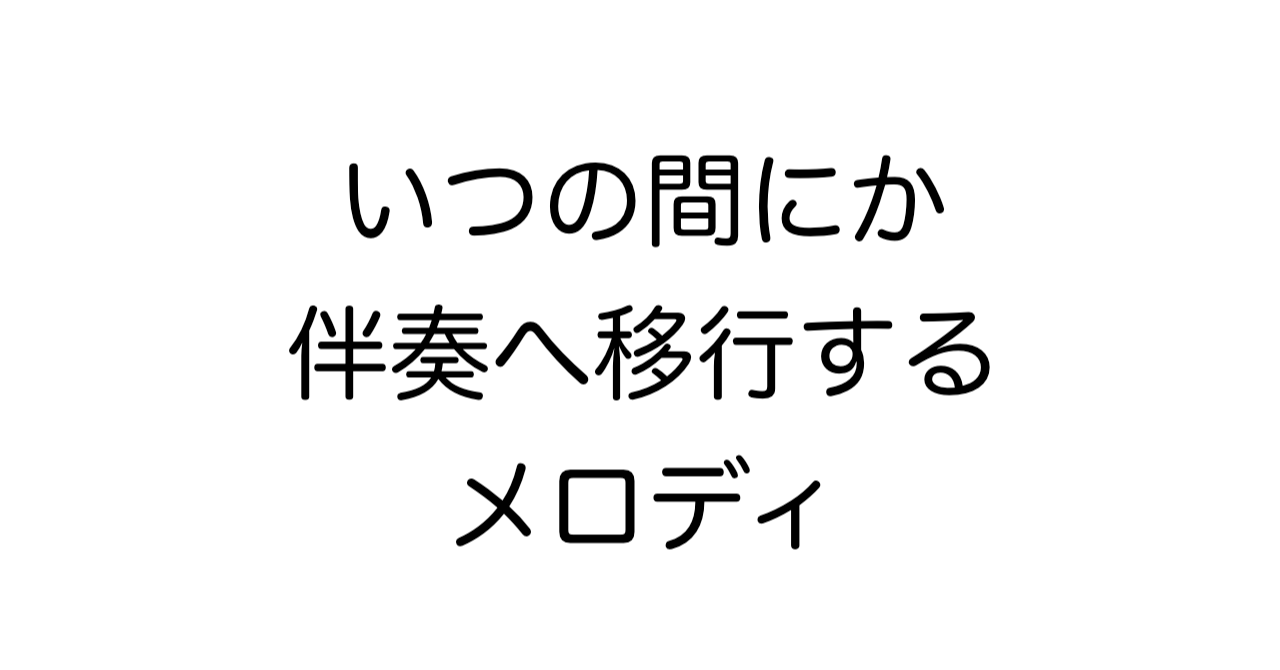
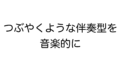

コメント