先日、
という記事でお伝えしたこととも共通するのですが、
「小さな音型が作品を作っている」
ということを改めて強調したい思っています。
天才が作曲した古典的な作品であれば、
どんなに小さな音型であっても
すべて作品全体に関わるイメージを含んでいます。
ふと出てきた音型に反応して、
どう表現すべきかを検討しましょう。
特にベートーヴェンやモーツァルトなどの
古典派の作品では、
一つ特徴的な音型を提出したら
その音型を「これでもか」というほど使い回すのが通例です。
そして、
「新しい音型が出てきた」
と思っても
「音程関係」や「音型の運動方向」など
何かしらの共通点を持っていることがほとんどです。
そしてそれらをまた
しつこいほど発展させていきます。
作品によっては
突発的に出てくる音型もありますが、
その場合でも
力のある作曲家の書いた作品であれば
その小さな音型が
作品全体に関わるイメージを含んでいます。
この記事でお伝えしたいことは
音型の練習方法ではありません。
譜読みの時に
「5連符が出てきました」
で終わらせずに、
◉ この音型だけ細かいけれど、何を表現したいのだろう?
などと考えていくクセをつけていくことの重要性について。
そういったこともすべて含めて「譜読み」と言えます。
音楽理論などを知らなくてもできる、
立派な「楽曲分析(アナリーゼ)」のひとつ。
こういったことを徹底しておけば、
他の作品を学ぶときにも
自分一人で音楽を読み取っていく力となります。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
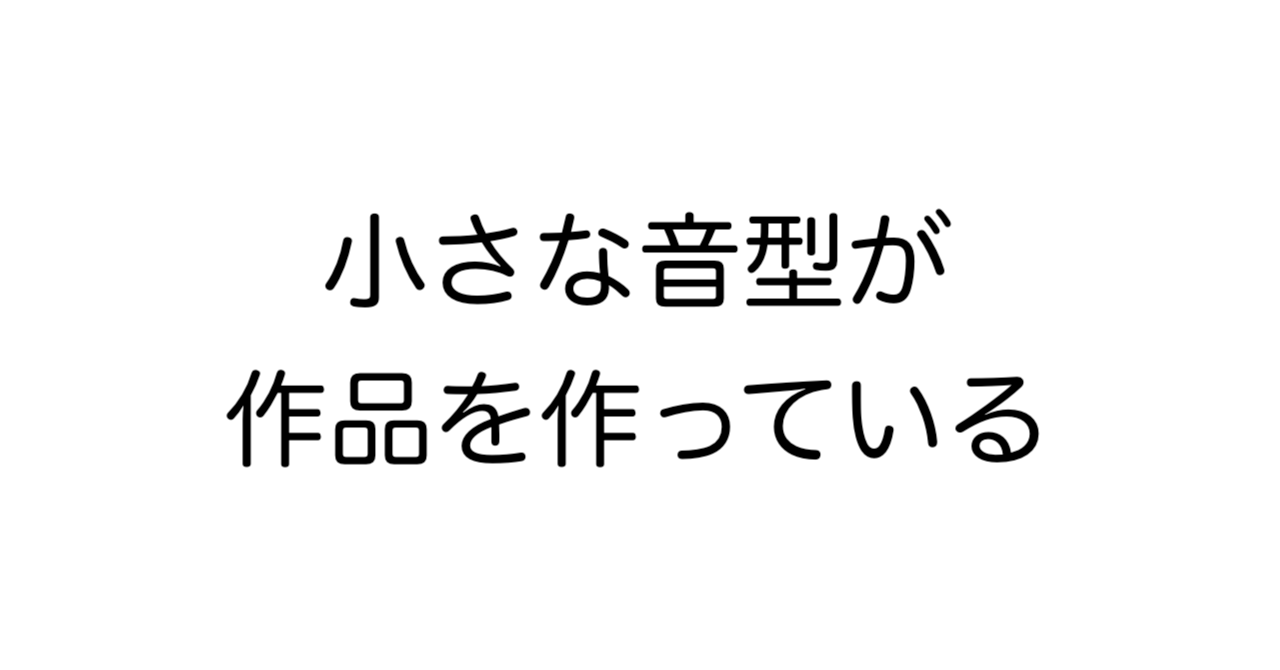
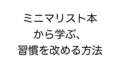

コメント