譜例(Finaleで作成)
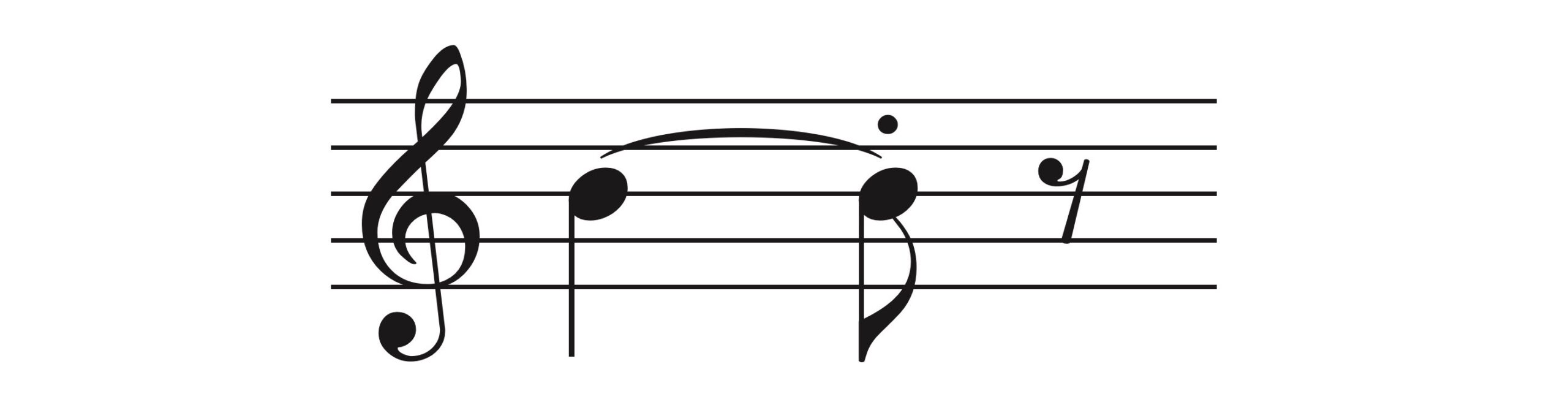
タイでつながれた音にスタッカートがついている例。
この記譜はピアノ曲でもよく見られます。
しかし、どうやって演奏したらいいか迷ってしまうのではないでしょうか。
歴史的にはいくつかの解釈がされている記譜ですが、
そのうちのひとつの解釈を解説します。
(再掲)
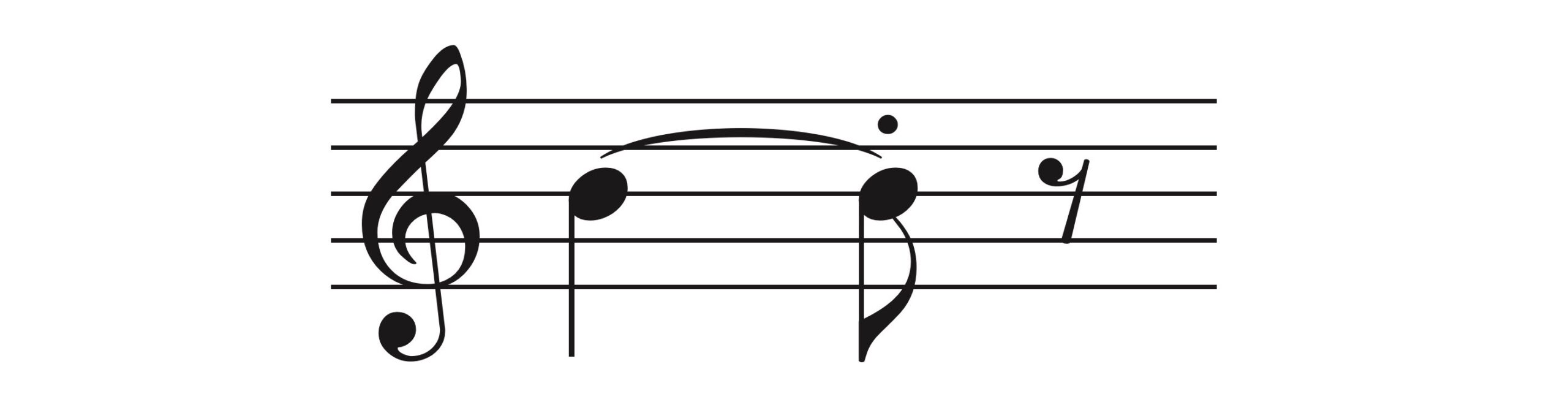
まず、譜例の場合の「音の長さ」としては
「4分音符 + 16分音符」
とほぼ同じであると捉えて構いません。
8分音符にスタッカートがついているので、
テンポなどにもよりますが
おおよそ半分の音価になると解釈できるからです。
では、どうしてあえてこのような記譜にするのかというと、
「スタッカートがついた音符で、指を上へ跳ね上げるようにする奏法の指示」
という考え方があります。
(「タイ」ですので、「打鍵し直す」という意味ではありません。)
そうすることで
「リリース(離鍵)」が急速になるので余韻が短くなる。
作曲家はこれを狙って書いているケースがあるというわけです。
音の長さ自体は
「4分音符 + 16分音符」と同じくらいでも
リリースの速さが異なると余韻の長さは変わるので
出音の表現が異なってくることが大事な視点。
指を上に跳ね上げるようにする奏法なので、
「ケル(蹴る)」
などと奏法に名前をつけて呼ぶ方もいるようです。
ささいなことのように思うかもしれませんが、
「余韻がどこで切れるのか」
これが変わると、
「直後の休符が聴感上どこから始まるのか」
といったことに影響します。
その結果、
グルーブや音楽の締まり方が変わります。
こういった細かなことを
「別にいいや」
などと決してないがしろにせず
「やってみよう」
と表現する気になれることが
上級への第一歩と言えるでしょう。
ちなみに、
こういった記譜が出てきたときは
「タイを取り払った状態で練習しておき、それができるようになったらタイを戻してみる」
という練習方法を取り入れてみましょう。
そうすると「ケル(蹴る)感覚」と「どのタイミングでケルか」
というポイントをつかむことができます。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
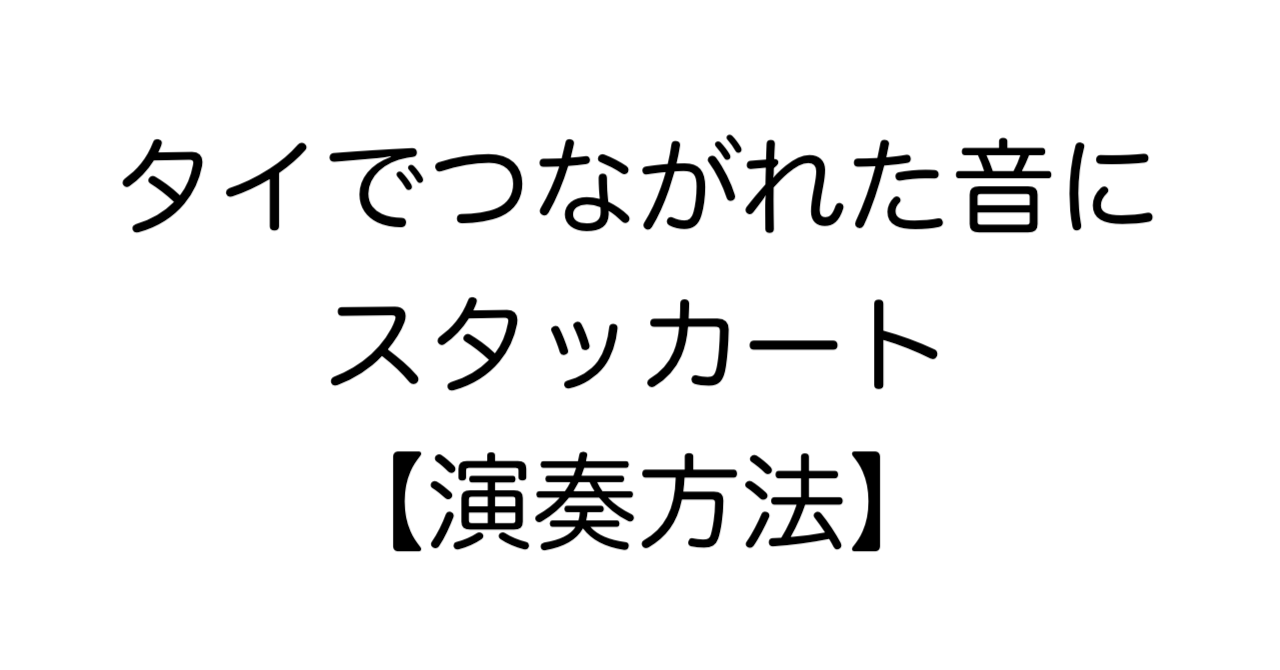
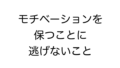
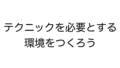
コメント