■スランプかも?と思ったらチェックすべき5項目
①「運指」に工夫できる余地を探してみる
新しく取り組んでいる楽曲が
おおむね弾けるようになってくると、
「運指」を再考する機会がなくなってしまいがちです。
しかし、
音楽的にうまく弾けないところなどは、
「その原因が運指にあるかもしれない」
と疑ってみることも必要でしょう。
運指が変わるだけで「音色」が変わります。
また、「レガート」に磨きがかかる可能性があります。
「運指」については以前に記事にしていますので
あわせて参考にしてください。
②「ICレコーダー」を活用していますか?
「自身の演奏を客観的に聴けているかどうか」
というのは、
なんとなくさらっているだけだとよくわからないものです。
一生懸命さらっていると
ピアノを前にやたらに音を出すことばかりに集中してしまい、
ICレコーダーなどで
ていねいに演奏をチェックする作業を
おこたってしまうことも多いでしょう。
いったん手を休めて
自身の演奏を振り返ってみましょう。
「ICレコーダー」についても以前に記事にしていますので、ぜひ参考にしてください。
③練習自体がマンネリ化していませんか?
これも意外と多いかもしれません。
いつも
「同じ環境」で
「同じピアノ」で
「同じ楽曲」を
「同じ練習方法」で練習していたら、
練習自体がマンネリ化してしまいます。
せめて「練習方法」を工夫してみましょう。
例えば、
「”皿回し”をするように、楽曲を区切って回しながら練習する」
「普段よりも片手練習の割合を増やしてみる」
など。
また、
「ピアノのフタを開けて練習する」
などといったように、
自分への音の聴こえ方に変化を与えるのも有効でしょう。
④楽曲の理解が深まるとテクニック的なこともクリアされてくる
ピアノというのは、
何か一つだけやったら上達する楽器ではありません。
◉ 楽曲解釈の力
◉ 練習による指と脳の運動
など、
さまざまなことがちょっとずつ積まれてきた結果、
やっと少し伸びるのです。
言葉だけ聞くと難しそうですが、
これは初心者にとっても上級者にとっても
結局は同じこと。
例えば、
基本的なことですが
今取り組んでいる楽曲に書かれている「音楽記号、用語」は
すべて調べてありますか?
「音だけを読んでいて、書かれている作曲家による指示(音楽用語など)を調べていない」
という状態は、
実は音大生などにもときどき見られるのです。
こういった細かなところもしっかりと理解して
楽曲の理解が深まると、
それが「テクニック面」や「音楽表現面」での克服につながる可能性があります。
「難しいパッセージこそ音楽的に深く理解すべき。そうすれば弾けるようになる。」
これは、とある著名ピアニストの名言です。
⑤いっそのこと、その楽曲は寝かせてしまう
どうしても伸び悩みが深刻の場合、
いっそのこと、
今取り組んでいる楽曲は寝かせてしまって
別の作品に取り組むのもアリでしょう。
独学の方の場合はもちろん、
習っている方も自身の先生に相談してみると
納得してもらえるはずです。
別の楽曲に取り組んでみることで、
伸び悩んでいた理由が
◉ 取り組んでいた楽曲の”ある部分”が現時点では難しすぎたのか
などいったことが明確になってきます。
楽曲を変えることで気分を新たに練習に取り組めるのもいいですよね。
このブログの記事は
専門の内容が中心ですので、
「初心者の自分にはそんなことわからないよ」
などと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、
結局は学習者自身が
楽しみながら練習していけるようになることがいちばん。
そのために何か工夫できることがないか
自身でも常にアンテナを張っているようにしましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
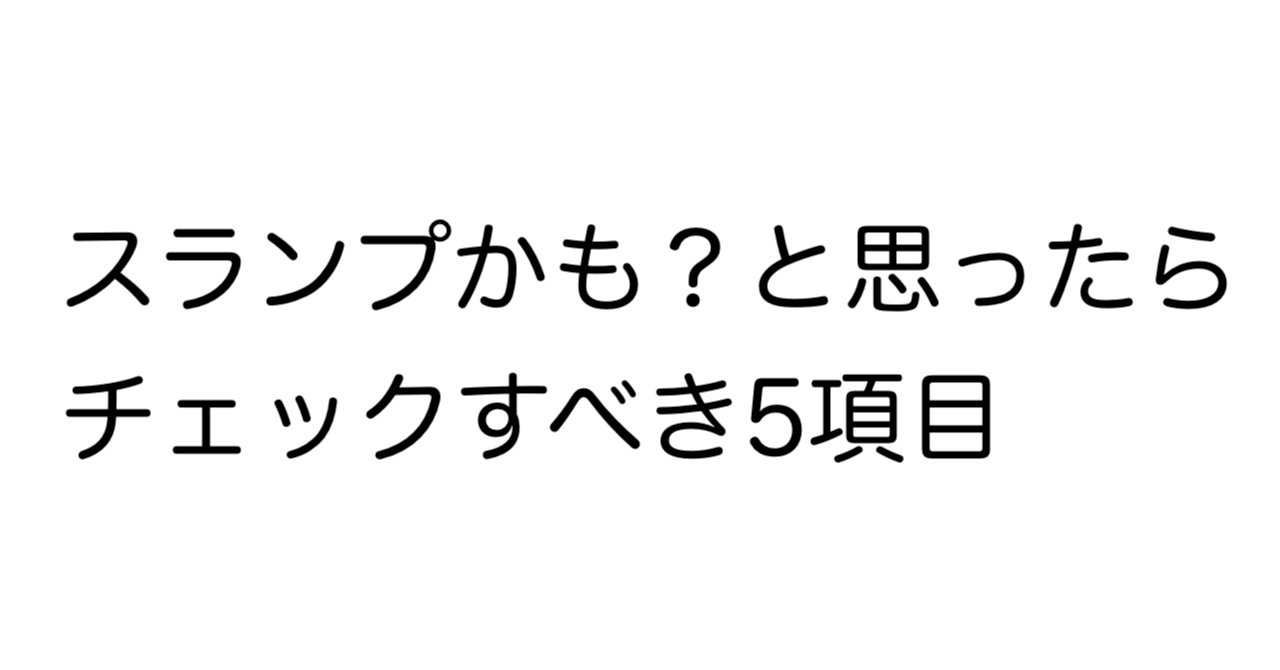
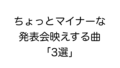
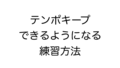
コメント