フレーズ終わりの音楽的な処理の方法は
以下の点です。
「フレーズ終わりの音」は大きくならないようにおさめるのが基本
具体例を見ていきましょう。
譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭のメロディ)
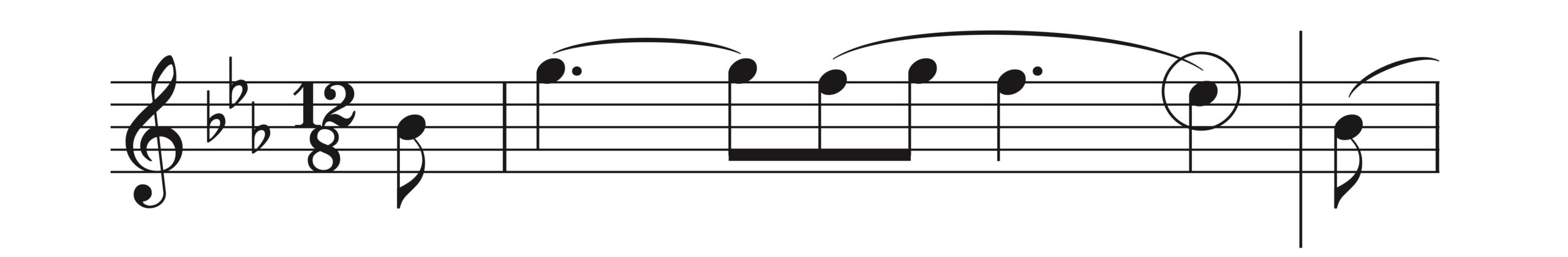
スラーを確認することで、
丸印をつけた「Es音」が
「フレーズ終わりの音」
であることは分かりますね。
つまり、
このEs音が大きくとび出てしまうと音楽的に不自然なのです。
直前の付点4分音符「F音」よりも
大きくなってしまわないように。
こういった考え方は楽曲が変わっても同様です。
楽譜をみて
「フレーズがどこで終わっているのか」
を見つけましょう。
そのためには、
「作曲家がつけたスラー」
も参考になりますが、
「メロディだけ歌ってみる」
もしくは
「メロディだけ弾いてみる」
といった方法も有効です。
一方、
この考え方には例外があります。
ベートーヴェン「ピアノソナタ第2番イ長調 作品2-2 第1楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成、58-60小節目のメロディ)
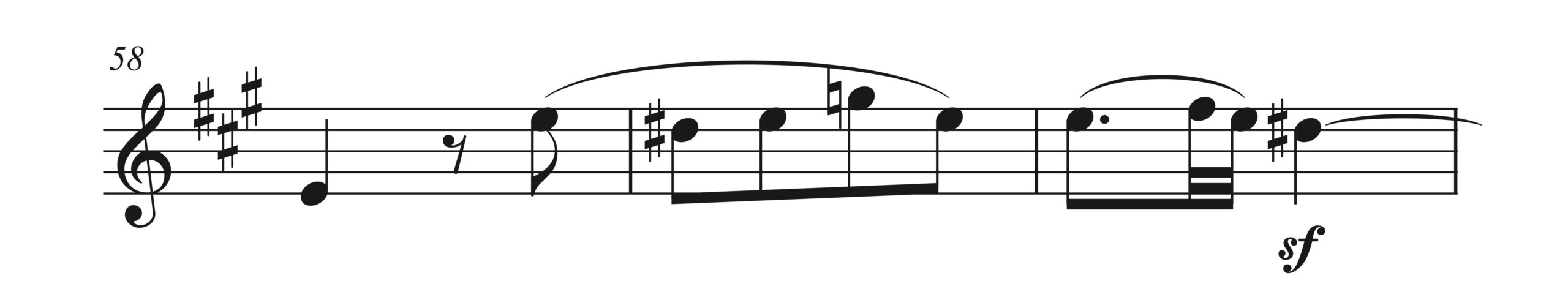
sf がついている音に注目してください。
本来はこのDis音は
「フレーズ終わりのように聴こえる位置にある音」
ですが、
ベートーヴェンはsf をつけることで
フレーズ終わりがここよりも先に来るように延長しています。
先ほど、
「フレーズ終わりの音」は大きくならないようにおさめるのが基本
と書きましたが、
ここではsf という
「作曲者による特別な指示」
がありますので
その音に重みを入れて演奏します。
ここで何が言いたいかというと、
フレーズがどこで終わっているのかを見つけるためには、
「メロディだけ歌ってみる」
もしくは
「メロディだけ弾いてみる」
という方法をとるだけでなく、
「作曲家による “記号などの指示” も見落とさずに読み取っていく必要がある」
ということ。
「フレーズ終わりの音楽的な処理の方法」は
まずはこれだけを意識できれば充分です。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
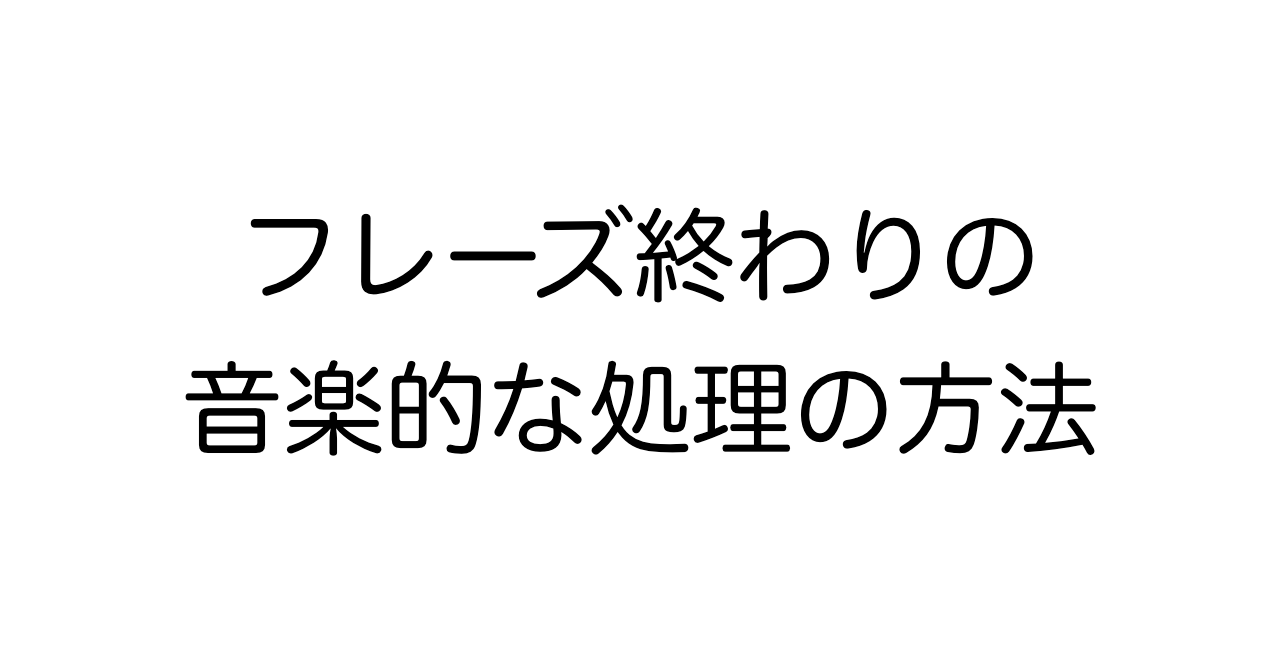
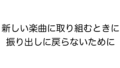
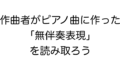
コメント