メロディというのは抑揚が分かりやすいので
「歌おう」と思えば、
まずは「メロディを歌うこと」に意識がいきますよね。
しかし、
メロディを歌うことに意識を向けることができていても
「伴奏部分を歌うこと」
これは忘れてしまっている演奏が多い。
メロディと伴奏で真逆のことを表現している楽曲も
ときどきありますが、
基本的には
メロディがカンタービレの時には伴奏もカンタービレ。
メロディがペザンテの時には伴奏もペザンテ。
メロディの波動の動きに寄り添った伴奏にしてあげましょう。
具体的には「音色」に気を配ることが必要。
例えば、
モーツァルト「ピアノソナタ K.545 第1楽章」の曲頭でしたら、
メロディが歌にあふれているのですから、
左手のアルベルティ・バスは決してガツガツ弾かないこと。
「歌う」というのはメロディのことだけではありません。
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

また、
多くの楽曲で必ずといっていいほど出てくる
「時間的な強弱変化の表現」
にも注意が必要です。
「時間的な強弱変化の表現」というのは
ロマン派の多くの作品では
「心情の変化」
を表している傾向があります。
「クレッシェンドのときにメロディだけで盛り上げずに、伴奏も一緒にクレッシェンドする」
などといったように、
それぞれの表現に関連性を持たせてあげるといいでしょう。
(あえてメロディだけにクレッシェンドが書いてある楽曲は、この限りではありません。)
重要なのは
「”メロディの表現に対してどのように伴奏を扱っていけばいいのか”ということに意識を向ける習慣をつける」
この点だと言えるでしょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
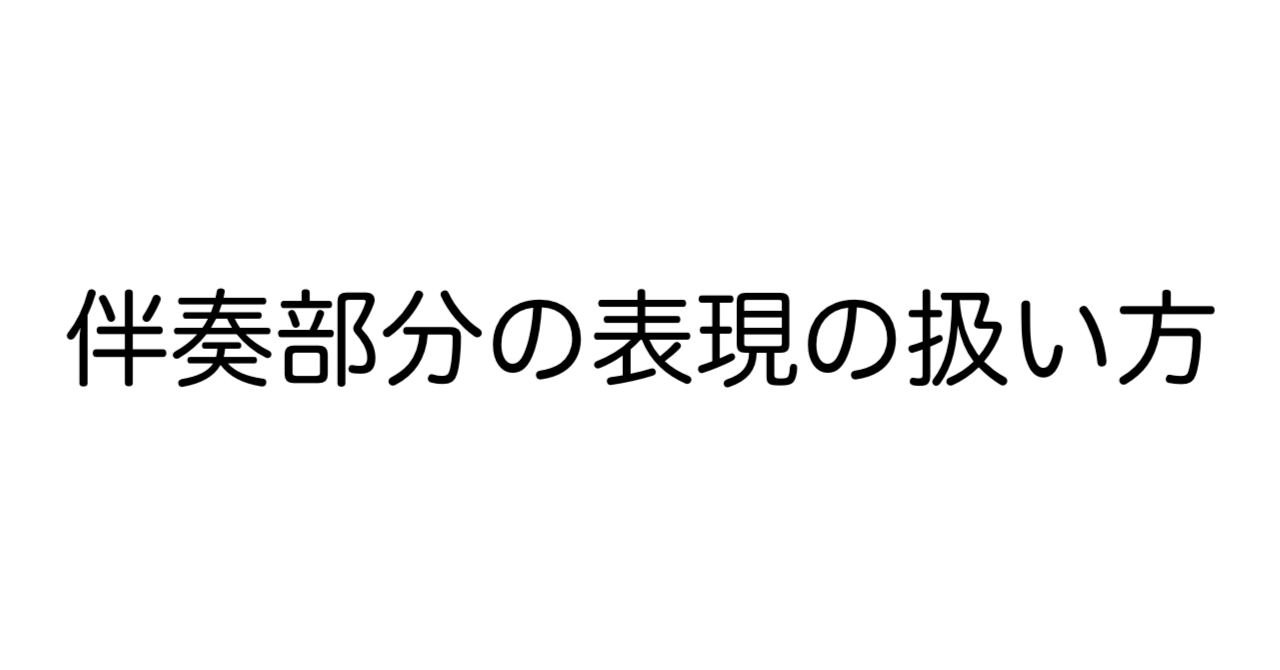
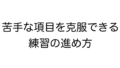
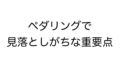
コメント