上記の第1弾の記事では、
対比を作れる要素として
以下の3点を挙げました。
◉ リズム
◉ 音色
この3点はもちろん
新たな要素にも注目して
以下の譜例を読み取ってみましょう。
モーツァルト「ピアノソナタ第5番 K.283 第1楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)
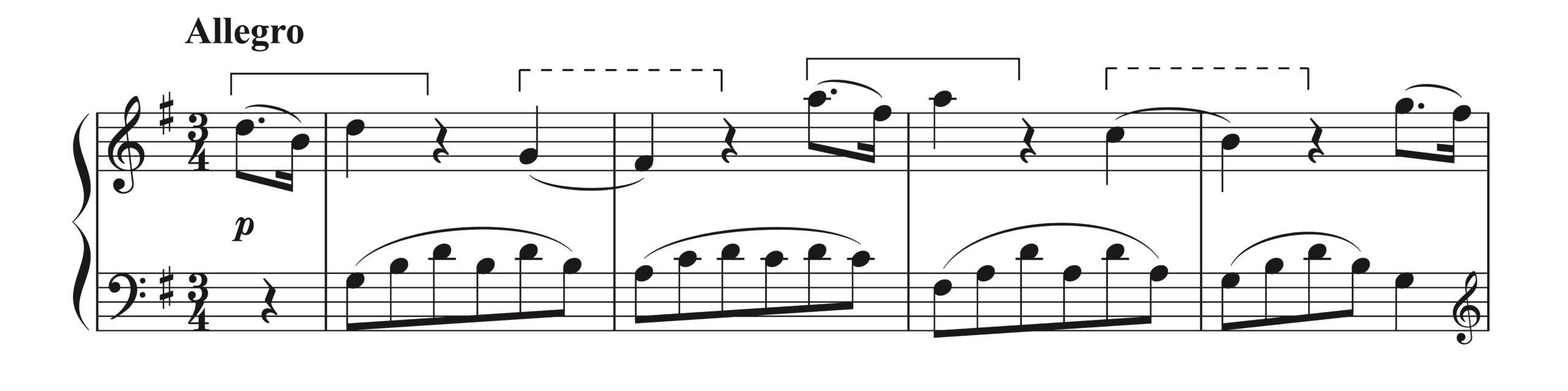
実線カギマークの音型で問いかけて
点線カギマークの音型で応答しています。
実線カギマークのリズム音型に注目すると
16分音符の細かな音価が含まれています。
それに対して
点線カギマークの音型は4分音符という長い音価。
前者の方が「軽さ」を感じますね。
16分音符が含まれているのは、
モーツァルト自身が「軽さ」を感じていた証拠です。
「軽さ ⇆ 深さ」
これらの対比を読み取ってください。
(再掲)
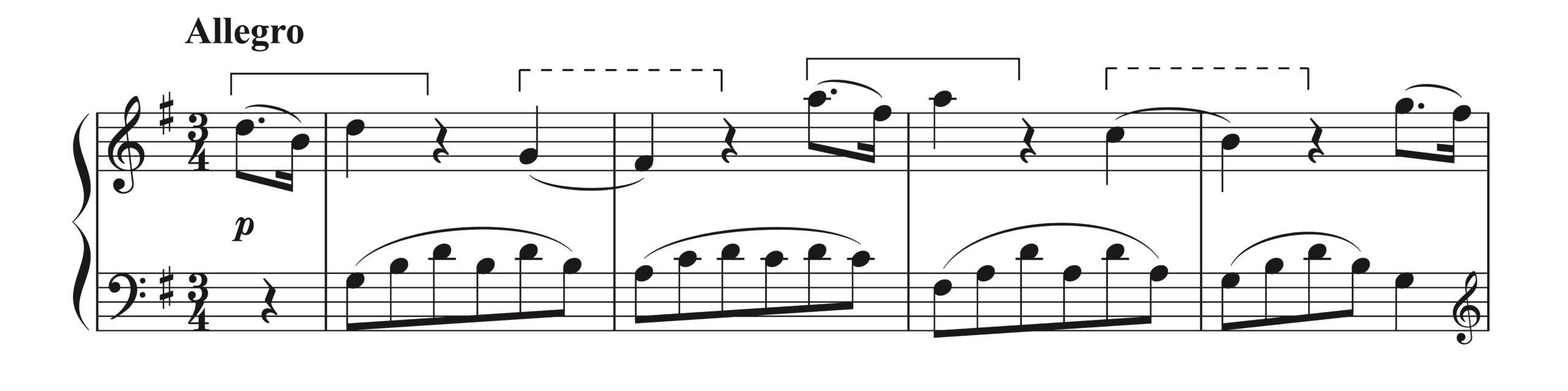
次に「音域」に注目しましょう。
実線カギマークの音型のほうが高い音域で出てきます。
やはり、
音域という観点でも
「軽さ ⇆ 深さ」の差を感じることができます。
では、どう演奏すればいいのかについてですが、
結論としては
点線カギマークの音型のほうが
やや太い声で演奏していいでしょう。
同じくらいのダイナミクスで弾いている演奏も多いのですが
「対比」という観点で言うと
少し差をつけて演奏することを推奨します。
いいですか、
主役よりも脇役のほうが大きくなってしまったら
これはおかしいのですが、
「問いかけ」に対する「応答」というのは
どちらが主役でどちらが脇役かは決まっていません。
楽曲によって、その都度読み取る必要があります。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
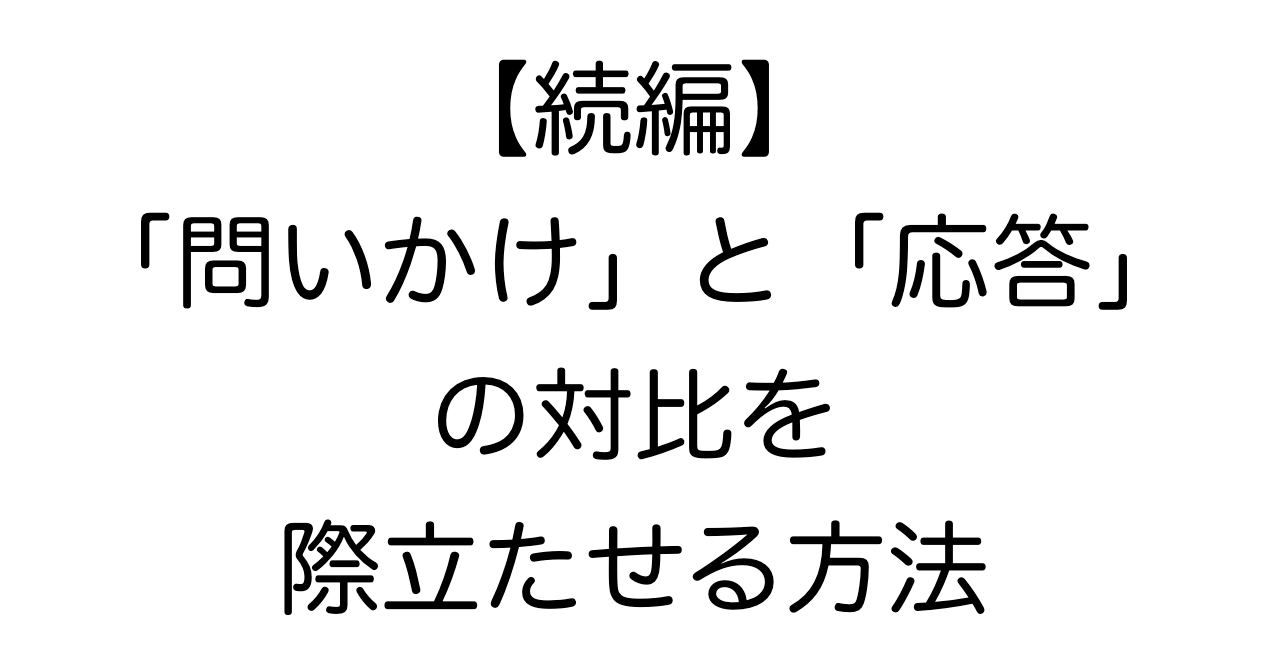

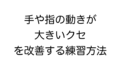
コメント