「間(ま)」というのは
上手く使うことで
◉ 音色をガラリと変えることができる
◉ 音量を上げなくても強調したように聴かせることができる
などをはじめとして、
表現の味方になってくれます。
しかし、
このブログで何度も書いているように
音楽の流れを止めてしまうような「間(ま)」をとることほど
もったいないことはありません。
「間(ま)」を取るべきでないところの典型例を
ひとつ見てみましょう。
具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
ブルーメンフェルド「左手のためのエチュード op.36」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43-44小節目)
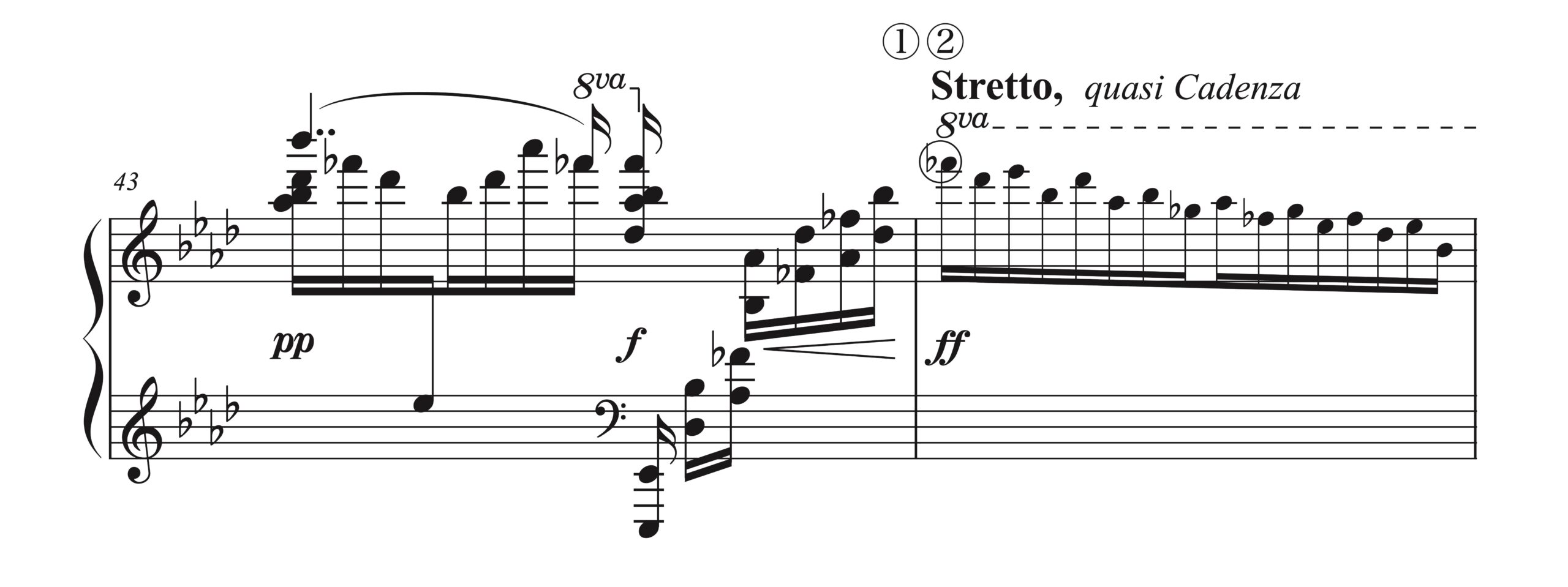
小音符のところからは
カデンツァ風になっています。
ここの入り、
つまり「①(小節の変わり目)」の部分で「間(ま)」をとってしまうと
音楽が停滞してしまいます。
やってしまいがちな典型的音型例です。
どうしてなのか分かりますか。
クレッシェンドで音楽の方向性が示されており、
明らかに丸印をつけたFes音が頂点で
そこへ音楽が向かっているのに
その前で一息ついている場合ではないからです。
(再掲)
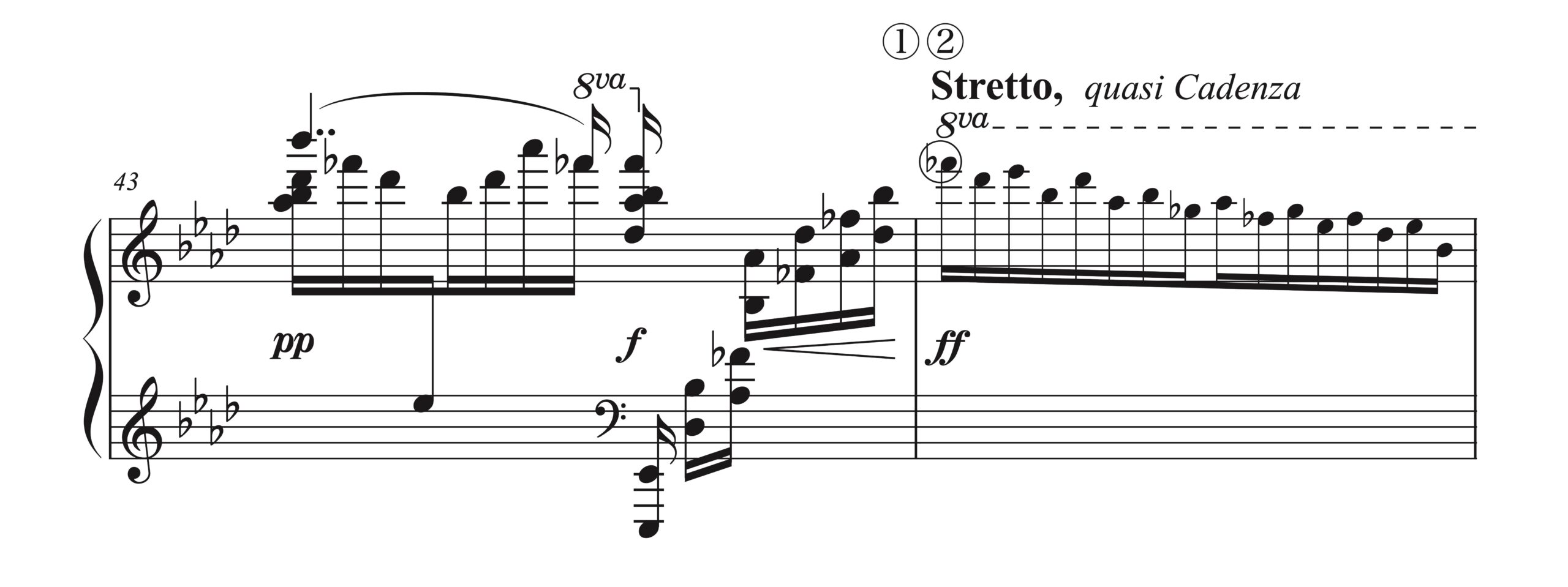
①のところでのろくなってはいけません。
もし待つのであれば、②で待ってください。
ノンストップで②へ入ってしまって、
それからショートフェルマータ。
待つところが音符ひとつぶんずれただけで
一気に音楽の方向性が明確になるのを
感じることと思います。
音符は一通り弾けるようになってからが勝負。
といいますか、
譜読みの段階から
こういうことも読み取れるようになるのがベストです。
楽譜から
「音楽の方向性」
つまり
「エネルギーの流れ」
を読みとってください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
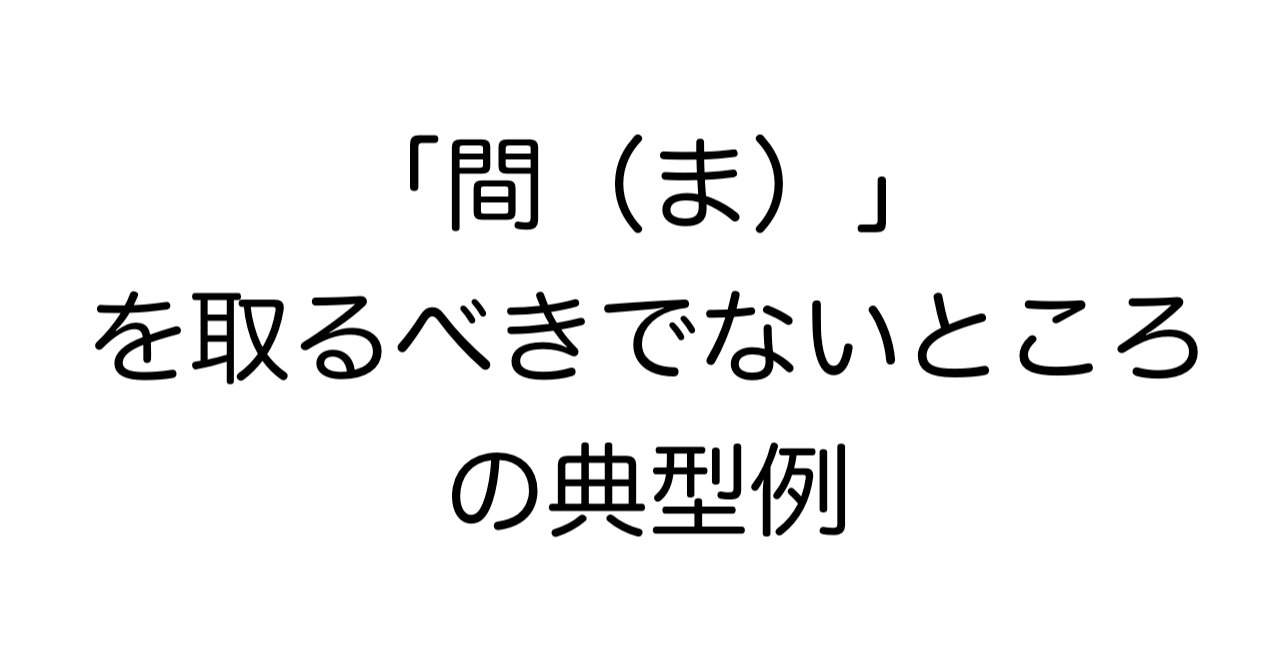
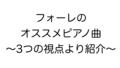

コメント