作曲家は、楽曲のあらゆるところで「対比表現」を用いています。
この表現があるからこそメリハリが生まれ
聴衆は飽きずに聴くことができます。
対比に関しての演奏者としての仕事は、
「作曲家が残した対比表現を見つけて、それを表現すること」
と言えるでしょう。
対比表現が出てきても
それを対比だと思っていなければ見つけることはできません。
「対比表現の見つけ方」とは
「対比の表現方法を知っておく」
ということと同じなんです。
知っていれば見つけることができます。
この表現は多岐に渡りますが、
オーソドックスなものは以下の10点です。
■オーソドックスな対比表現の一覧
① ダイナミクスによる対比
p と f の交替、
f と p の交替、など。
② 音域による対比
低い音域から高い音域への移行、
高い音域から低い音域への移行、など。
③ 音の数による対比
ある区切りから音数が大きく変化して直前と雰囲気が変わる、など。
④ 音色による対比
楽曲によっては una corda の指示が出てきたりと
作曲家が音色の変化による対比を要求しているケースがあります。
⑤ ダンパーペダルの有無による対比
これについても、
楽曲によっては作曲家がダンパーペダルの有無による対比を
要求しているケースがあります。
ダンパーペダルを使うと音が全て和音化され、ウエットな印象になります。
反対に、ノンペダルだとドライな印象になります。
⑥ 音型やアーティキュレーションによる対比
音型が大きく変わったり、
レガート中心のセクションからスタッカート中心のセクションに移行したり、など。
⑦ 調性による対比
durからmollへの移行、
mollからdurへの移行、など。
もちろん、
「durから別のdur」
「mollから別のmoll」
への移行であっても
調性によって雰囲気が違うので
広義での対比とみなされる場合もあります。
D-durとGes-durの響きの違いなどはかなり大きいので
耳で確かめてみてください。
⑧ 拍子による対比
単純拍子同士の交替よりも、
単純拍子から
複合拍子、変拍子への交替の方が
変化は大きく感じます。
こういったところでも対比が表現される可能性あり。
⑨ テンポによる対比
テンポが大きく変化するのも対比表現の一種です。
「だんだん速く」「だんだん遅く」
というのは
聴いている側が変化を徐々に感じていくので対比効果は薄く、
ガラリといきなりテンポが変わる方が
対比効果は大きくなります。
⑩ フレーズの長さによる対比
長いフレーズと短いフレーズの交替、
短いフレーズと長いフレーズの交替など。
対比表現のうち、
オーソドックスな10点をまとめました。
実際の楽曲では
これらの「組み合わせ」で表現されていることも多くありますので、
譜読みの際に注意深く読み取っていきましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
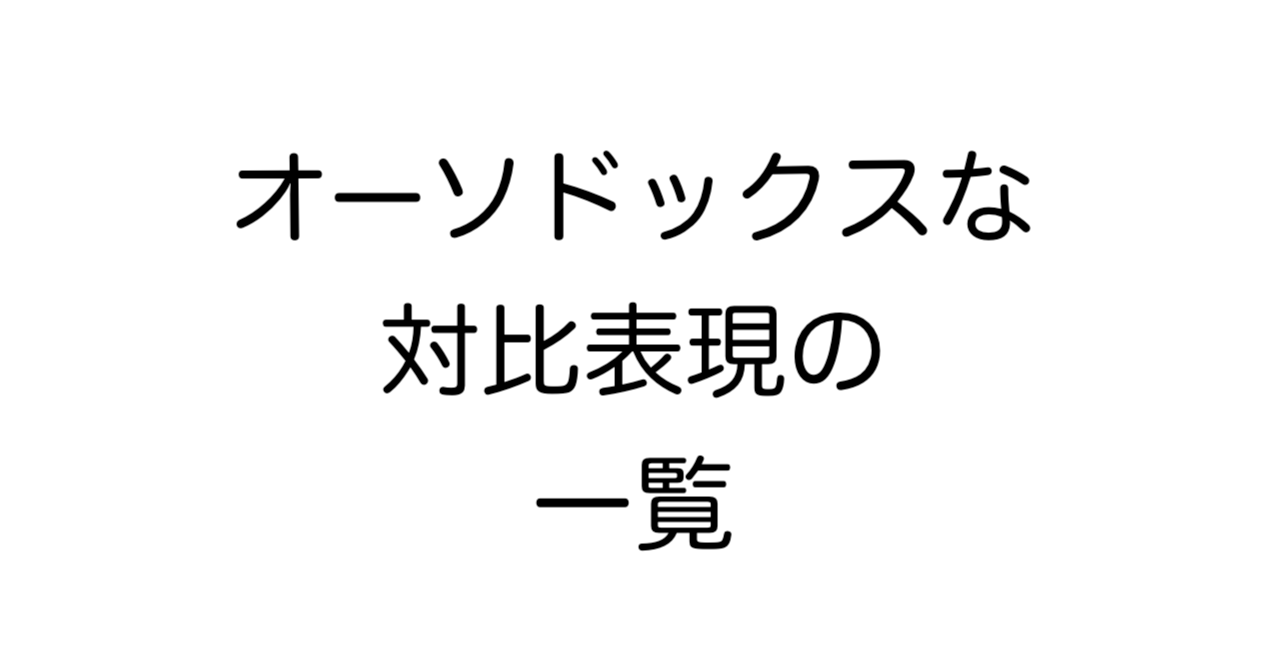
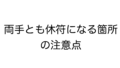
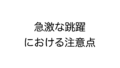
コメント