♬ ピアノの構造や音楽史を勉強しようと思っている
♬ 勉強を始めているけど、頭に入ってこない
こういった方へ向けた記事です。
「ピアノの構造」や「音楽史」などの
知識的なことを学ぶことの重要性は
以前から何度もお伝えしてきました。
◉ ピアノをやっていたら純粋に興味をもった
など、理由はなんでも構いません。
とにかく始めてみることをオススメします。
一歩踏み出して学習を始める方のために、
筆者がオススメする
身に付く勉強方法をお伝えします。
やり方は、とてもカンタンです。
「 ”はじめて” という用語を見つけたらすべてに線を引く」
これが超重要ポイント。
参考書などを使って学習するときに、
「作曲家◯◯がはじめて音楽教育を受けた時期は〜」
「打鍵の力の影響をはじめに受ける部位は〜」
など、
文中に「はじめて」という用語が出てきたら
絶対に見逃さないでください。
「はじめて」というのは
歴史はもちろん、知識的なことを学ぶ上で
絶対に外せない部分だからです。
外してしまうと、
「知識が時系列に並ばない」という結果になり
整理された学習ができません。
流れが理解できていると
ただ覚えやすいだけでなく、忘れにくい。
仮に忘れても、復習するとすぐに戻ってくる。
いろんなところからいろんなものを
つまんで覚えただけの学習では
身にならないんです。
学生の頃に歴史の先生から
「必ず、キーパーソン(重要人物)をおさえよ」
と習ったと思いますが、
「はじめて」にまつわるものというのは、
キーパーソンも含めて
まぎれもなくキーワードです。
「創始者」
などといった、
「はじめて」に類似した用語にも目を光らせましょう。
近年では、
すべてを「動画学習」で済ませる方もいらっしゃると思います。
特に「ピアノの構造」に関しては
動画学習も効果的ではありますが、
必ず「書籍」も手に取って
「体系的に積み上げ式で学ぶこと」
を並行してください。
「忘れたらこの一冊に戻ってくる」
という支えを手元に置いてください。
やや根気が要ることは確かです。
しかし、そうすることで
「かいつまんで手を出して、すべて忘れて振り出し」
という中途半端な学習を避けることができます。
単にピアノを演奏するだけでなく
知識的なことがあわせて身についてくると、
演奏に活かせますし
音楽の理解が深まり楽しみが増えますし
色々な方と話ができるようにもなります。
いいことづくめ。
ピアノへ向かえない時間などを有効利用して
ぜひトライしてみてください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
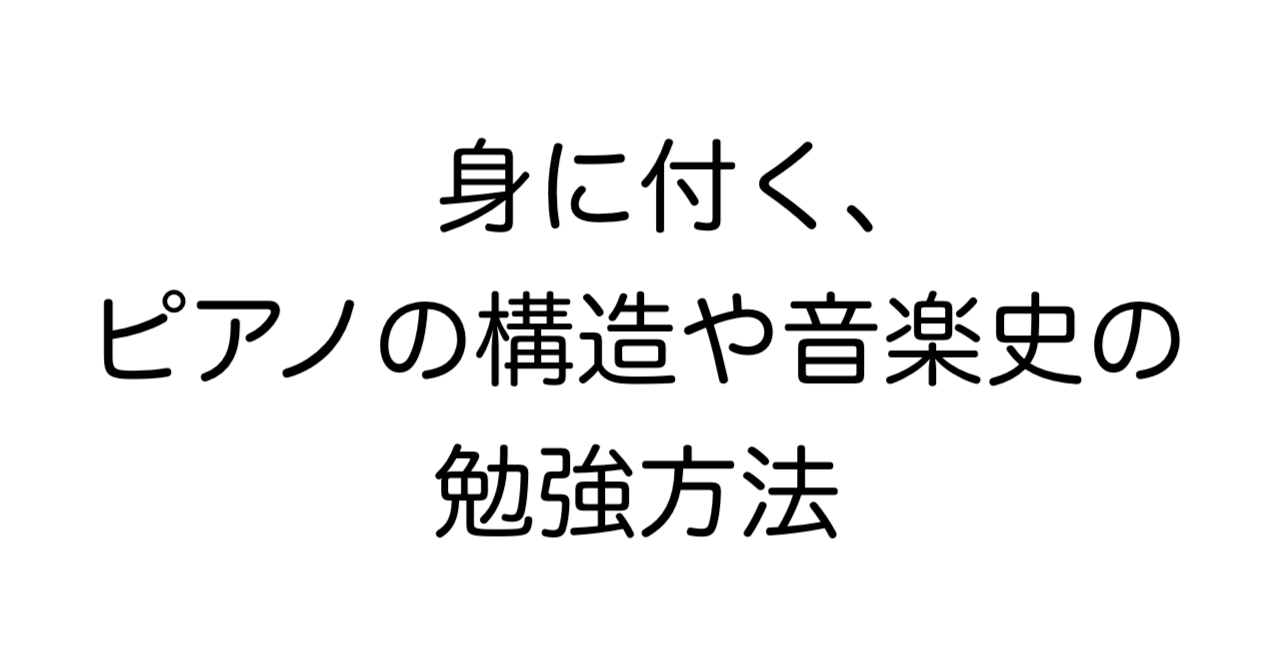

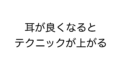
コメント