譜例を見てください。
譜例(Finaleで作成、1-2小節)
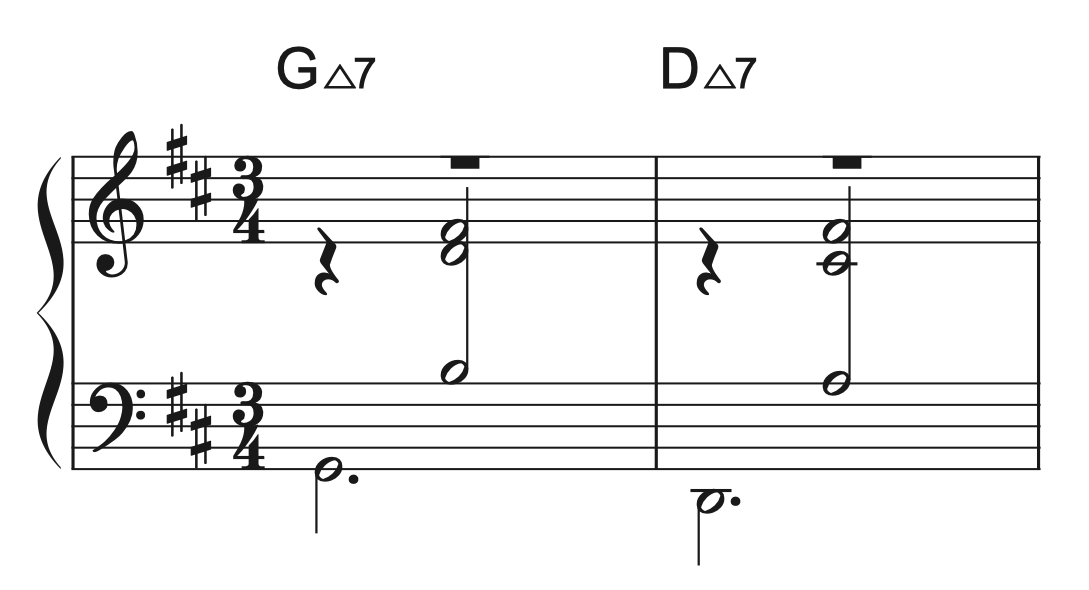
上段に、「全休符」が入っていることに注目してください。
なぜ声部分けしてまで全休符が入っていると思いますか?
つまり、
サティは作曲段階から
この右手の和音を「伴奏」だと想定しているのです。
聴衆は、5小節目でメロディが出てきたときに初めて、
「今まで聴いていたのは伴奏だったんだ」
と気付くわけです。
(もちろん、すでに有名な楽曲ですので多くの方が知っていますが、
「音楽のつくりの話では」という意味です。)
しかし、
もし仮にこの楽曲を全く知らない方が聴いたら
1-2小節目の和音それ自体を旋律だと思うはずです。
「旋律かと思ってしまう伴奏」
音楽のつくりのアイディアとして面白いと思いませんか?
私はこういうことを感じるたびに
ワクワクしたりウズウズしたりしてたまらなくなります。
こういったことを知っておくと
演奏にも活かせます。
5小節目の旋律が出てきた時に
音色を変えて新鮮な旋律として聴かせる必要があり、
直前の「旋律かと思ってしまう伴奏」と
同じ音色や同じダイナミクスで弾いてしまうのは
楽曲のことをよく理解していない証拠となってしまいます。
「旋律かと思ってしまう伴奏」を使った例は
ピアノ曲だけに限らず多くの例があります。
ぜひ探してみてください。
そういった視点で楽曲を聴くクセをつけると
知らずのうちに他の要素のこともよく理解できたり
発見できるようになります。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
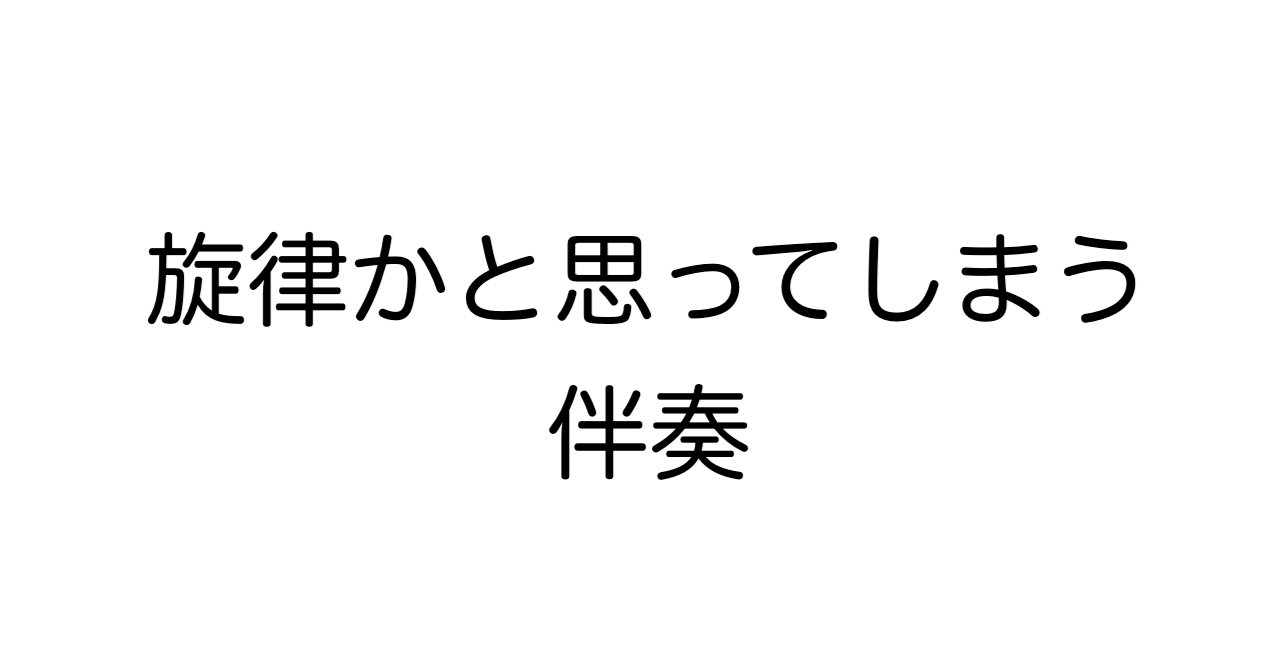
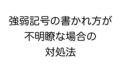
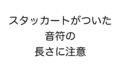
コメント