sf(スフォルツァンド)は
一般的な意味としては
となっています。(「楽典―理論と実習 石桁真礼生 著(音楽之友社)」より)
しかし、以下のような意図で書かれる場合もあります。
「そこからフレーズを新しくしたい」
したがって、
sf を見かけたときに
「ただ強調したいのかどうか、それとも…」
などといった意図を読み取る必要がありますね。
加えて、
特に ”ドイツ” のきちんとした音楽教育機関では
「sf はダイナミクスを一段階上げる」
という指導をすることが多いのです。
fff が初めて用いられたのは
ベートーヴェン「交響曲 第7番」の中だと言われています。
それまではまだ fff が無かったですし、
ベートーヴェンの他の作品を見ても
「 ff +sf 」でfff を表現しています。
ポイントとしては、
「sf を何でもかんでもff やfff のように演奏してしまわないこと」
これが重要です。
sf を見ると、とにかく思いっきり強調して
「びっくり箱的表現」をしてしまいがち。
しかし、
の中にも以下のように書いてあります。
f の中で用いられた sf は ff ぐらいに奏する必要があろうし、
p の中で用いられた sf は mp か mf ぐらいに奏するのが普通である。
(抜粋終わり)
p の中で用いられたsf をff やfff のように弾くのは
余程の意図がない限り避けておいた方がベターです。
びっくり箱的表現は fp や ffp で表現されます。
著者の石桁真礼生氏は、やはりドイツ系統の方です。
この流れの知識で書かれたのが、この書籍。
ダイナミクス記号の解釈については
以下の記事も参考にしてください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
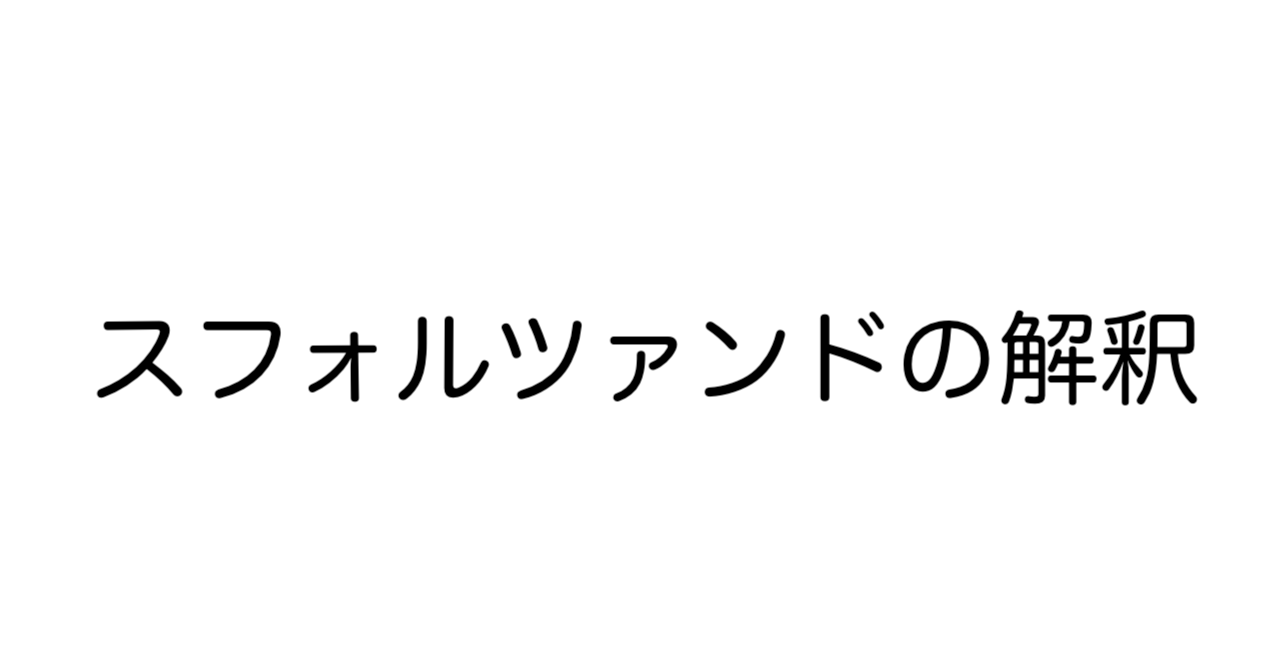
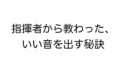
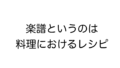
コメント