譜例を見てください。
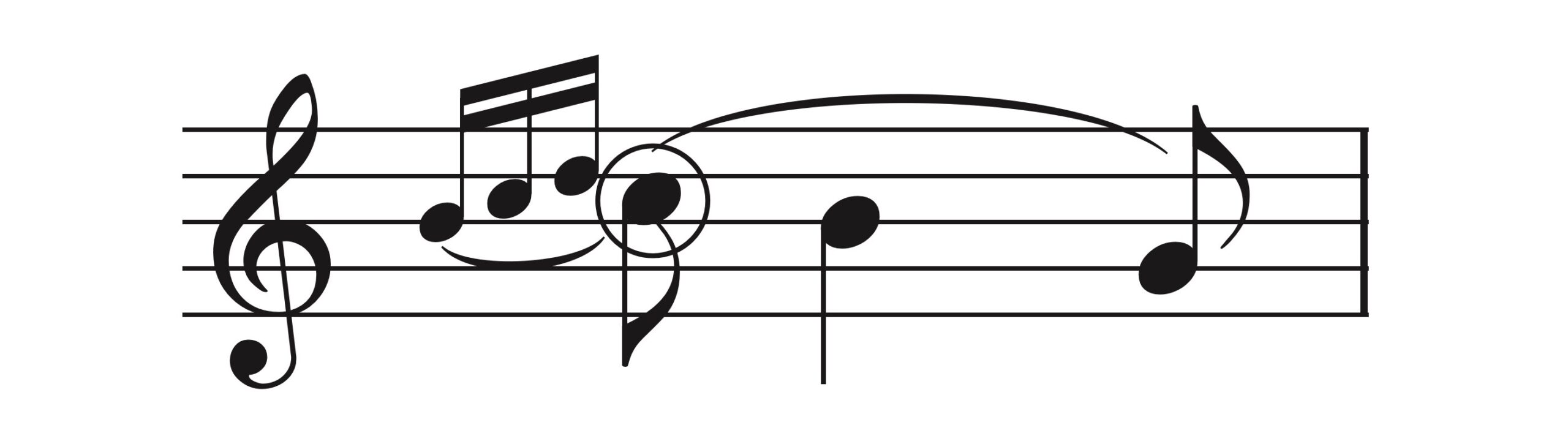
装飾音は、1音だけ引っ掛けるケースが多いですが、
譜例のように複数個つらなるケースもありますよね。
例えば、
ベートーヴェン「ピアノソナタ第10番 ト長調 作品14-2 第1楽章」
などでは、譜例のような3音を引っ掛ける例が出てきます。
演奏上の注意点としては、
「装飾直後の音(丸印をつけた音)が埋もれないようにする」
ということ。
このような直後の音は、
1音だけ引っ掛けるケースよりも
複数音の場合の方が埋もれがちになります。
演奏ポイントとしては、
他の記事の繰り返しになりますが
「装飾音符はあくまでも”装飾”なので、極めて軽く入れる」
これが重要。
丸印をつけた音が埋もれてしまう原因には
「装飾音が目立ちすぎているから」
という理由もあるのです。
装飾音符を取り払って練習してみることで
一度、デッサンと言いますか「楽曲の骨格」を理解しておくことも重要です。
装飾音を見かける度に
「どうしてその音は通常の音符ではなく、あえて装飾音符で書かれたのだろう」
と考えるクセをつけてください。
そうすることで、
装飾音の
「処理の仕方」
「演奏のニュアンス」
という部分のイメージが明確になります。
通常の音符のようにゴリゴリと弾いてしまい、
直後の大きな音符の存在を邪魔しないように気をつけましょう。
「装飾音」カテゴリーでは、
装飾音関連の別例も取り上げています。
あわせて参考にしてください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
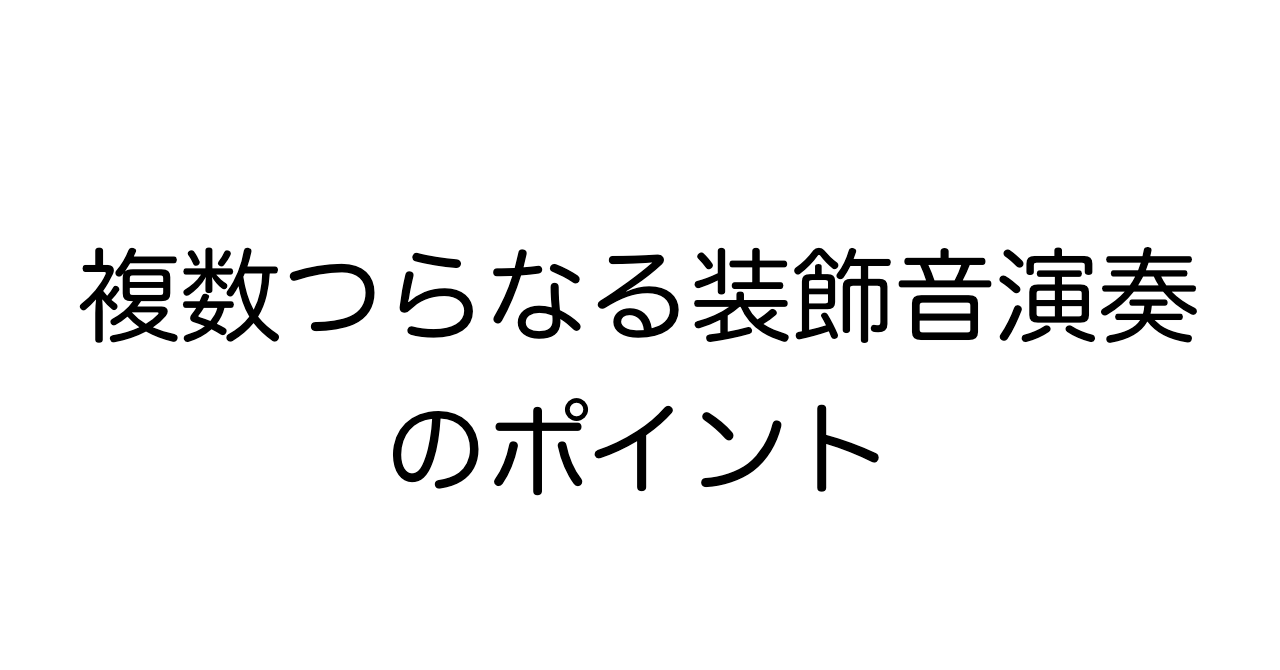
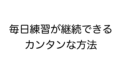
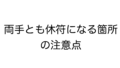
コメント