譜例を見てください。
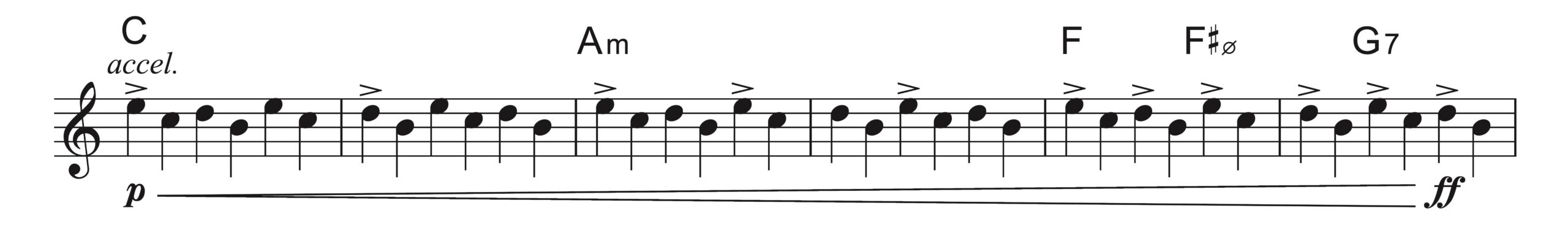
この譜例の中には
せき込み感を表現するためにとられた手法が5つも含まれています。
① accel. によるテンポのせき込み
② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み
③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み
④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み
⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み
② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み
③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み
④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み
⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み
実際の楽曲では
これらの手法が「単独」で出てきたり
譜例のように「組み合わせ」で出てきたりもします。
① accel. によるテンポのせき込み
この項目はせき込みの表現だと分かりやすいですが、
② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み
③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み
④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み
⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み
③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み
④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み
⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み
これら4項目は、意外とせき込みの表現だとは気づかないものです。
せき込み以外の場合でも使われることがあるからです。
実際は、
①がせき込み表現の基本で
②③④⑤を併用することでその効果を高める、
などといった使われ方がされています。
④に関して
「ハーモニーが変わることも一種のリズム表現」
ということを認識しておきましょう。
今回は譜例を簡略化するためにコードネームだけを書きましたが、
クラシック作品ではコードネームは書かれていないので
伴奏部分などでハーモニーチェンジを判断することになります。
せき込み表現のうち代表的な5項目を挙げました。
こういったことを理解しておくことで
譜読みで読み取れる情報量が増えてきます。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!
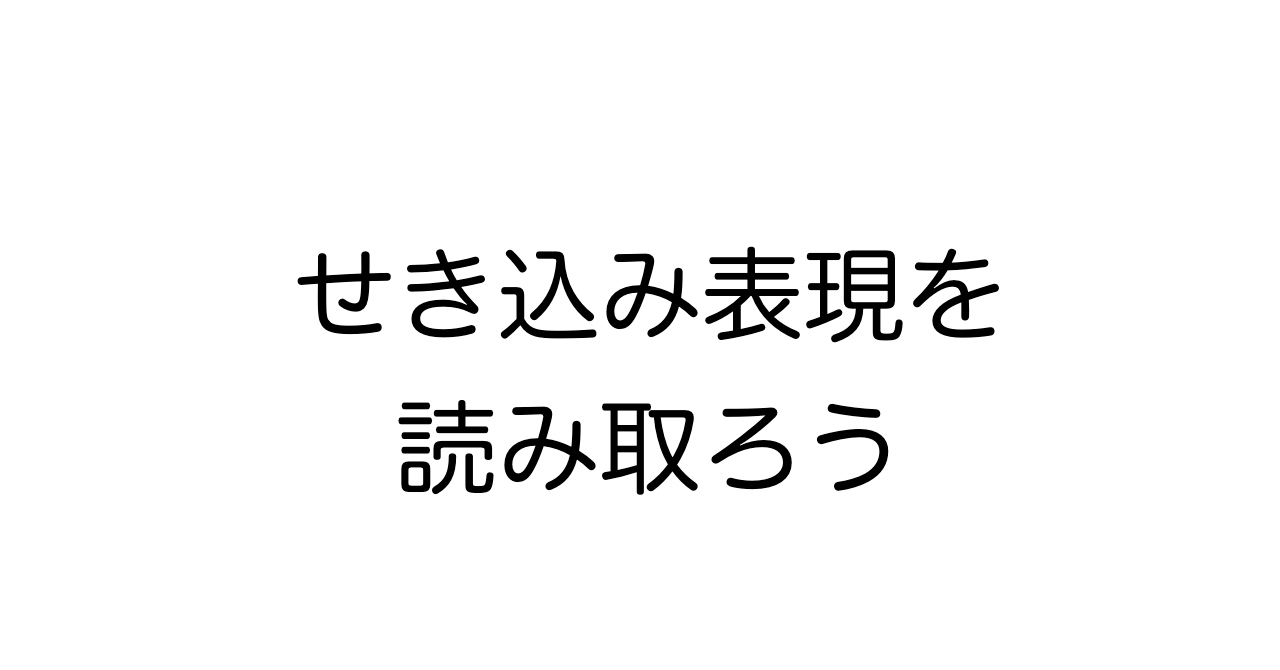
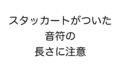
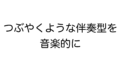
コメント