■「曲名」や「舞曲の名称」は目安程度で考えよう
♬ 20世紀につけられた「別れの曲」というタイトル
ショパンの「別れの曲」はよく知られているタイトルですね。
実はこのタイトル、
ショパン自身がつけたタイトルの日本語訳ではなく
「後年になってからつけられたタイトル」です。
もちろん、
作曲家自身がつけたタイトルではなくても
特定のイメージを浮かべるためには
効果的なこともあります。
しかし、
「作曲家の意図をくみとる再現芸術」
という面をあわせ持つクラシック音楽の特徴を考えると
第三者がつけたタイトルにとらわれすぎてしまうのは考えもの。
第三者がつけたタイトルというのは、
作曲者の歴史などをていねいに調べた上で
考えられているものもあれば、
聴いた感じの雰囲気で
なんとなくつけられているものもあるのです。
♬ 舞曲は1つの名称で示せるほどワンパターンではない
「舞曲などの名称がそのままタイトルになっている楽曲」
は多くあります。
一方、色々な楽曲をみてみると
「ポロネーズ」
「メヌエット」
などといった楽曲タイトルは
「内容の、ある一定の傾向」
という程度でしかないことがわかります。
つまり、
内容に幅がありすぎるのです。
楽式の基礎的な部分を学んだら、
あとは一曲一曲
「その舞曲の中の別の顔」
として見ていくしかありません。
「楽式論(音楽之友社)」
などの書籍を通して
その舞曲の基本を知っておくことは必須だけれども、
「メヌエットとはこういうものだ」
などととらわれすぎると
それ以上理解が先へ進まなくなる可能性がある、
ということ。
基礎を知っていて柔軟に考えられるのと
知らないのとでは
大きな違いがあるのは確か。
「基礎はしっかり学び、いったんそれが身体に入ったら、もうとらわれすぎない」
この姿勢が大切です。
ピアノ演奏に活かせる!参考書「楽式論(音楽之友社)」レビュー
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
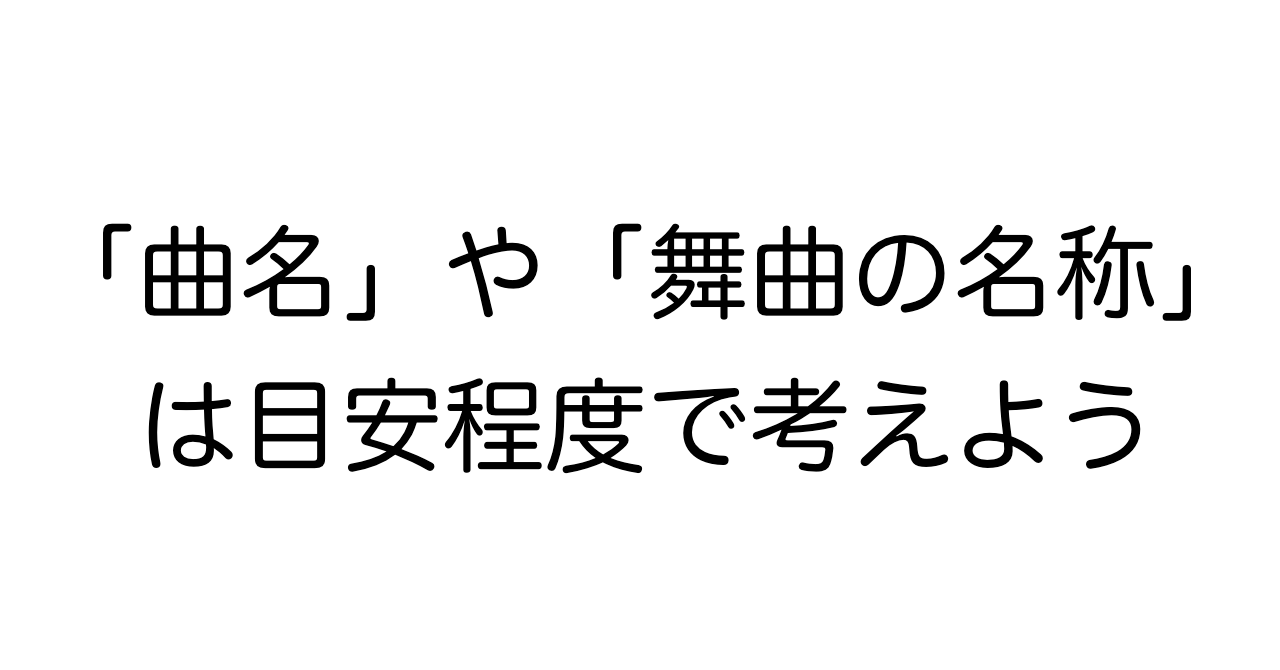

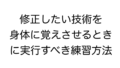
コメント