譜例を見てください。
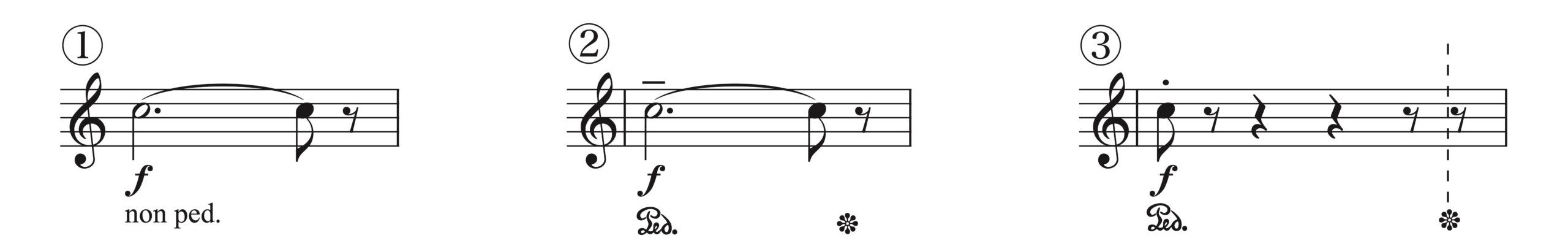
①〜③まで、
「同じ強さ」「同じ高さ」
そして、「同じ長さ」の音です。
しかし、どれも出てくる音色は異なります。
①は、
「non ped.(ノンペダル)」で演奏し、指で音価分を伸ばしている例です。
ノンペダルなので
ダンパーペダルを踏むことによる響きが加わりません。
したがって、ドライなサウンドが得られます。
(再掲)
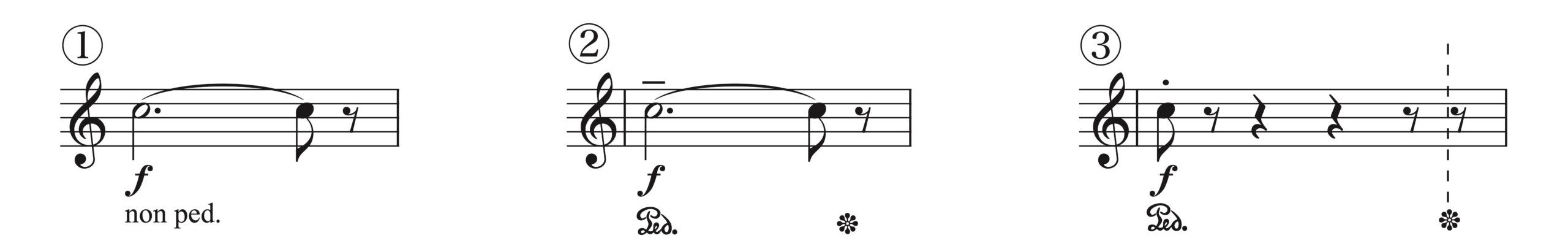
②は、
ダンパーペダルを踏み、なおかつ、指で音価分を伸ばしている例です。
①の状態に、ペダルを踏むことによる響きが加わります。
したがって、ウエットなサウンドが得られます。
③は、
指では音を切ってしまい、ダンパーペダルで音を伸ばしている例です。
①や②に比べると、
空間性のあるサウンドが得られます。
こういった音色のニュアンスまで読み取るのが「譜読み」です。
楽曲によっては
「作曲家自身によるペダル指示」
が書かれていない場合もありますが、
その場合は、
ペダルを使うかどうかまで含めて
演奏者の演奏解釈の問題になるわけです。
求めている音色によって使い分ける必要があります。
つまり、
「譜読み」か「演奏解釈」のどちらかにとっては
絶対に必要になるのが
本記事の内容ということです。
音色は「音域」によっても異なってきますし、
「弱音」の場合なども含めれば
さらに多くの考慮が必要になるでしょう。
演奏で必要なのは、
「音の高さ」や「リズム」のみを読み取って満足するのではなく
「音色」という観点でも楽曲にアプローチをする姿勢です。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
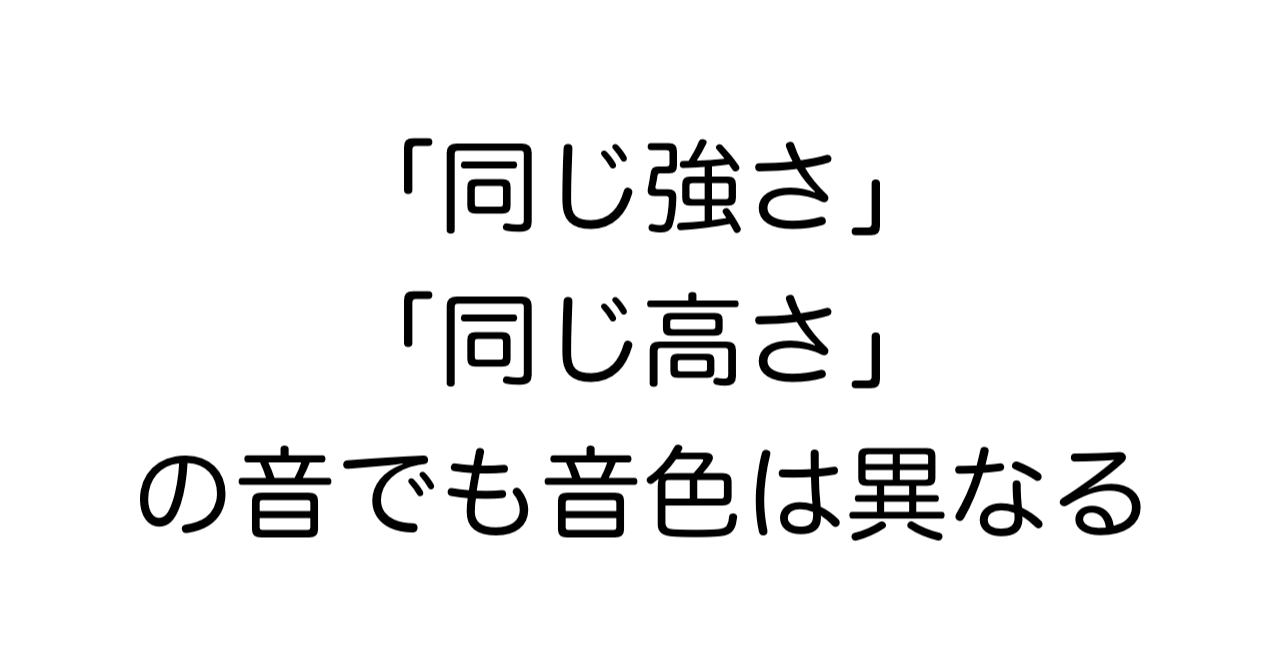
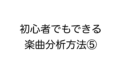
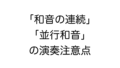
コメント