今回紹介する
取り組みやすい楽曲分析の方法とは、
「メロディの音程関係を調べる」
というもの。
今取り組んでいる楽曲をメロディに注目しながら
はじめから見ていきます。
そして、
以下のことを調べます。
◉ 順次進行が中心で動いているメロディなのか
◉ 跳躍進行が中心で動いているメロディなのか
◉ これらが適度に混ざって動いているメロディなのか
ひとつの楽曲の中でも
ずっと同じやり方ではなく
この4項目が使い分けられているはずです。
こういったことを把握できると、
「メロディが持つ意味を理解するヒント」
を得ることができます。
どういうことかと言いますと、
それは
のなかにヒントがあります。
部分的に引用して紹介させていただきます。
(以下、「音程について」の項目より引用)
♬ 順次進行はエネルギーが少なくてすみ、平静な、なだらかな感じを伴う
♬ 同じ順次進行でも、下降の場合は全くエネルギーを不要とする
♬ 跳躍上昇では、音程が広ければ広いほどエネルギーが必要で、興奮と緊張をもたらす
♬ 跳躍進行でも下降する場合、やはりエネルギーは少なくてすむ
(引用終わり)
もちろん、
「リズム」「強弱」「テンポ」などによっても
随分と印象は変わりますし
ここで引用した内容は絶対的なものではありません。
しかし、
音の進行によるエネルギーの観点としては
最も基本的なものとなります。
こういったことを読み取れると、
「緊張感などのコントロールを見てとることができる」
という利点があります。
作曲家が、
緊張感や表現したい内容を
一曲の中でどのようにコントロールしているのかを想像して
解釈に活かせる手がかりになる。
例えば、
跳躍進行ばかりのメロディを聴いた時に
「この楽曲は落ち着いている楽曲だな」
と感じる聴衆はほとんどいないでしょう。
こういったことを
感覚的な部分のみではなく、分析的にも理解しておく。
そうすると、
「ここの部分の rit. はどれくらいの加減でかけるのがいいか」
などといったことを
判断していくきっかけの一つにすることができます。
ここまでの判断は
初心者には難しいと思います。
しかし、
この分析に必要なのは、
「同音連打」「順次進行」「跳躍進行」
この3つの言葉の意味を知っておくことだけ。
その先は、
楽譜を見るだけで
「連打しているのか」「順次で動いているのか」「跳躍しているのか」
これらは一目瞭然ですから。
ここまではおそらく初心者でも取り組むことができるでしょう。
まずはひと段階だけでもチャレンジしてみましょう。
「メロディの音程関係を調べる」
これは、
立派な楽曲分析なのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
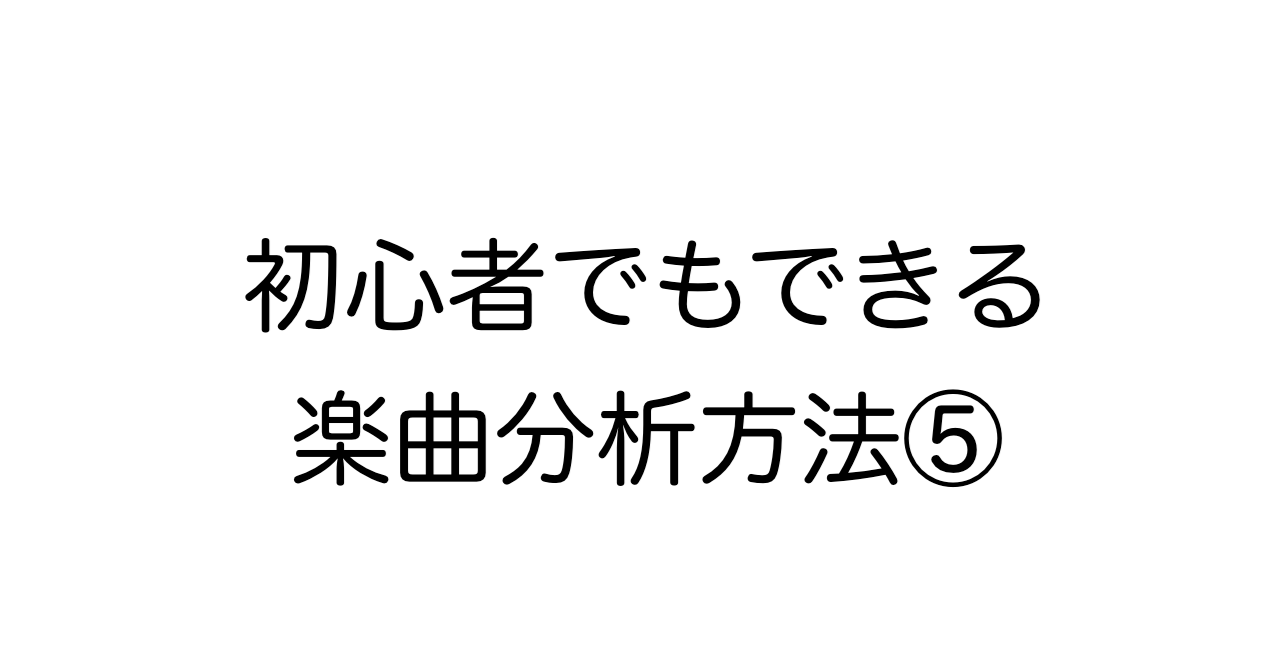
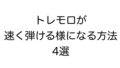
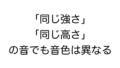
コメント