具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
ベートーヴェン「ピアノソナタ第22番 ヘ長調 作品54 第1楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成、29-30小節目)
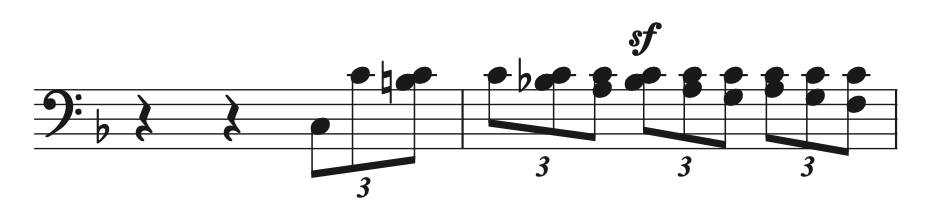
ここからの左手は
「同音連打される声部」と「順次進行で動く声部」に分かれます。
「2声的な和音」になっていますよね。
ではなぜ、2声に声部分けされていないのでしょうか。
答えはシンプル。
「見にくくなるから」
です。
明らかに2声がリズム的にも独立して動いている場合には
上向き、下向きで声部分けしたほうが見やすいのですが、
この譜例のように
片方の声部がステイしていてリズムも同じ場合などは
無闇に声部分けされていると
ただ煩雑になり見にくく感じてしまいます。
多くの楽譜というのは「利便性」も考慮されて書かれているのです。
(再掲)
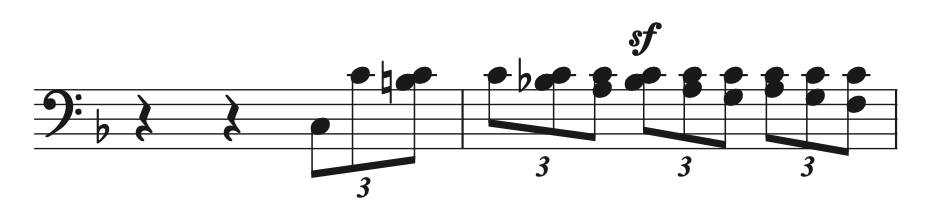
さて、話を戻しましょう。
こういった「片方の声部がステイしている2声的な和音」の演奏ポイントは、
「“同音連打される声部”をやや控えめに演奏し、”動く声部”の方が多めに聴こえるバランスを探る」
ということ。
こういった箇所で全てを同じバランスで演奏すると、
ただの「音のカタマリ」になってしまいます。
それでは「2声的」には聴こえてきません。
テクニック的には
「際立たせたい音を意識すると共に、手をわずかにその音の方向へ傾けて打鍵する」
このようにするとうまくいくでしょう。
【ピアノ】和音の中から特定の音だけを際立たせる方法
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
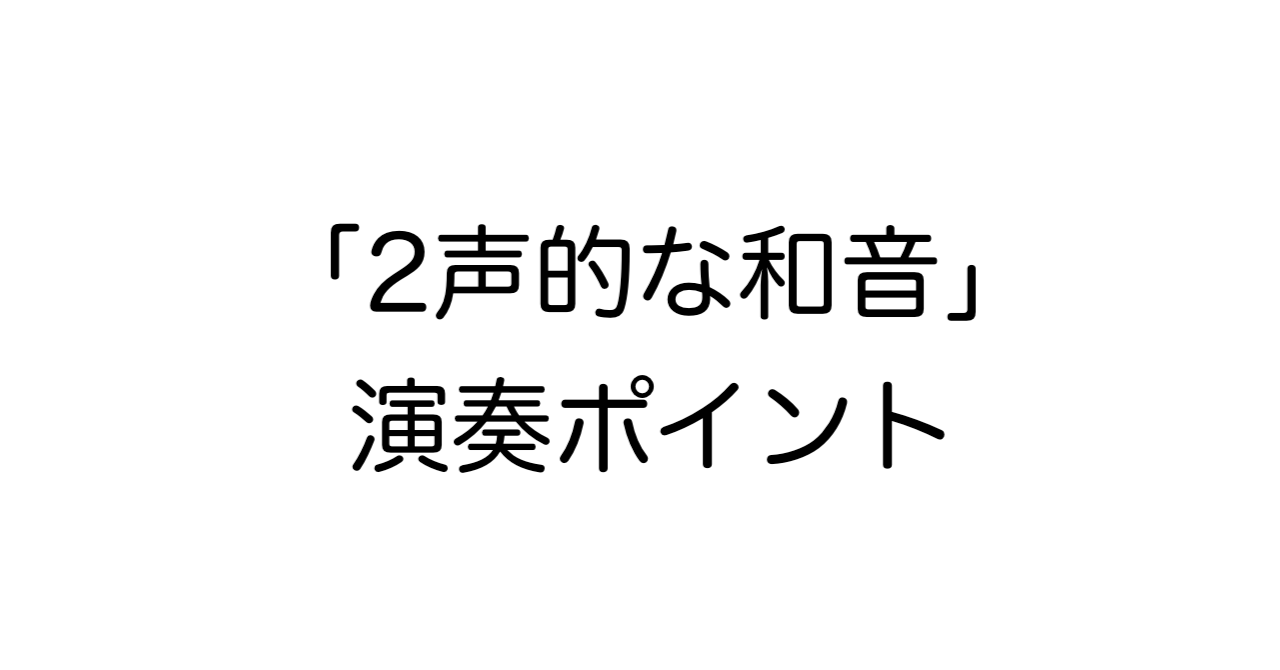
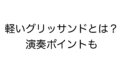
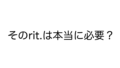
コメント