注: 「ソナタ形式がどういうものか」という、
「形式そのものの解説」は本記事では割愛します。
この形式の学習参考書籍は本記事の最後で紹介しています。
一番のヤマが展開部にあるとは限らない
ピアノ演奏において
「クライマックスの活かし方」には注意が必要です。
「一番のヤマ」がどこなのかに気をつけて演奏しないと、
ヤマがいくつもできてしまいます。
展開部というのは、
「提示部で出てきた重要な素材の展開」
を主としていますが、
必ずしも楽曲(楽章)の一番のヤマがくるとは限らないのです。
展開部よりも「再現部の(あとの)終結部分」に
音楽的、音量的な頂点がくる楽曲も多い。
そういったことを
細かく読み取っていかなくてはいけません。
関連して、
ダイナミクス面での演奏ポイントも
一つお伝えしておきましょう。
「 f(フォルテ)」を見たときにすぐにマックスにならないこと」
これが重要です。
「f よりも上のダイナミクス領域」
というのはまだまだあります。
sf などの各種アクセントがつくこともあれば、
ff 、fff 、・・・など
時代によってはさらにダイナミクスの指示に幅があります。
◉ f(フォルテ)」を見たときにすぐにマックスにならないこと
この2点を意識しておけば、
「もっとも盛り上げたいところが分からない演奏」
は回避することができます。
他の楽章の特徴を調べる
これは、
ベートーヴェンなどのピアノソナタで
「第1楽章がソナタ形式になっている作品に取り組んでいる場合」
でのことです。
そのようなケースでは、
必ず「他の楽章の特徴」を調べてみてください。
特に「ハイドン以降」のピアノソナタの場合、
形式、テンポ、調性、拍子、素材、・・・
など、
様々な点で楽章同士のバランスがとられています。
つまり、
他の楽章の特徴を調べることで、
ソナタ形式になっている(ケースが多い)
第1楽章の特徴も
より浮き彫りになってきます。
例えば、
「このソナタは第2楽章がレッジェーロで第3楽章がプレストだから、
第1楽章はテンポを速くしすぎない方がバランスがいいかな」
などと、全体のバランスを考えていくきっかけになります。
ソナタ形式による第1楽章は
そのソナタ全楽章の中で一番深い内容を持っているケースが多いので、
「全体のバランスにおける第1楽章の位置」
というものを考えることは欠かせません。
いきなり全楽章を練習するのはたいへんだと思います。
そこで、
まずは楽譜を見ながら音源を聴いてみたり、
「楽譜だけ」もしくは「音源だけ」で調べてみる、
といったところから
他の楽章の勉強を始めましょう。
「似ているけれど異なっているところ」を調べる
例えば、
ロンド形式では「Aのセクション」が何度も出できますが、
ソナタ形式でも
「セクションのわかりやすい繰り返し」があります。
それはもちろん、
「提示部に対する、再現部」
のことです。
再現部は「一種の繰り返し」ですが、
ほとんどの場合は
提示部に「変更」が加えられています。
そこで、
「どこが同じで、どこが似ているけど異なっているのか」
こういったことを譜読みの段階から
ていねいに整理しておくことがポイント。
そうすると、
譜読みをスムーズに進められるだけでなく、
後々「暗譜」をする際に非常に有効です。
いろいろな本番を聴いていると、
ソナタ形式の楽曲で
暗譜がとんでしまう方もいる。
こういったケースの場合、
それらのほとんどが
「再現部で提示部と同じことを弾いてしまって、それ以降が分からなくなってしまう」
という理由。
つまり、
暗譜で苦戦する箇所の定番は、
「似ているけど少し異なっている箇所」
と言えます。
「ソナタ形式」について基礎から学びたい方は
以下の電子書籍を参考にしてください。
◉ 大人のための独学用Kindleピアノ教室 【対話形式でまなぶ】誰でもわかるソナタ形式
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
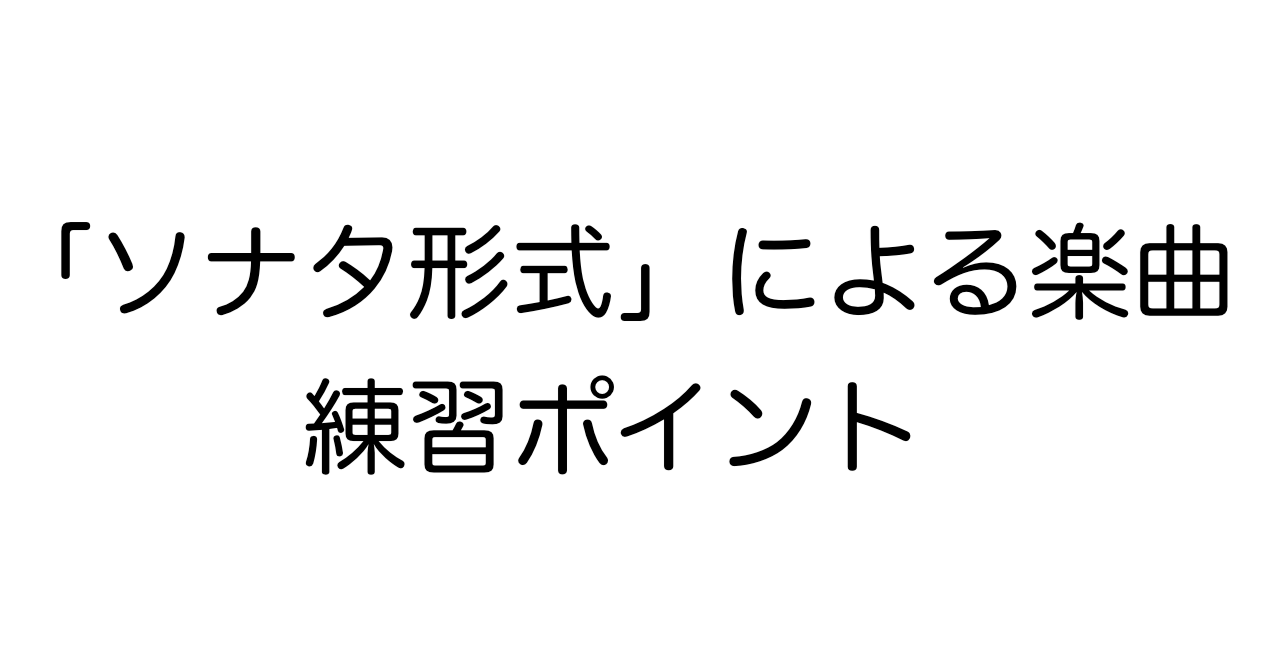

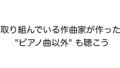
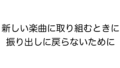
コメント