次の譜例を見てください。

①は、アクセント音の1つ前の音でスラーが切れている例。
②は、アクセント音までスラーがかかっている例。
これらはどちらも見かけますよね。
しかし、音楽表現は別物です。
1つ前の記事をお読みいただけると分かるように、
「スラーとマルカートは本来反する表現」であり、同居は難しい。
それは、②のようにスラーとアクセントが同居している場合でも同様です。
「スラーが書いてあるということはレガートである」
これが前提ですが、
「隣の音同士の音色が揃っていないとレガートには聴こえない。
逆に、音量差があっても音色が揃っていればレガートに聴こえる」
という事実も踏まえておかなければいけません。
(再掲)

その観点で言うと、
②のようにスラーがかかっている中にアクセントがあるというのは
音楽表現上、不自然。
アクセントがついている音は
必ず直前の音と音色が変わるからです。
だからこそ「アクセント」という表現が存在します。
筆者の知る限り、
ほんとうに力のある作曲家は②のようには書きません。
しかし、すでにできている楽曲を演奏するわけですから、
どうにかして演奏しなくてはいけませんよね。
そこで、筆者は次のように考えます。
(再掲)

①のように、
アクセント音の1つ前の音でスラーが切れている場合は、
アクセントの直前(矢印を書き込んだ位置)で
「一瞬の音響の切れ目」を作る。
このようにすることで、
アクセントの音が「別」になるため、強調されます。
(この方法は、あまりにテンポが速いケースでは不可能です。)
②のように、
アクセント音までスラーがかかっている場合は、
カッコ付きで示したように
少しのクレッシェンドを補なうといいでしょう。
そうすることで、先ほど示した問題もクリアされます。
(この方法は、テンポが速くても可能です。)
ポイントは、
アクセントがついた音の強度を到達点とするように、
自然なクレッシェンドをつけること。
そうでないと、音楽がまったく変わってしまいます。
アーティキュレーションからは、
どういう音楽(表現)なのかを読み取ることが重要。
「長さ」というよりは「音楽」を示すもの。
今回の例のように、
レガート表現とアクセント表現が同時に出てくるケースでは
特に注意が必要です。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
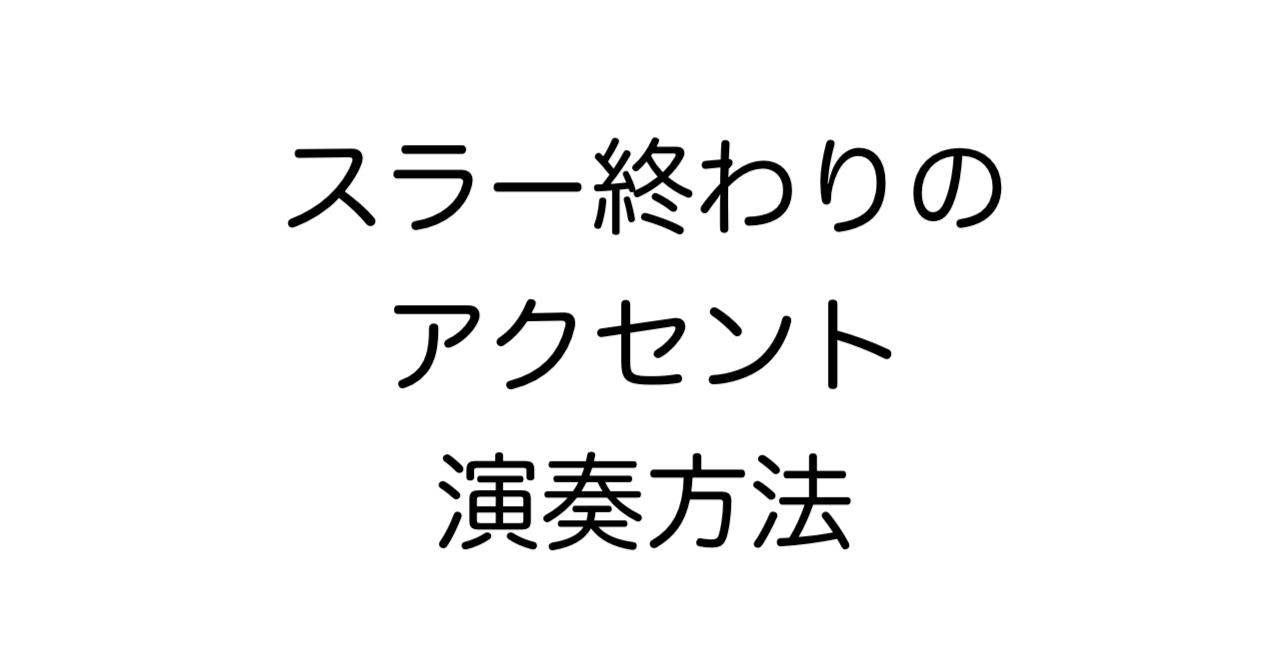
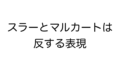
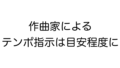
コメント