(譜例)

この譜例は私が作成したものですが、
実際のピアノ曲を見てくると
このような「スラーとmarcatoが同居している記譜」が度々見られます。
素直に頭を働かせれば、
「レガートではっきり弾くのだろうな」
と分かるわけですが、
それって音楽表現からするとちょっと妙なのです。
作曲家の言いたいことは分かります。
しかし、
「スラーとマルカートはほんらい反する表現であり、同居は難しい」
ということは
それぞれの音楽用語を細かく調べてみると
すぐに理解できます。
また、それは管楽器の演奏法からも理解できます。
例えば、
フルートなどの管楽器は
スラーが書かれている場合、
「タンギングをせずに一息で演奏すること」
を意味する。
つまり、marcatoで演奏したくても
「ウウウウウ」というニュアンスに。
タンギングをしないので当然ですよね。
一方、
スラーが書かれていない場合は、
「タンギングをして演奏すること」
を意味する。
つまり、marcatoであろうとなかろうと
「タタタタタ」というニュアンスに。
テヌートで演奏すると「ターターターターター」
となります。
これらのことからも、
「スラーとマルカートはほんらい反する表現であり、同居は難しい」
ということが分かっていただけると思います。
管楽器とピアノでは
楽器としての発音方法が違うことは確かですが、
記譜の解釈の基礎は変わりません。
(再掲)

譜例のような表現が出てきたときは、
marcatoは書かれていないものと思い、その代わりダイナミクスを1段階あげる
スラーは書かれていないものと思い、その代わり、一つ一つの音をテヌートでmarcato演奏する
この2種を、
楽曲により判断して使い分けていきます。
作曲家の意図を無視しているわけではありません。
スラーとマルカートを同居させている書き方自体、
ほんとうに力のある作曲家は使用しないもの。
そこで、
演奏にとっていちばん効果的で、かつ、
作曲家の意見が残るような演奏法に
翻訳する必要があるのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
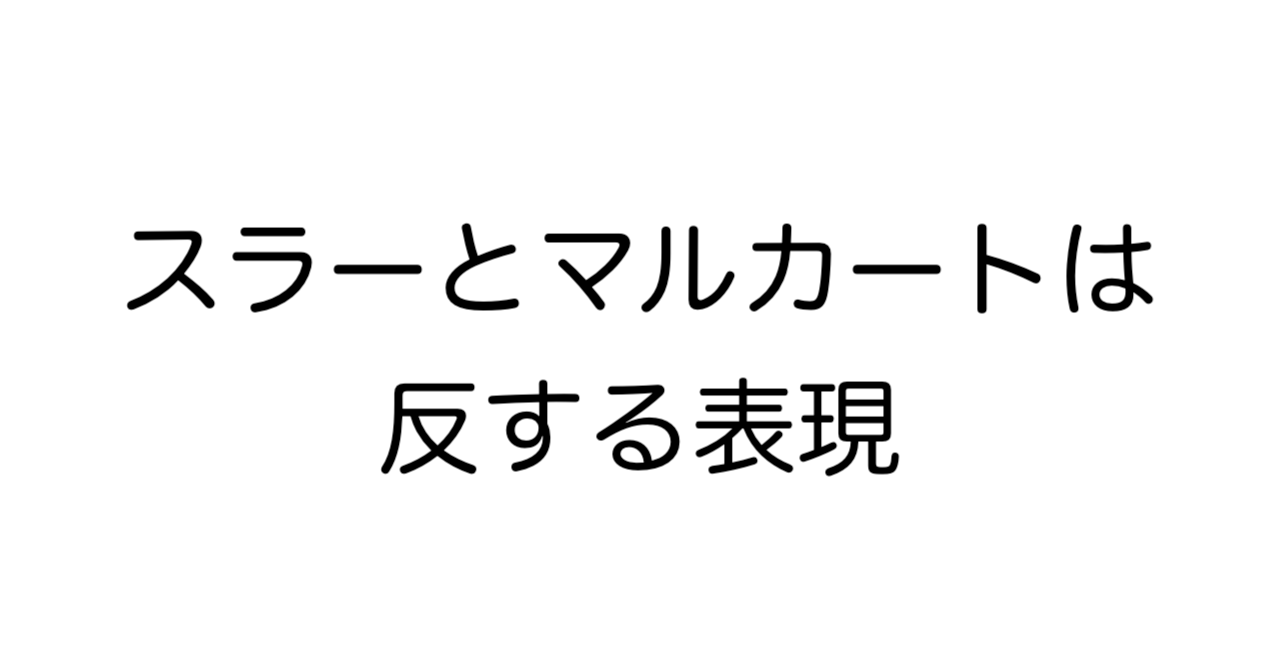
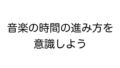
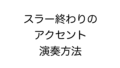
コメント