音楽大学には科目として「初見法」のクラスが設けられています。
「単旋律」で実施するクラスや
作曲科やピアノ科の学生を対象にした
「大譜表」で実施するクラスも。
興味がある方もいらっしゃると思いますので、
どんなことをやっているのかなどを
少しだけ紹介します。
「初見法」というだけあって
「ピアノの初見演奏」以外にも
様々な面から「初見」についてアプローチします。
例えば、ある日のクラスでは
「フランスの読譜用の教材(Manuel pratique pour l’études des clés など)」
を使用して、
リズムは関係なく羅列された音符を
滑らかに声に出して音読していきます。
もちろん、
ハ音記号が出てきたりと
オーケストラで使用される様々な楽器の初見読譜に対応できるような訓練をしていきます。
ソルフェージュの授業と共通点が多い内容でもあります。
◉ Manuel pratique pour l’études des clés
また、実際にピアノで音を出しながら初見演奏をする日もあります。
大勢の学生とクラス担当教員の前で
与えられた課題を元に初見演奏をし、
それに対して教員と生徒数名が感じたことを発言するという、
一種の公開オーディションのような緊張感あふれる内容。
音楽大学の初見法の授業では
かなり細かなことまでを学習目標としているので、
「音が間違っていなくても、アーティキュレーションをひとついい加減に扱っただけでチェックが入る」
という厳しさもあります。
学生同士による「連弾での初見」もクラスに組み込まれたりと、
バラエティに富んだ練習課題となっています。
学期末には
初見演奏の実技試験が
専攻別の演奏実技試験とは「別」に用意されていて、
数人の審査員の前で
そのときに出された数分の課題を初見で演奏します。
筆者の卒業した大学では
初見法のクラスはいくつか用意されていて、
「必ずひとつのクラスは単位をとらないといけない」
という決まりになっていました。
初見法のクラスは緊張感もありますし、
「学期末の実技系の試験がひとつ追加になる」
ということからも
割と避けたいと思っている学生が多い。
そのために、
「決まり通り1つのクラスをとり終えたら、他の初見法のクラスはとらない」
という学生も多かったのです。
本ブログの読者さんの初見練習は
誰かに審査されるわけではないですから、
ぜひ前向きに
初見演奏の練習へ取り組んでいただきたいと思います。
初見の練習をすると、多くの恩恵が受けられます。
◉ 初見能力が上がると「演奏能力」も上がる
◉ 初見能力が上がると「譜読みの速さ」にも直結する
楽器をやったことのない方が他人の演奏を聴いたときは
「初見能力 = その人のピアノの実力」
だと思ってしまう傾向がある。
実際にそういった一面は否めなくもないのですが、
非常にもったいないと言えますね。
こういった意味でも、
「初見能力が上がることによるメリット」はあるはずです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
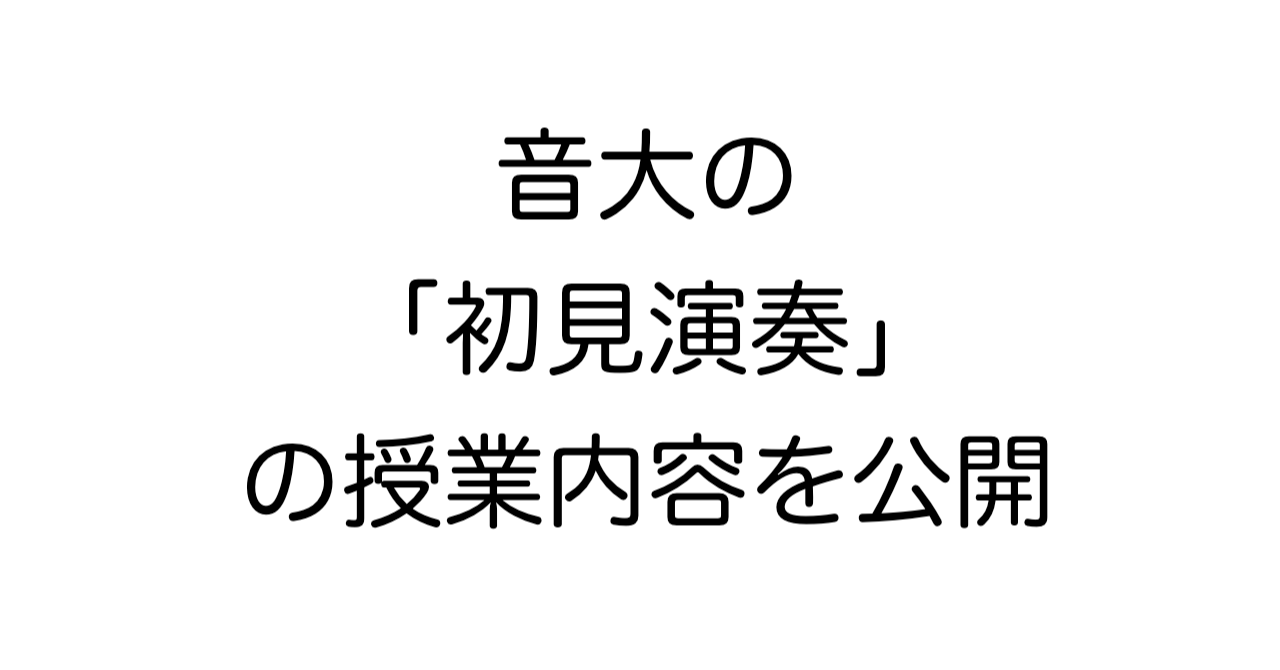
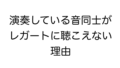

コメント