筆者が子供のときに
ピアノコンクールで審査員から受けた講評のうち、
印象に残っているものがあります。
その時の講評を下さったのは
ピアニスト2名及び、作曲家1名の計3名でした。
ピアニストの審査員方は
「テクニック寄りの講評」だったのですが、
作曲家の審査員は
「ブラームスらしいフォルテというものを考えたことはありますか?」
と講評を出されたのです。
今思えば、
作曲家の先生らしい素晴らしい観点だと感じます。
もちろん、
「ブラームスらしいフォルテ」に正解はありません。
10人いれば10通りの考え方があるはずです。
一方、少なくとも、
プロコフィエフの「サルカズム」を弾く時のような音色ではないのは
言うまでもありません。
「作曲家」によって、
また、
同じ作曲家でも「その作品のタイプ」によって、
フォルテを含め各種ダイナミクス記号のニュアンスを
考えていく習慣をつけましょう。
出したい音色が決まれば、
「では、どのように身体を使って音を出せばいいか」
といったように
後付けで必要なテクニックもみえてきます。
✔︎ あわせて読みたい
【ピアノ】ハイドン、モーツァルトにおけるダイナミクスの解釈方法
【ピアノ】ハイドン、モーツァルトにおけるダイナミクスの解釈方法
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
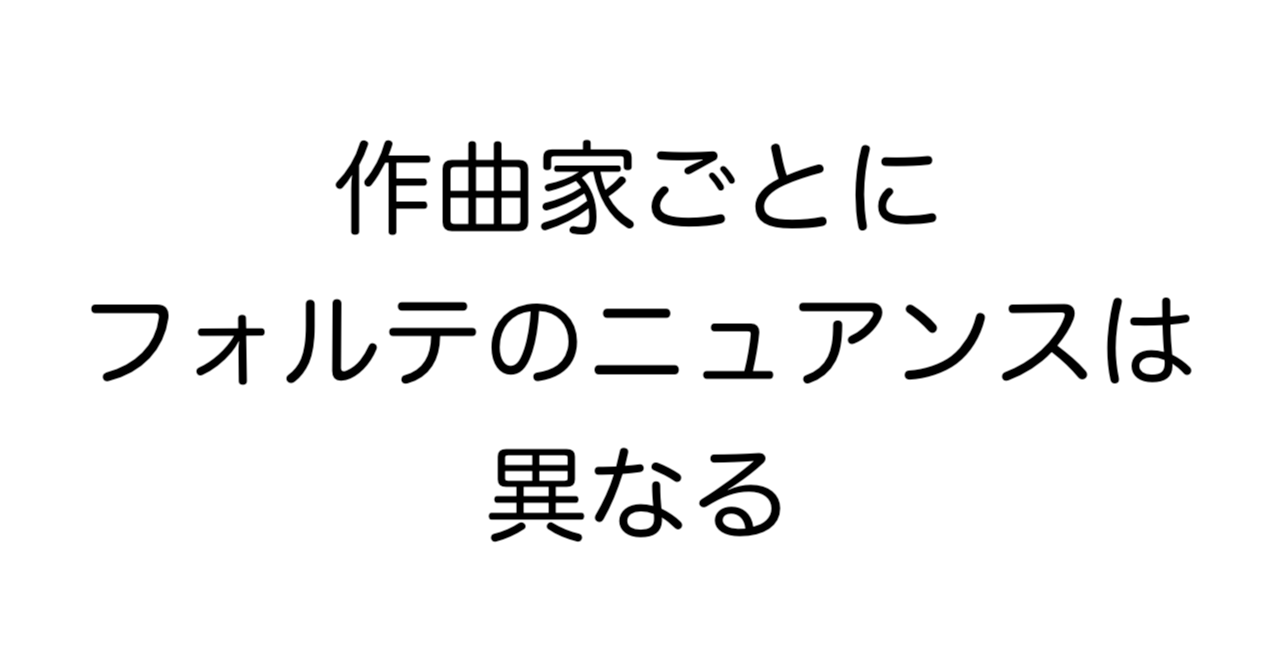
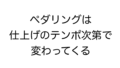
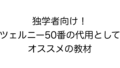
コメント