【ピアノ】「楽典―理論と実習」に入門して読了するまでのロードマップ
► はじめに
楽典を学ぶためのテキストとして、多くの音楽家に支持されている定番の入門書があります。
「楽典―理論と実習 著:石桁真礼生 他 / 音楽之友社」
この書籍は、独学でも理解しやすいように書かれており、ピアノ学習に必要な基本的な内容がバランスよく収められているのが特徴です。
本記事では、これから楽典の学習を始める方のために、効率的な学習方法と、つまずきやすいポイントについて解説していきます。
・楽典―理論と実習 著 : 石桁真礼生 他 / 音楽之友社
► 現時点で知識ゼロでも問題ない理由
「でも、今は何も知識がないけど…」
こういった心配は必要ありません。なぜなら、「楽典―理論と実習」はゼロから段階を踏んで学べるように構成されているからです。音楽理論の予備知識がなくても、順を追って理解できるようになっています。
ピアノ演奏に必要な基本的内容はすべて入っているので、他の楽典書籍に浮気する必要はありません。
筆者自身、楽典に関しては完全な独学でした。楽典の学習に、年齢制限や向き不向きは関係ありません。
► 入門して読了するまでのロードマップ
‣ 効果的な学習のための3つのポイント
· 気づきは、すべてテキストへ書き込む
効果的な学習のための一つ目のポイントは、学習中に気づいたことや必要だと思った内容は、消せるペンでテキストへ書き込んでいくこと。
例えば「音名」の項目で「Ces」と書かれていますが、読み方を調べ終わったら「ツェス」などと小さく書き込んでおくのです。ガンガン書き込んでテキストをノート代わりにして下さい。
どうしてこんな初歩的な話をするのかというと、楽典の内容というのは、音楽を続けている限り、どんなに学習が進んでからも参照する機会は出てきますが、そんな時に、いつでもこの書籍から情報を取ってくることで、情報の出典元を統一した整合性を保った学習ができるからです。
1年後、3年後、さらにその先まで、必要なときにすぐに情報が取り出せる自分だけの教科書として育てておくことには、大きな利点があります。
·「8割理解できればいいや」くらいの気持ちで進めていく
特にテキスト1周目は「完全に理解しないと先に進めない」というストイックさは捨ててしまいましょう。
楽典の学習では、前後の学習内容が結びついている箇所はありますが、概ね8割程度理解しながら進めば、残り2割の不理解が次の項目に支障を与えることはありません。むしろ、完璧な理解を求めすぎるとモチベーションが下がってしまう可能性があります。
理解できていない2割の部分は、実際の楽曲の中で、あるいは2周目の学習で自然と埋まっていきます。
· 譜例は、できる限り音で確認する
テキストに出てくる譜例は、できる限り実際に音を出して確認しましょう。これをやらないと、単に机上で理解した勉強になってしまいます。特に「第6章 和音」のあたりは、何度も響きを確認してみるべきです。
「楽典だけではなく、ピアノも初心者で…」という方もいるかもしれませんが、ゆっくりと探りながら、全音符の和音を押さえることはできるはずです。
「楽譜が読めなくて…」という悩みも不要。それは楽典の一番最初から学ぶ項目なので、「第6章 和音」にたどり着く頃には、簡単な譜面は読めるようになっています。
‣ 楽典初心者が最初は飛ばしてもいい項目
「楽典―理論と実習」では、段階を踏んで学べるようになっています。
むしろ、ピアノ演奏に活かすということだけで考えるのであれば、一旦省略してもいい項目すらあります。以下の項目は最初の学習では飛ばしても問題ありません。
· 序章-Ⅱ-1 「純正律」
ピアノは「平均律」で調律されているので、最初は純正律の知識は必要ありません。純正律は奥深い世界なので、余裕が出てきたら後に学んでください。
· 第1章-Ⅲ-2-b 「総譜」
ピアノで3段以上の楽譜を使うことはほとんどありません。アンサンブル作品や、ソロでも近現代作品などで目にする程度です。
· 第5章-Ⅰ-5 「移調」
ピアノは移調楽器ではないので、後回しにしても構いません。※ただし、「転調」の項目は必ず学習してください。
· 第5章-Ⅰ-6 「調の判定」
これは主に音楽大学受験のための知識です。
旋律を見て調性が分かるというのはソルフェージュの力として重要ではありますが、実践的な演奏にはもっと音楽的なアプローチがあります。
· 第5章-Ⅱ 「その他の音階」
興味深い内容ですが、基礎を固めてから取り組む方が効果的です。
► 終わりに
楽典の学習は、決してゴールではありません。むしろ、音楽をより深く楽しむための入り口です。「楽典―理論と実習」を一冊マスターすれば、楽譜を見る目が変わり、音楽に対する理解が格段に深まります。
本記事で紹介した3つのポイントを意識しながら、学習を始めてみてください。
・楽典―理論と実習 著 : 石桁真礼生 他 / 音楽之友社
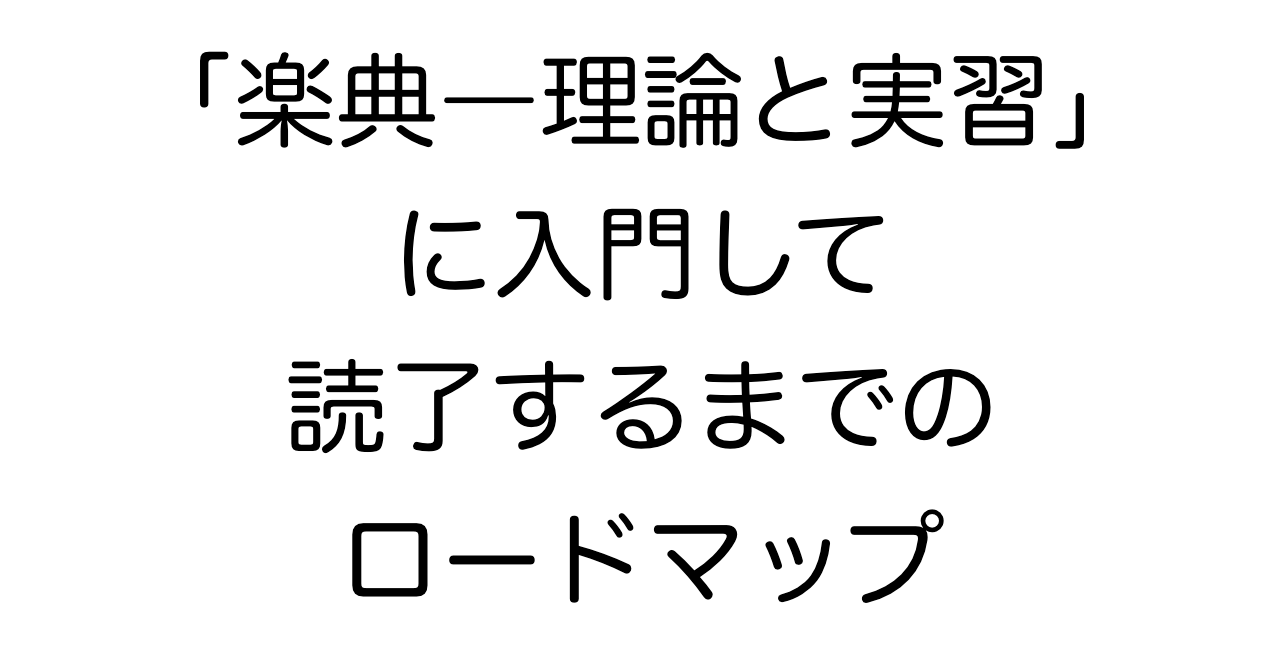

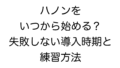
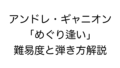
コメント