ピアノ作品は
あらゆる楽器のソロ作品の中でも
その数は非常に多いですよね。
さまざまなタイプの作品がありますが、
大きな傾向としては
「近現代へ近づくにつれて、ピアノを打楽器的に扱った作品が増えてくる」
というものがあります。
例えば、
◉ アイヴズ「ピアノソナタ 第2番」
◉ プロコフィエフ「風刺(サルカズム)」
などの作品は
音の使い方からして
明らかに打楽器的な作品。
他にもたくさんあります。
芸術音楽の作曲家は
常に新しいことを開拓しようとしていますので
時代を追うごとに楽器の使い方も模索され
19世紀後半、打楽器的な扱いへとたどり着きました。
ピアノは1700年頃に生まれたわけですが、
なぜ、ピアノが誕生した直後の時代に
この種の作品が存在しないのでしょうか。
答えは簡単で、
ピアノが誕生するより前の時代にも
この種の作品が存在しなかったからです。
そんな使い方をしたら
クラヴィコードやチェンバロは壊れてしまいますし、
音楽史で当時のモラルをみていても
鋭く突いたり叩いたりする奏法が好まれなかったのは明らかです。
あらゆる作曲家というのは
永い年月をかけて
その新しい楽器のためのさまざまな楽曲を生んでいきます。
佳作、失敗作などあらゆるものが生まれて
何百年にも渡ってようやく
その楽器独自の楽曲が世に増え始めます。
したがって、
楽器誕生時は
そのときすでにあるような作品が
演奏されたり作られたりするしかないのです。
つまりピアノの場合は、
「チェンバロなどで演奏されていた音楽」から始まり
ピアノ独自の奏法を含む作品まで
たどり着く過程の中で
打楽器的な扱いが入ってきたということです。
ざっくりと大きな流れがつかめましたか。
こういったことを把握しておくと
レパートリーを増やしたり
コンサートプログラムを組むときなどにも
参考材料にできます。
各作品の特徴をとらえつつ、
さまざまなタイプの楽曲に挑戦してみましょう。
【ピアノ】聴いておくべきピアノ曲一覧
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
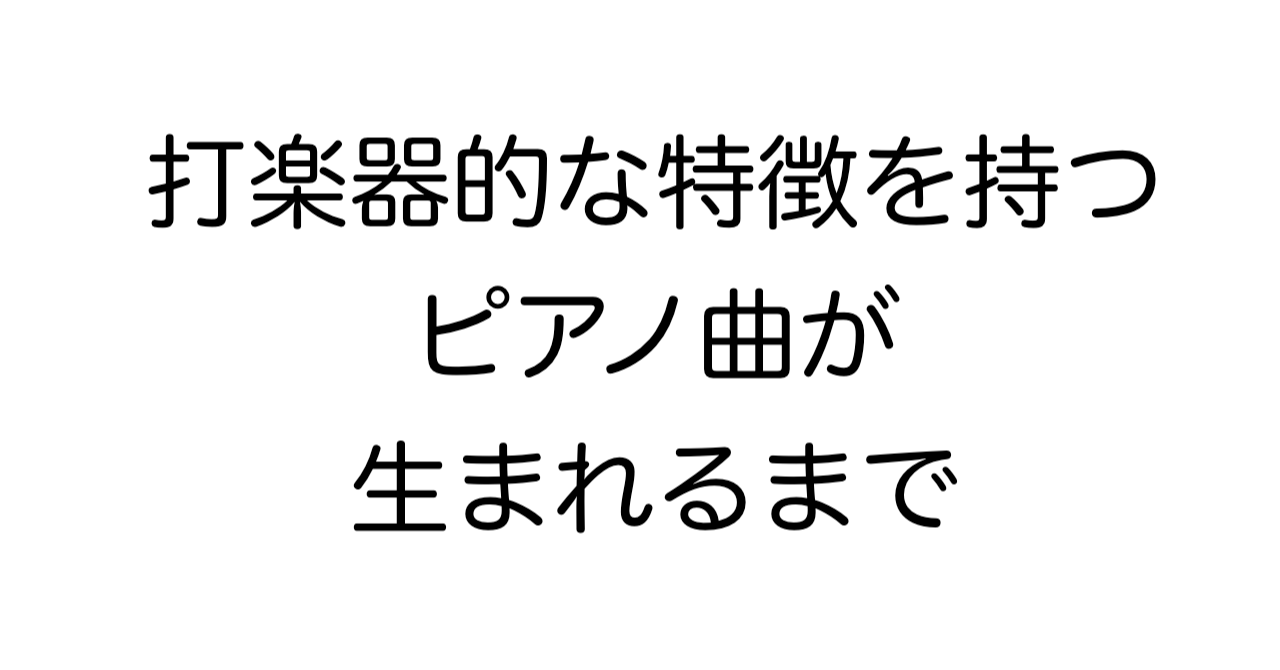
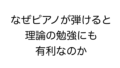

コメント