よく次のようなことを訊かれます。
「ここは何調に転調していますか?」
気になるのは当然のことですし、
知っておいて損はありません。
ただ、多くの方がここで終わってしまうのです。
一般的に言われている「楽曲分析」というのはなぜか、
和声記号をつけたり転調を知ったりすることばかりに比重が置かれていて
時々モヤモヤします。
それを知ってからが大事なのです。
「○○mollに転調した」
などと事実を知るだけでは意味がありません。
その転調によって
◉ 音色がどう変わったのか
◉ レジスター(音域)がどう変わったのか
◉ 音の濃淡がどう変わったのか
◉ レジスター(音域)がどう変わったのか
◉ 音の濃淡がどう変わったのか
などといったことを調べましょう。
そうすることで初めて演奏に活かせます。
初級者〜初中級者の方は
まずは「音域」のことだけでOKです。
いいですか、
「和声記号」や「転調の結果」というのは
記号でシンボル化されているので
それを楽譜に書き込むことで分析した気にはなります。
しかし、
それをどうやって演奏に活かしていくのか
もう一度考え直す必要があります。
そして、
「楽曲分析には他にも大事な要素はたくさんある」
ということを
今一度再認識してください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!
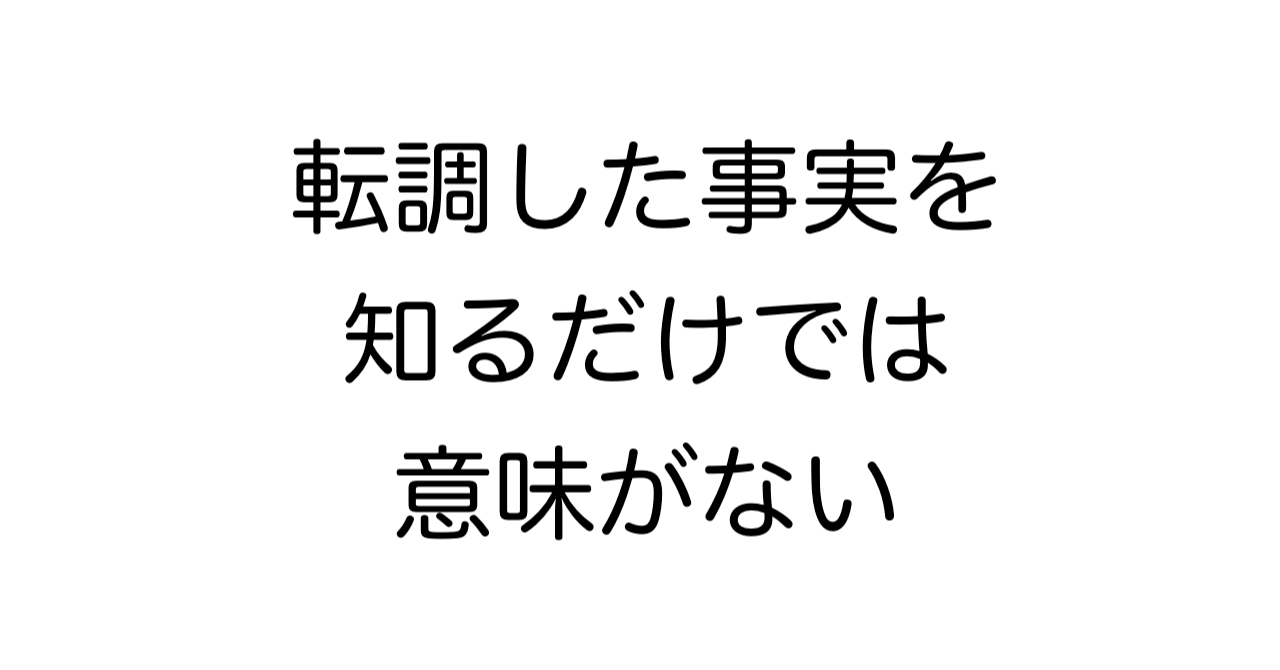
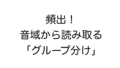
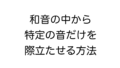
コメント