具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 妖精はよい踊り子」
譜例(PD作品、Finaleで作成、101-108小節目)

カギマークで括った2箇所(105、107小節目)に注目してください。
101小節目からずっと似たような音型が続きますが、
カギマークで括った2箇所でいきなり、
「は?何今の?」
みたいな意外性のあるサウンドが挟み込まれるのです。
サプライズですね。
それに
1度目に出てくる105小節目では直前に4小節ありますが、
2度目に出てくる107小節では直前に1小節しかなく、
「1度目にこう来たから、次はこうくるだろう」
という我々の予想を裏切ってきます。
(再掲)

この意外性のある2箇所は
クレッシェンドが書かれていることで
その効果を高めています。
さらには、
直後にsubitoで pp へ戻すことで
何事もなかったように素知らぬ顔をして先へ進んでいくからこそ
意外性のある2箇所の効果が際立ちます。
こういったサプライズの演奏ポイントとしては、
「これからきますよ〜、いきますよ〜」
などといった様子を
「視覚的」「演奏法的」
に感じさせずにサラッと通り過ぎること。
これが効果的な演出につながります。
聴衆に予感させずに出てくるからこそ
意外性となり得るのです。
これは、すでに聴衆が楽曲を知っているかどうかは関係ありません。
演奏自体で新鮮味を感じさせることはできるからです。
今回取り上げたような
「意外性のある挟み込み」
はあらゆる時代の作品に登場します。
きちんと見抜くことで
演奏時の注意点につなげていきましょう。
どんな時でも注意点は同様で、
「聴衆に予感させずに出すこと」
これに限ります。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
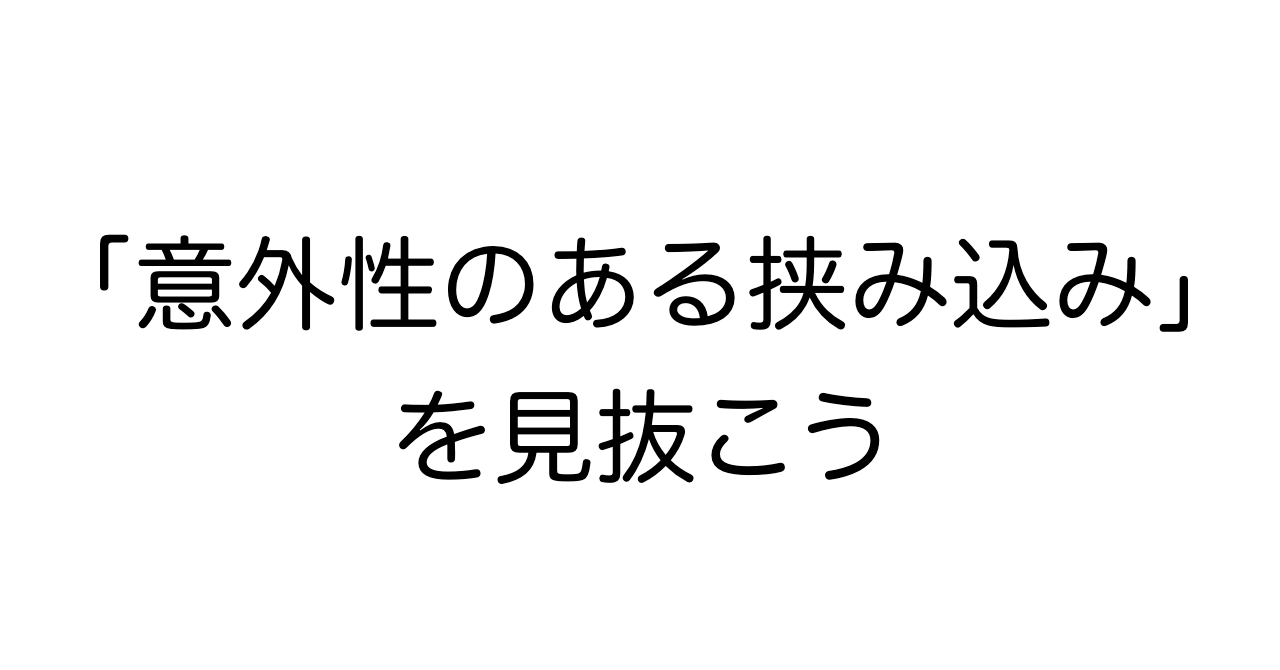
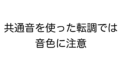
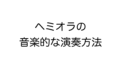
コメント