メロディラインと思われる音型が細かく動いている場合、
それらの音のカタマリの中から
◉ 響きに隠したい音
これらを的確に弾き分けていかなくてはいけません。
例えば、次のような例。
ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 熱情 ヘ短調 op.57 第2楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成、42小節目)
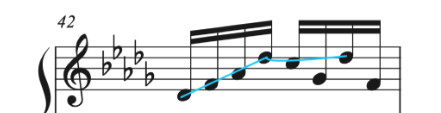
右手を見ると青いマーカーで示した音以外にも
Ges音やF音が出てきていますよね。
つまり、ここは「右手だけでも2声的」なのです。
したがって、
Ges音やF音が大きくなってしまうと
立体的な演奏になりません。
楽曲によっては
作曲家自身が声部分けをしてくれている作品も多くありますので、
そういった作品に触れていくことで
重要な音を見分けられるようになっていきます。
声部分けをしてくれている作品例としては、
◉ ブルグミュラー25の練習曲より 第7番「清らかな小川」
など、他多数。
右手部分を見直してみてください。
本記事の内容に関連する文章が
書籍「斎藤秀雄 講義録(白水社)」
の中に書かれています。
ヒントになる部分を
少しだけ抜粋させていただき紹介します。
バッハの場合はヴァイオリン・ソナタを見ると非常によく分かるんだけれど、
ヴァイオリン・ソナタというのはソロ・ソナタといって独奏ソナタだけれども、
あの中には伴奏の部分がいっぱい入っているんです。
ハーモニーを分からせる部分が、そのために書いてある音が。
それをどれもこれも1本の線にして全部メロディーだと考えるのは
間違いじゃないかという考えが出てくるわけです。
(抜粋終わり)
この内容は「バロック時代のソロ作品」で顕著ですが、
他の時代の様々なタイプの作品を理解する際にも
非常に有益な考え方となっています。
さらなるヒントは、
以下の記事を参考にしてください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
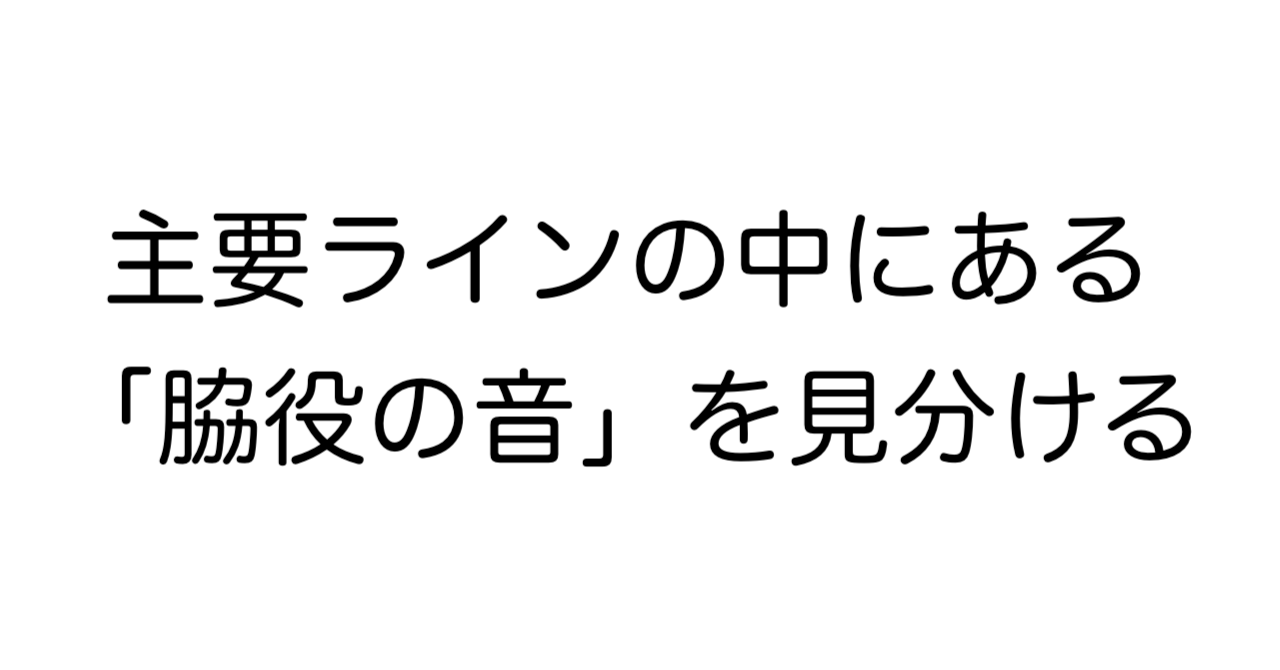

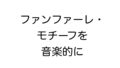
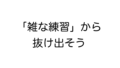
コメント