なぜ、J.S.バッハの付点は3連符に合わせるのでしょうか。
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)
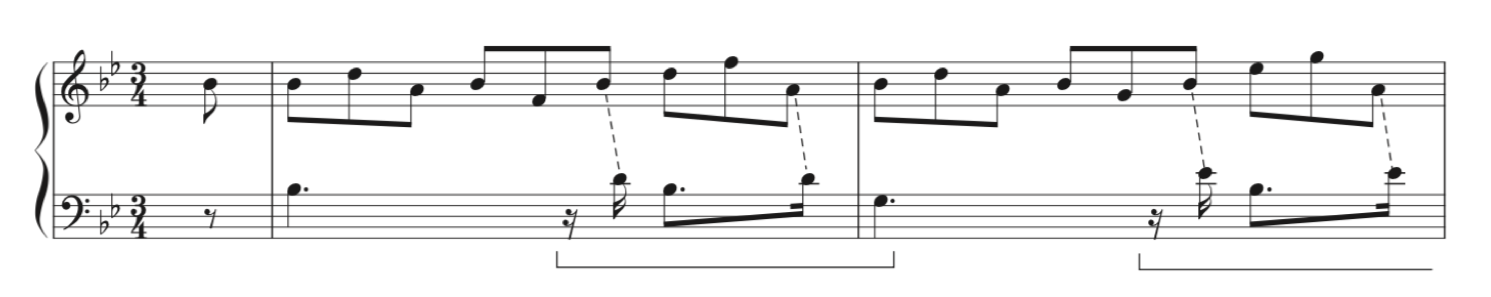
点線で示した箇所を見てください。
左手は16分音符で書かれていますが、
これはJ.S.バッハ(およびその時代)の特徴的な記譜法で、
実際は右手の3連符の3つ目の音と合わせて打鍵します。
16分音符のリズムに右手を合わせるのではなく、
3連符のリズムに左手を合わせます。
つまりこのケースでは
「付点リズムが前寄りに詰まる」
ということ。
ではなぜ、
こういった慣例が存在するのでしょうか。
ポイントは
「当時、どういった記譜が存在して、反対に、どういった記譜が存在しなかったのか」
これを知ることにあります。
(譜例)
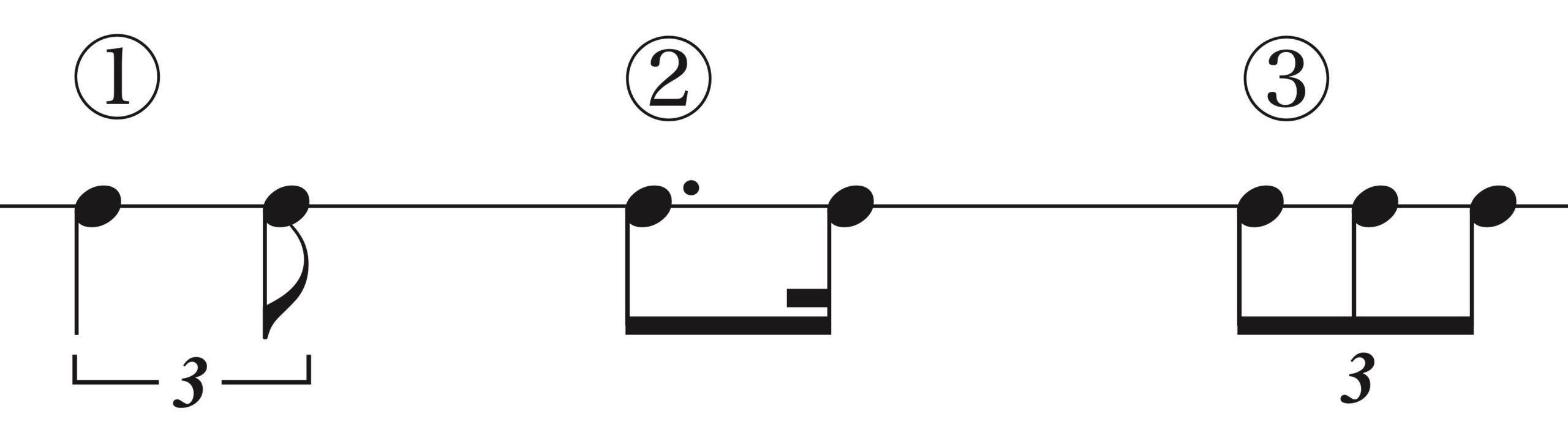
J.S.バッハの他の作品を調べてみると分かりますが、
当時、①の記譜はありませんでした。
そこで①の代わりに②のように書きました。
ところが③の記譜はあったんです。
このような理由で、
そのまま付点で演奏し、
②が③とセットで出てきたときは
①=②と解釈して③のリズムに合わせる
という慣例がでてきたというわけです。
上記のクーラントの例で解説した演奏方法を
見返してみてください。
この時代からベートーヴェン辺りまでは特に
ダイナミクスの書かれ方や
本記事で扱った慣例などをはじめとして
独特な記譜の特徴がたくさんあります。
ロマン派の作品を演奏する解釈では
楽曲を充分に把握することはできません。
できる限り、
当時の慣例なども合わせて学習していきましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
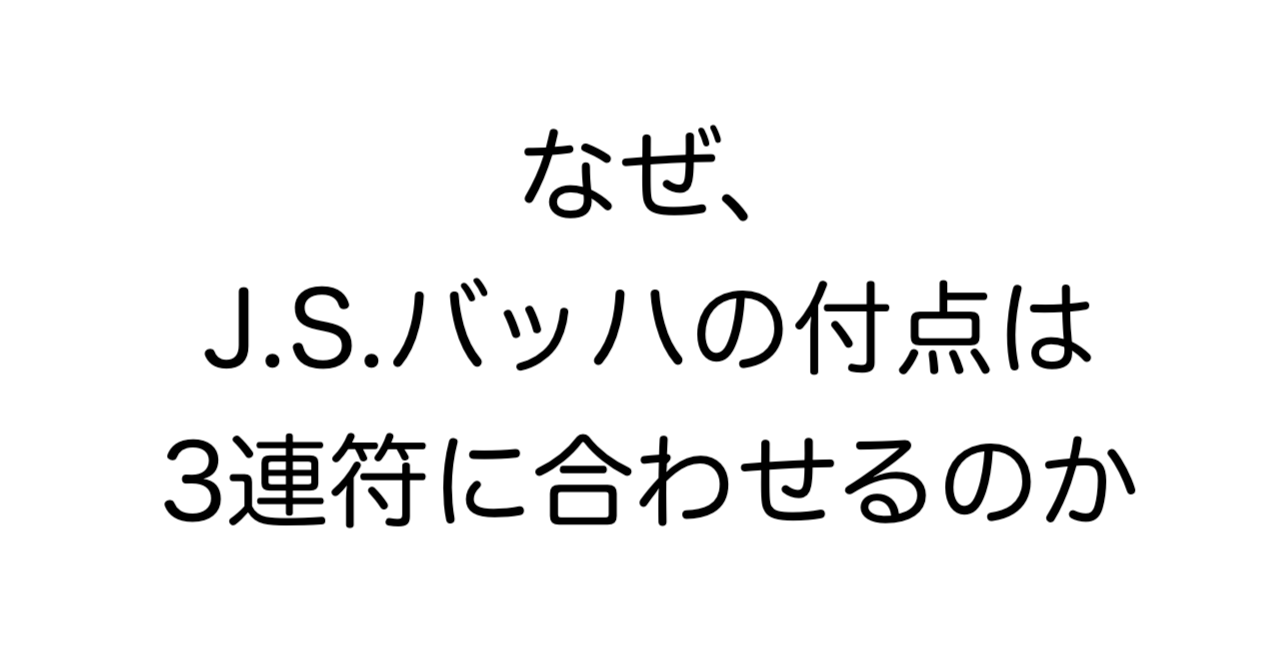
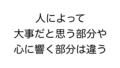
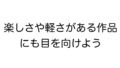
コメント