具体例を挙げます。
楽曲が変わっても考え方は応用できます。
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11-12小節)

11小節1拍目の左手部分で
○印をつけた音を見てください。
こういった親指で演奏する音で
大きく飛び出てしまっているケースが多いのです。
10度音程をアルペッジョで演奏するとなると、
結構忙しく打鍵する必要があります。
そういったこともあり、
うっかり親指の音が大きくなってしまうのです。
少なくとも
この譜例のケースでしたら
親指の音は触れるだけで大丈夫です。
それでも充分に響きます。
(再掲)

もちろん、
こういった10度音程のアルペッジョが
右手で演奏するメロディ部分にきていたり、
左手の場合でも
トップノートが
メロディ音になっている場合は
その音を多めに出して問題ありません。
あくまで、
今回の譜例のように
「伴奏の一部になっている場合」の注意点。
「音が大きく飛び出てしまっている」
というのは
音自体を間違えているわけではないので、
注意深く自分の演奏する音を聴かない限り
気づきにくいものなのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!
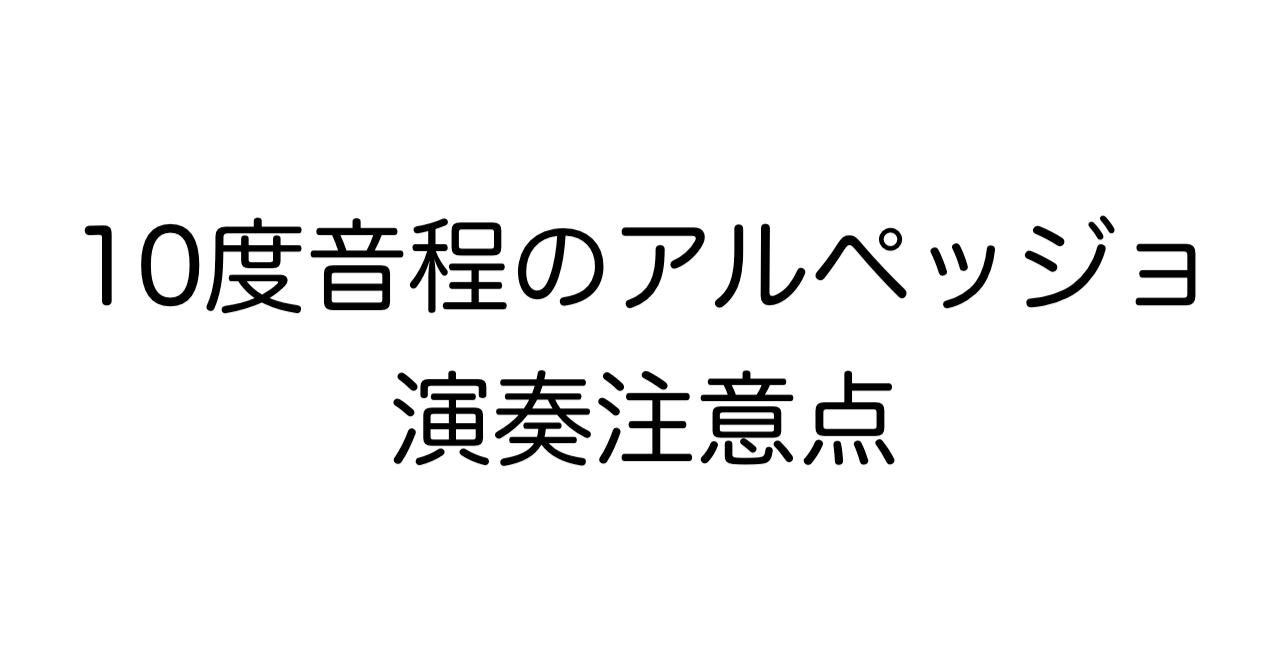
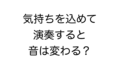
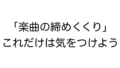
コメント