「4/4拍子が、中間部から3/4拍子になった」
などといった例は
音楽の意図もわかりやすいですよね。
では、譜例のような場合はどうでしょうか。

「普段は基本的な拍子(譜例では4/4拍子)にいるけれど、時々1拍増えてまた戻る」
などといった例。
特に近現代の作品では頻出する書法です。
このような場合は、
「1拍増えた小節では、音楽が広がった雰囲気(多少のテンポ変化)を出して欲しかったのかな?」
などと想像してみましょう。
5/4拍子の箇所というのは
4/4拍子の箇所に比べると音楽的には「曖昧」です。
それは聴いていても明らかですよね。
あえてその特徴を利用して
ルバートなどの表現を求められている可能性は充分にあります。
「4/4拍子のままルバートをする」
というのとは
出てくる音楽が異なることに注目してください。
こういった拍子変化を見たときに、
「はい、4拍子ね」
「はい、5拍子ね」
などと単純に処理して
音だけを拾ってしまってはいけません。
拍子変化の意図は作曲家しか知り得ないので
存命の作曲家の作品でない限り、答えはわかりません。
しかし、
それを考えて自分なりの解釈を持たないと
今の時代にあなたが演奏する意味はありません。
「音だけ弾いて楽しければいい」
「私は趣味でピアノをやっているから」
などと言い訳をする段階はそろそろ卒業しましょう。
その先に、
”たとえ趣味であっても”
もっと音楽の深みに入っていける楽しさが
あるのですから。
関連内容として、
という記事も参考にしてください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
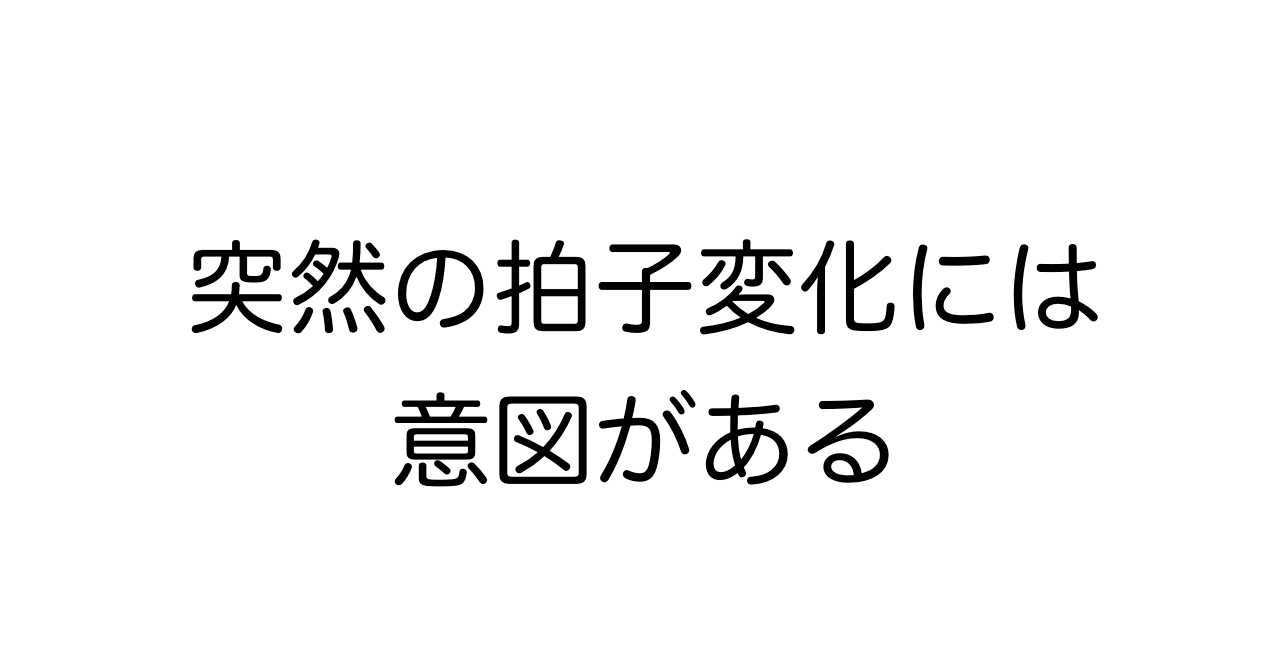
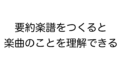
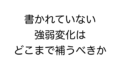
コメント