♬ 楽曲分析、よく分からなくて続かない
♬ やっても、演奏に活かせている気がしない
こういった悩みを解決します。
楽曲分析に挫折しない、たったひとつの方法。
結論からいきます。
和声分析を無視してください。
何度か書いているように
和声分析というのは
記号化してシンボルとして書くために
分析した気にはなります。
しかし、
実際の演奏に活かしにくいのです。
そのくせ、「知識」が必要。
楽曲分析を難しくしている原因は
和声分析にあると言っても過言ではありません。
和声分析をすることで
「音色を変えるタイミングを考えるヒント」
になったりと、
まったく意味がないわけではありません。
しかし、
「もっと大づかみに作品の内容をつかむ分析」のほうが
演奏に活かせて、なおかつ、取り組みやすいものが多いので
当面はそちらを優先した方がいいのです。
例えば、これまでに記事にしたものだと…
◉ メロディラインの起伏にしたがって、マーカーで色をつけてみる
◉ メロディの音程関係を調べる
◉ 役割分担をみる
◉ 書かれている「a tempo」の前に「線入れ」をする
◉ ”偽終止” の直前に線を入れる
などが、
初心者にも取り組みやすいものとなっています。
それぞれの詳細は以下リンク先記事をご覧ください。
◉「初心者でもできる楽曲分析方法」シリーズ
もう一度書きます。
和声分析を無視してください。
もう少し正確に言うとすると、
観念して、和声分析を ”いったん” 無視してください。
楽曲分析(アナリーゼ)というと
どうしても
「和声分析」や「動機分析」をすることが一番重要だと
思いがちのようです。(以前の私もそうでした。)
しかし、
少なくとも楽曲分析の初心のうちは
そういった考えからいったん離れるのが
挫折しない、たったひとつの方法なのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
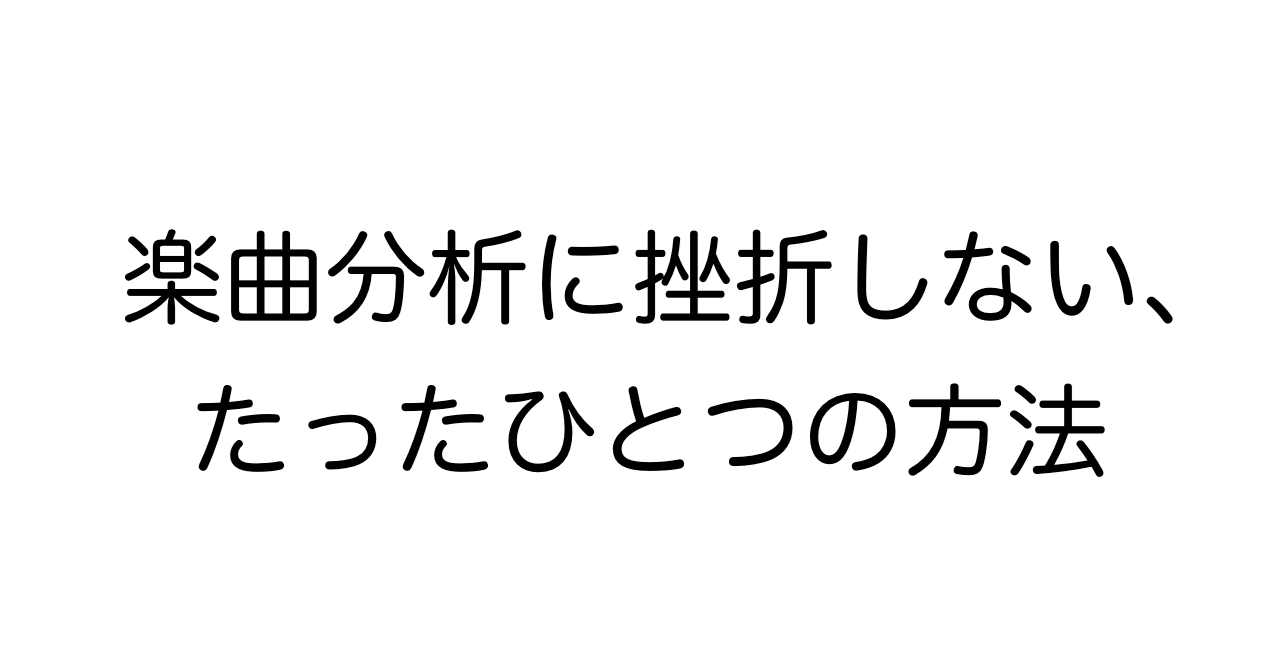
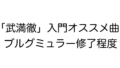
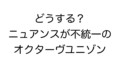
コメント