はじめに
「保続」には
「高音保続」「低音保続」がありますが、
今回は「低音保続」について取り上げます。
単純に「保続」と呼ばれることもあれば、
「持続低音」「オルゲルプンクト」「ペダルポイント」
などと呼ばれることもあります。(実は、やや意味合いが異なるのですが…)
大きくは4つに分類されます。
「何のために」「どういった時に」
使われるのか整理しました。
■作曲家が低音保続を使う意図 4選
① 主調へ戻る前の演出に(属音上の保続)
この使用例は、
「主調を用意するためにソナタ形式の展開部の最後などで登場する」
というのが定番。
具体例を見てみましょう。
クレメンティ「ソナチネ Op.36-1 第1楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成、16-23小節)
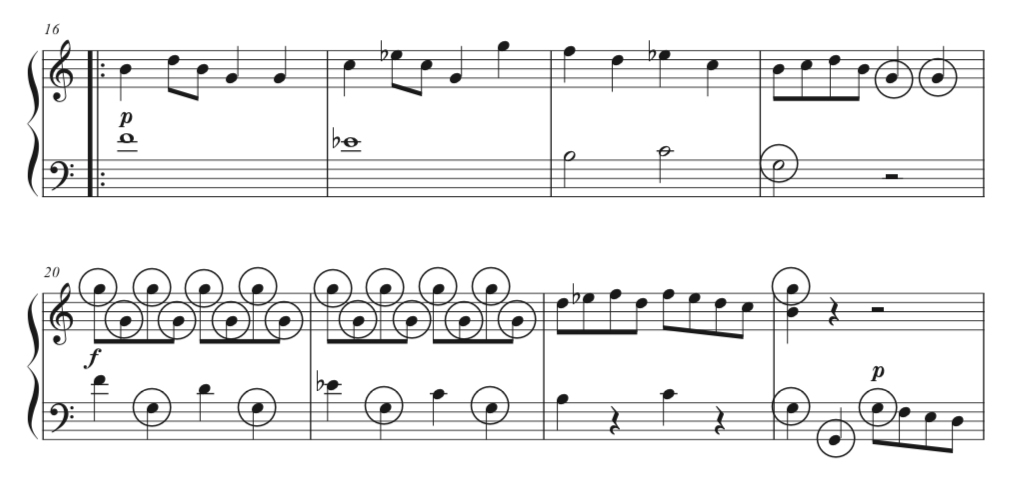
多少の例外はあれど、
ソナタ形式の再現第一主題は「主調」から始まるのがお決まりです。
展開部の最後で主調の属音を用意する事で
スムーズに再現部に入れると共に
「緊張感」「期待感」を高める効果があります。
この楽曲では
高音と低音の両方で保続をしていることがわかります。
もちろん、
「主調へ戻る前」意外にも使われる可能性があることは承知しておいてください。
② 楽曲の締めくくりの演出に(主音上の保続)
この使用例は、
「楽曲の最後に、落ち着かせて楽曲を締めくくりたい場合」
などに用いられることが多い書法です。
J.S.バッハの楽曲を中心にオンパレード。
具体例を見てみましょう。
J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第2番 c-moll」
譜例(PD作品、Finaleで作成、29-31小節目)
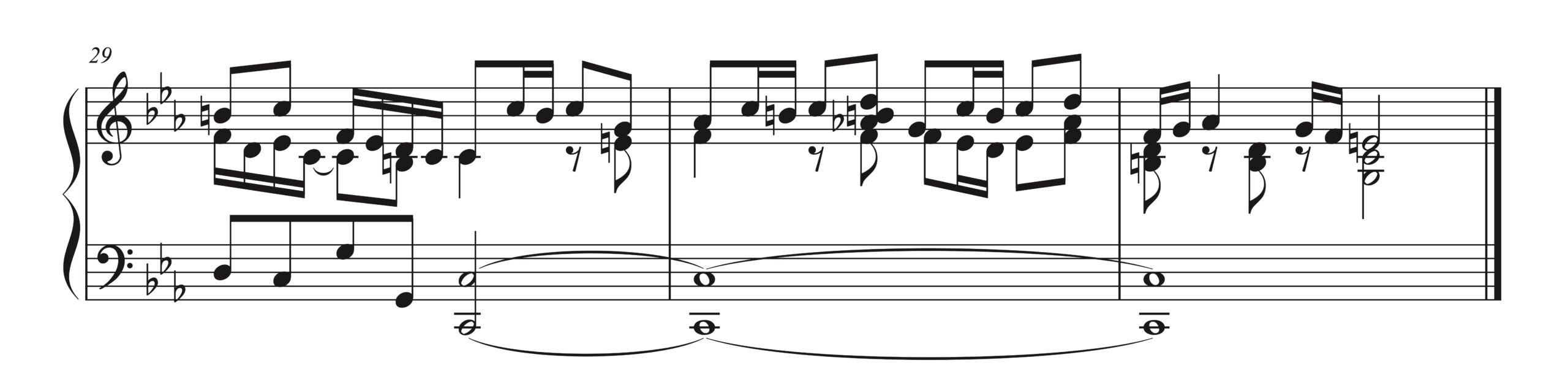
曲尾に出てくる「主音上の低音保続」で
楽曲を締めくくっています。
バスが主音でステイすることで安定しているので、
この書法が出てくる箇所というのは
全体的なサウンドとしては落ち着いて聴こえる傾向があります。
曲尾で使用されることが多いのは
そういった理由による部分が大きいでしょう。
もちろん、
「曲尾」意外にも使われる可能性があることは承知しておいてください。
ちなみに、属音と主音の「二重保持音」が使われる楽曲もあります。
③ あえて進行感はおさえておきたいとき
バスが保続されている時と比較すると、
バスが動くときというのは音楽の進行感が強くなります。
したがって、
ケースバイケースではありますが
クライマックスではバスを動かすことで、
音楽をドラマティックにする
という書法がとられるケースも見られます。
緊張感は高めても、あえて進行感はおさえておきたい時には
保続という手法はうってつけなのです。
④ 単純に保続のサウンドを求めて
聴くとすぐに感じていただけると思いますが、
保続の箇所というのは独特のサウンドがありますよね。
バスは保続されているのに
上に乗っているハーモニーは移り変わっていくので
当然と言えば当然です。
実際のクラシックピアノ曲ではもちろん、
ちょっと変わったところでいうと
民族音楽や民族系アレンジ音楽などのドローンも
「楽器の特性」「ジャンルの特性」ということと同時に
保続のサウンドを求めている例の一つと言えるでしょう。
参考動画:Amazing Grace – Bagpipe Master
今回の内容のような
「楽曲のつくり」に関しての話題を多く取り扱っているのは
それを知ることで、
「譜読み」
「楽曲分析(アナリーゼ)」
「楽曲解釈」
の力が飛躍的に向上するからです。
「楽譜のウラを読む」というくらいの心持ちで
日々取り組んでいる楽曲に向き合っていきましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
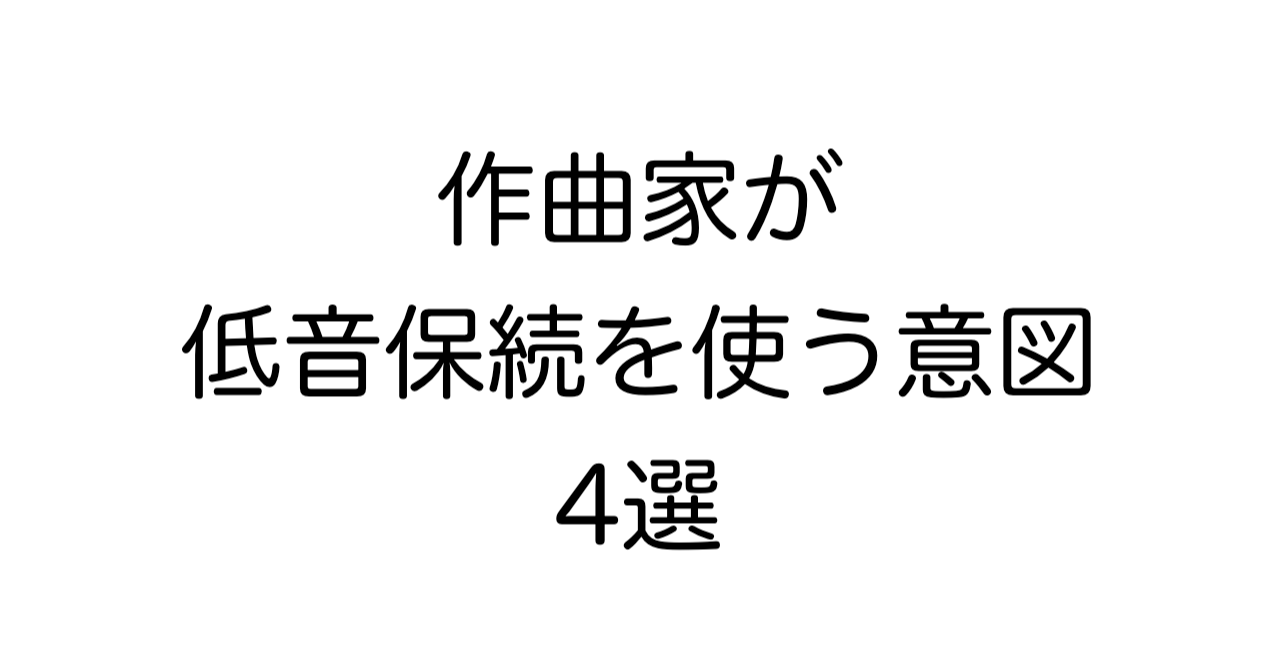
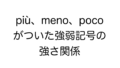
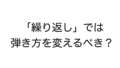
コメント