「今取り組んでいる楽曲で “出したい音(色)” 」
を想像してみてください。
「モーツァルトの緩徐楽章のフォルテ」
だったら、
「柔らかく丸い音や、深くひびくフォルテ」
かもしれません。
「プロコフィエフのフォルテ」
だったら
「モーツァルトよりは立ち上がりの鋭いフォルテ」
かもしれません。
演奏者によってある程度の差があるでしょう。
つまり、
表現したいことがはっきりすると
「それを表現するために必要なテクニック」
が見えてきます。
そして、それを身につける。
これがテクニックをまなぶ望ましい手順です。
「出したい音(色)をピアニッシモで出す」
というのも
大事なテクニックのひとつということ。
「出したい音(色)をピアノで出す」ために必要なのは、
「出したい音(色)を自分の中で鳴らすこと」
「出したい音(色)を自分の中で鳴らせるようになる」ために必要なのは、
「ピアノが出せる音(色)の可能性をひとつでも多く知っておくこと」
そして、
「一曲を深く学ぶこと」
これが欠かせません。
「作曲の基礎技法」(シェーンベルク 著)にも
このような重要な一文があります。
これはつまり、
「出したい音(色)を自分の中で鳴らすこと」
これにほかなりません。
出したい音(色)を自分の中で鳴らし、その音をつかみにいく。
これは「演奏家」「作曲家」共通の
音楽にとってもっとも重要な部分。
演奏家は、
自分の中に聴こえない音は出せません。
仮に一回だけ出せたとしても
再現性がなく
本番で同じことはできません。
作曲家は、
自分の中に聴こえない音は書けません。
「こういう音が欲しい」
と自分の中で鳴るからこそ、
「ではここではこのようなリズムや音色を使って・・」
などといったように
表現と結びついてくるのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
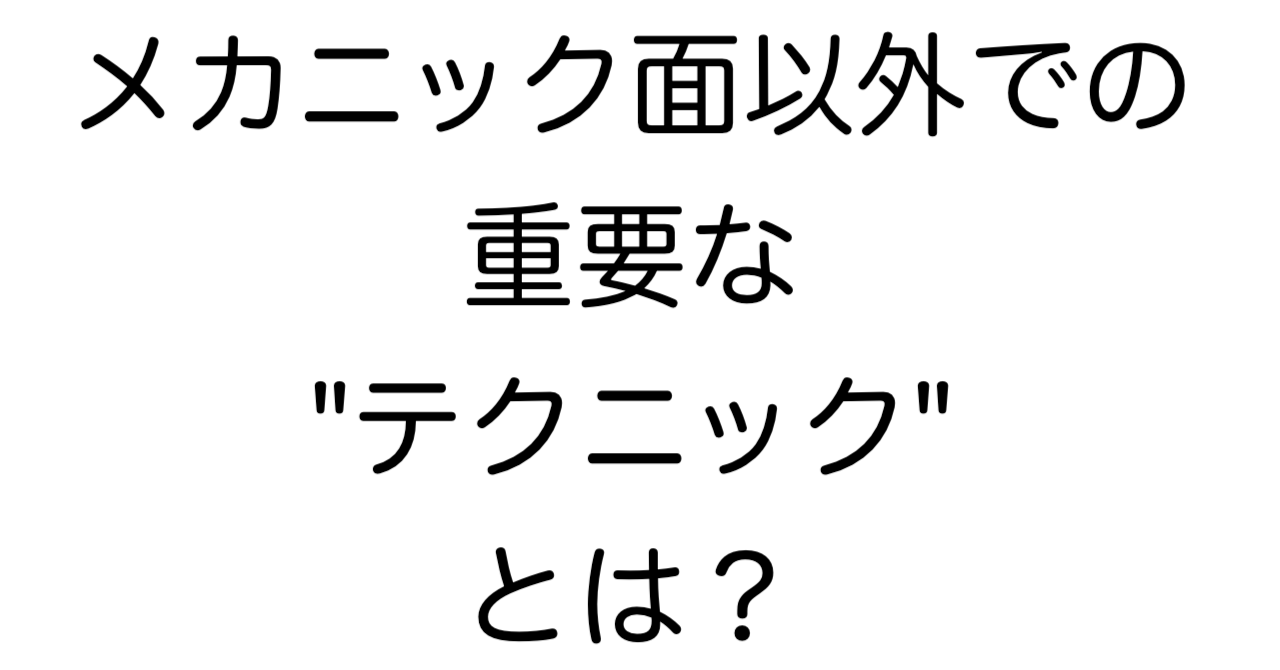

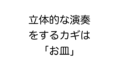
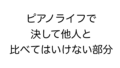
コメント