具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
譜例を見てください。
ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 熱情 ヘ短調 op.57 第2楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成)
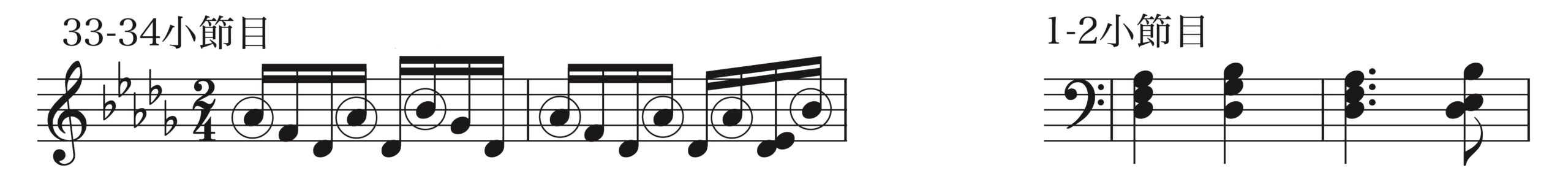
譜例左(33-34小節目)では
右手が16分音符で動いていますが、
すべての音がメロディというわけではなく、
丸印をつけた音がメロディです。
その判別ポイントは、譜例右(1-2小節目)のメロディ。
「1-2小節目と同じメロディ(As音とB音)で出来ているバリエーション」
であることが分かりますね。
ピアノの譜面では、
煩雑さを避けるために
あえて声部分けなどをしないことも多いのです。
したがって、譜例のように、
細かいパッセージの中から
演奏者自身が
メロディを抜き出して考える必要があります。
そうすることで、
「聴かせるべき音(多めに出す音)」と
「響きの中に隠すべき音(静かに弾く音)」
の区別がつき、立体的な演奏になります。
(再掲)
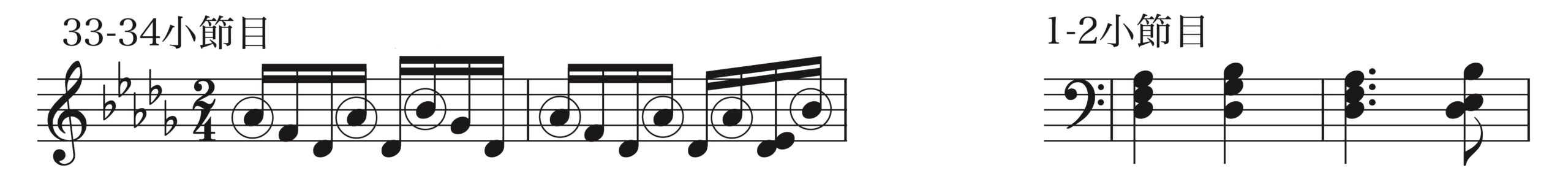
細かいパッセージからメロディを見つけるためには、
やはり、今回の例の1-2小節目のように
「前の部分に、似たメロディがあるかどうかをチェックする」
という方法が有効でしょう。
もうひとつの方法は、
「まずは音域の高い音を疑ってみる」
というものです。
譜例を見るとわかりますが、
この例でも
パッセージの中で音域が高い音に丸印がついていますよね。
ここまで踏まえたら、
あとは「勘(カン)」に頼るしかない。
「この音がメロディかな?」
などと、
音を出しながら探ってみて発見するのもいいでしょう。
繰り返しますが、
「細かいパッセージからメロディを拾い出す」
という技術は、
立体的なピアノ演奏をするために
非常に重要なテクニックとなってきます。
それをせずに、
すべての音を均等にゴリゴリと弾いてしまうと
音楽的な演奏には到達できません。
「今いちばん聴かせるべき音はどの音かな」
という視点を常に持って
楽譜を読んでいきましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
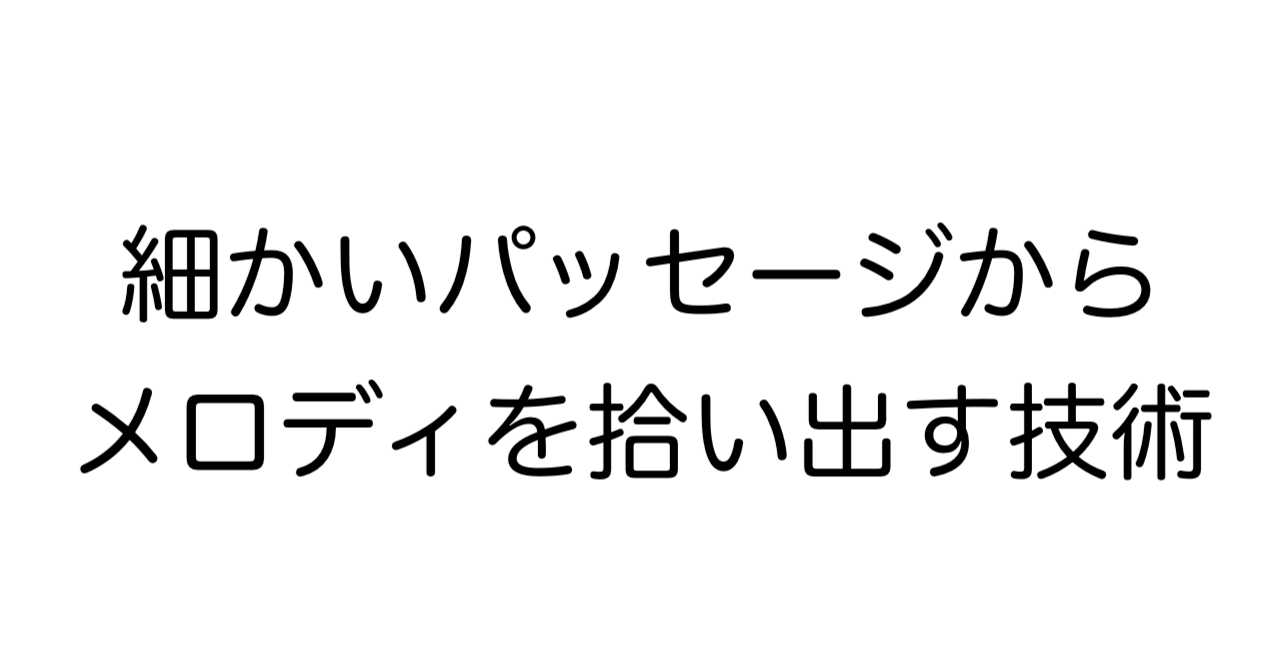
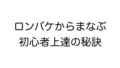
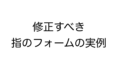
コメント