「すみ分け(住み分け・棲み分け)」について、
まず広辞苑に載っている意味を確認してみましょう。
生活様式が類似する動物の個体または個体群が、
種としては同じところに棲めるのに、
競争などの相互作用の結果、
生活の場を空間的または時間的に分け合う状態で生存する現象。
(抜粋終わり)
次に「すみ分け」の音楽的な使用例や注意点について解説します。
例えば、
◉ 音域が大きく離れていれば、2つの要素を互いに大きく出しても邪魔しあわない
◉ 接近した音域にある複数の要素をどちらも強調してしまうと、どこを聴いていいのか分からなくなる
など。
それぞれの「すむ場所」を「分ける」ということであり、
すみ分けを意識することで
スッキリした演奏に仕上げることができます。
作曲家は作品のつくりとして
ある程度「すみ分け」を意識しているはず。
しかし、
演奏としてもそれを考慮してあげなくてはいけません。
時々、一度にたくさんの要素を聴かせる部分を含む作品もありますが、
基本的には
そのときに聴かせたい要素はひとつに決まっています。
それをきちんと聴かせるためには
「どの要素を控えて、どの要素をたててあげて…」
などという単純なことに始まり、
「音域」や「音色」も考慮しながら
主役の要素をきちんと主役として聴こえるように
演出してあげなければいけません。
f を例にとると、
「 f と書かれていれば、全ての要素が f 」
という解釈をするのではなく、
「全体として f のエネルギーに聴こえてくる」
というバランスを探る。
そのためには、
主役は f の骨太な音で弾き、
伴奏部分は mp で弾くのが適切かもしれませんし、
その作品のその箇所の前後関係も踏まえて
決定していくのです。
今回なぜ「すみ分け」の話題を取り上げたのかというと、
ピアノは単旋律楽器ではないため
その演奏では
一人でオーケストラのようなアンサンブルをするからです。
実際のオーケストラでは
「配置」や「音色」ですでにすみ分けされています。
例えば、
「弦楽器群よりも管楽器群は(前方客席側から見ると)奥にいて、
さらにその奥に打楽器群がいて…それらの並び順にも定型があって…」
などといったように。
さらに演奏面でも
各演奏者自身や指揮者が的確にバランスをとっていき、
「聴こえすぎている音」や「聴こえなさすぎている音」には
バランス調整、音色調整を試みて
場合によっては席の配置まで変更することで
適切にすみ分けていきます。
しかしピアノでは、
「配置によるすみ分け」も
「音色によるすみ分け」もできません。
原則、どの音もそのピアノの置いてあるところから出てきますし、
ピアノという楽器が出せる範囲内でしか音色も変化しないからです。
だからこそ
「”演奏の仕方” ですみ分ける意識は絶対に忘れるべきではない」
ということを踏まえておくべき。
具体的なすみ分けのやり方は
このブログでも度々取り上げています。
各パートの音が住む(棲む)べき場所をていねいに読み取ることで
音楽的な演奏を目指しましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
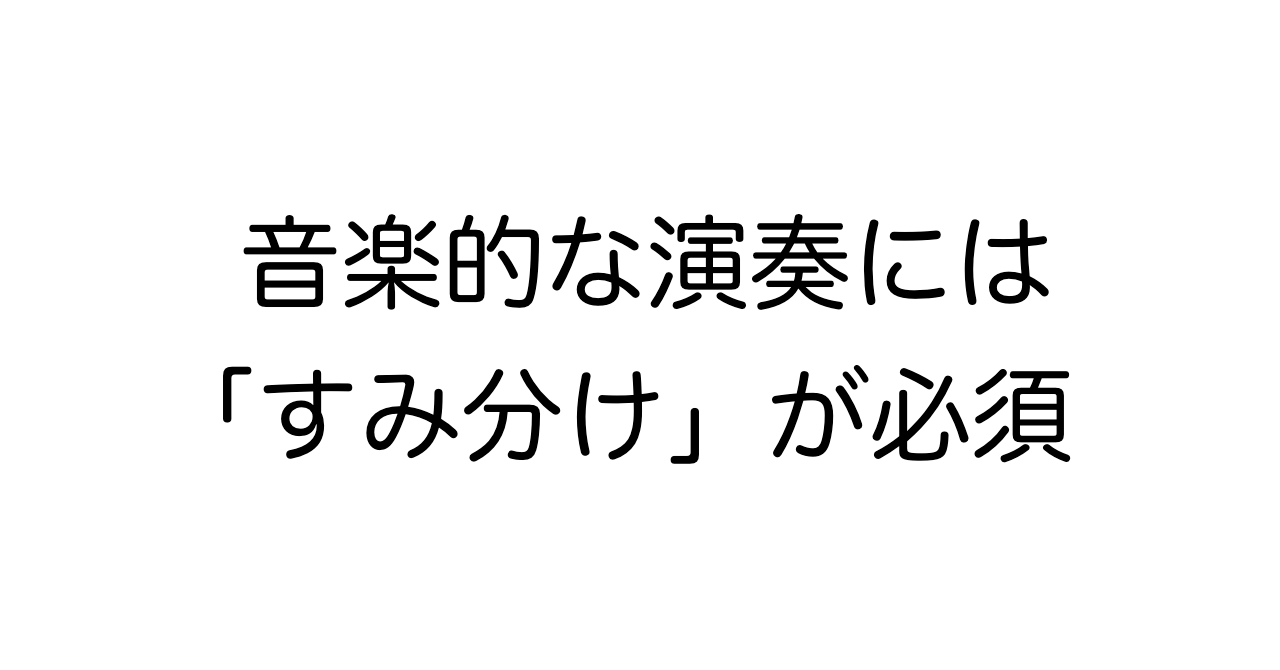
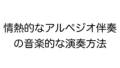

コメント