■「繰り返し」では弾き方を変えるべき?
♬「繰り返し」で弾き方を変えるべきケース
「繰り返し」で弾き方を変えるべきケースというのは
いたってシンプル。
聴衆にとって”今さっきと同じことが繰り返されている”
ということが明らかに分かるケース
です。
以下の譜例を見てください。
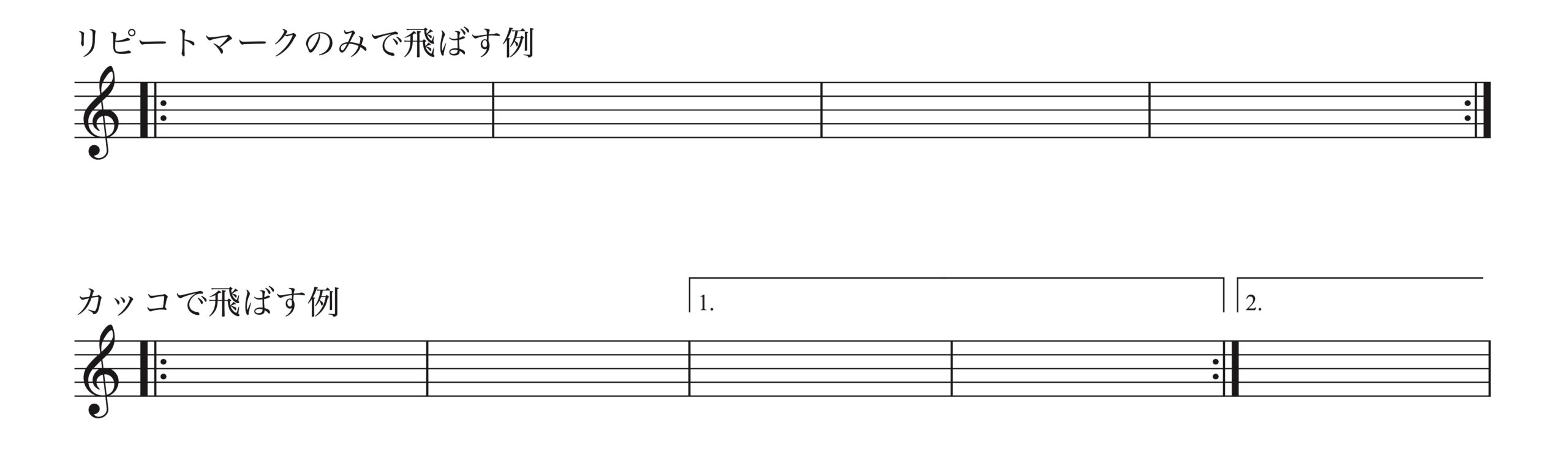
この「A-A」のような繰り返しが該当します。
特に「短い単位」で繰り返される場合は
聴衆にとって「繰り返されている」ということが明らかですよね。
そういったときにまったく同じ弾き方をしてしまうと
聴衆を退屈させます。
「強弱」「アーティキュレーション」「ペダリング」
などの解釈に何かしらの変化を与えましょう。
このような工夫は
作曲家の意図を無視しているとはみなされません。
さらなるケースを挙げます。
ソナタ形式の提示部というのは
ベートーヴェンの中期作品くらいまででしたら
ほぼ必ずといってもいいほど
提示部全体をリピートするように作曲されています。
その場合は、
ある程度の長さのものを反復することになりますが
繰り返しで弾き方を変えることは良くおこなわれます。
「A-B-A-B」という例ですね。
♬ 「繰り返し」で弾き方をあえて揃えるのもアリのケース
楽曲によっては、
「A-B-C-D-E-A」
などと、別の多くのセクションが挟み込まれた後に
まったく同じ形での繰り返しが用意されているケースもあります。
(A-B-C-D-E-Aの場合は、Aのこと)
例えば、
武満徹「雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-」
など、他にもいくらでもあります。
(ちなみに、これらの楽曲構成はA-B-C-D-E-Aではありませんが、同様の考え方ができる作品です。)
こういった楽曲のように
多くの別セクションを挟んだ後に
ひとつのセクションだけが回想的に戻ってくるときは
あえて同じように表現を揃えておくことが有効なケースもあります。
「やっと帰ってきた印象」や「楽曲全体の整合性」
を感じさせることができるからです。
それに、短い単位をすぐに繰り返しているわけではないので
先ほどの例のように飽きさせることもありません。
この辺りは解釈次第。
変えてもいいでしょうし、変えないことの良さもある。
前項の
♬「繰り返し」で弾き方を変えるべきケース
との違いを理解してください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
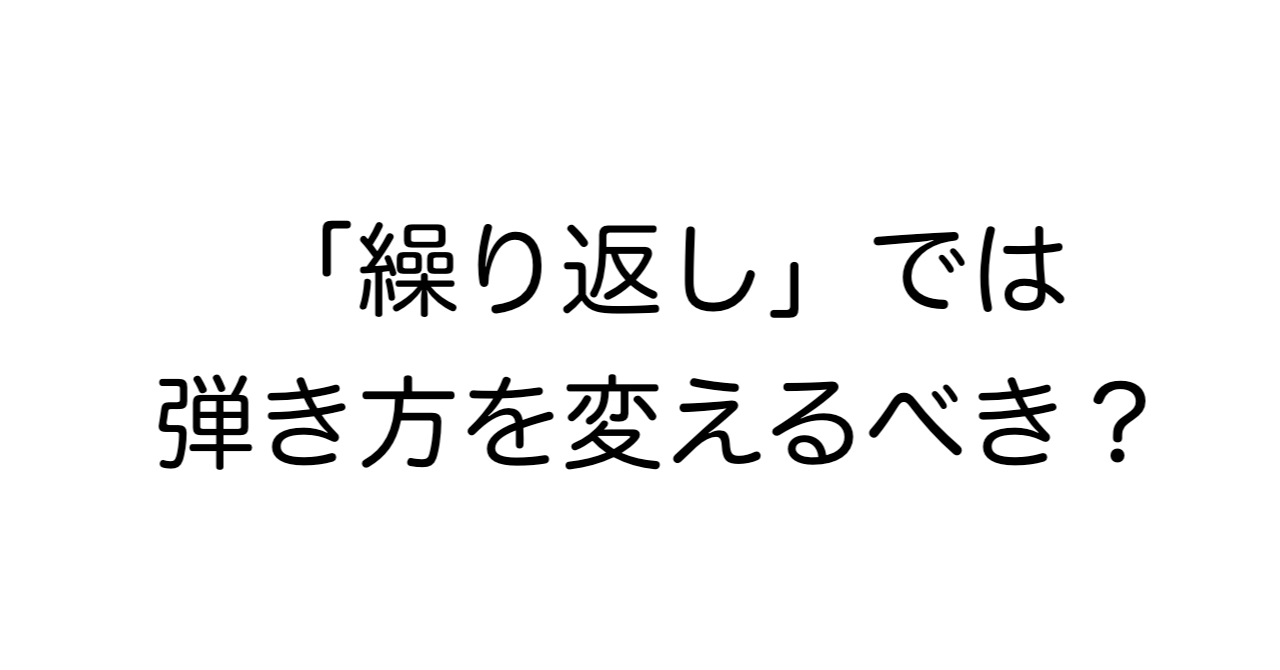
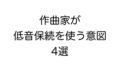

コメント