■プロコフィエフのピアノソナタ入門
♬ 最初に結論
プロコフィエフのピアノソナタとなると、
一番取り組みやすい作品であっても
それなりの難易度になります。
それは予め踏まえておかなくてはいけません。
結論から言うと、
入門に最適な作品は、
「ピアノソナタ第1番 ヘ短調 作品1」
となります。
この種の挑戦において考慮すべきなのは、取り組みやすさ。
その観点でいうと、
1番のソナタや3番のソナタなどは「単一楽章」によるソナタですので、
練習のハードルが下がります。
それに、
「8分程度」の1つの楽章を仕上げるだけで即、
演奏会用のレパートリーになるのです。
また、
プロコフィエフのソナタの中でも1番のソナタは
「ロマン派の名残が強い近現代作品」ですので、
◉ プロコフィエフの後期の作品に繋がる個性
これらを併せ持っています。
したがって、
ロマン派の作品に多く取り組んで来た学習者にとっても
挑戦しやすいでしょう。
♬ 難易度
メカニック的なテクニック面の観点で言うと、
1番のソナタはプロコフィエフのソナタ中、難易度的に最も容易です。
それでも、最低でも「ツェルニー40番の後半」程度の力は必要です。
しかし、考えてみて下さい。
何も、1日で弾けるようになる必要はないのです。
日頃取り組んでいる作品と並行して、
こっそり練習してみてはいかがでしょうか。
♬ 推奨する楽譜の版
「Boosey & Hawkes」一択です。
プロコフィエフの作品に取り組む多くの方は、この出版社の楽譜を使います。
国際コンクールにおけるプロコフィエフ作品の使用楽譜の定番でもありますので、
迷わず選んで下さい。
ちなみに、
日本で手に入るプロコフィエフの楽譜はそれほど種類が多くありませんので、
普通に選べばコレになるとも言えるでしょう。
「ピアノソナタ第1番 ヘ短調 作品1」のみが収載された
「Boosey & Hawkes」の楽譜も売られていますが、
紹介している「1-5番までのソナタが全て入っている楽譜」は
1番のみの楽譜の2倍もしない価格で手に入るので
購入するのであれば
ぜったいにアルバム版がオススメです。
♬ 練習における注意点
練習における注意点は以下の2つです。
② 運指の決定をていねいに行うこと
① 臨時記号に細心の注意を払うこと
この作品は「12/8拍子」ですので
一小節に入る音が多くあります。
加えて、臨時記号もかなり多い作品です。
したがって、
臨時記号に細心の注意を払って譜読みしないと、
小節内有効臨時記号を見落とす可能性があります。
実際にこの作品で譜読み間違いをしている演奏は
たびたび聴かれます。
プロコフィエフやラフマニノフの作品では、
ゆっくりさらっていると
今演奏している内容が正しいのか分からなくなるようなフレーズが多くあります。
そういった音楽的な特徴が、
小節内有効臨時記号の見落としに気づきにくい理由にもなるのでしょう。
② 運指の決定をていねいに行うこと
Boosey & Hawkesの楽譜には、
運指があまり書かれていません。
したがって、
運指の決定を自分の力でおこなわなくてはいけないのです。
一度クセになった運指を修正するのは
思った以上に困難を伴うので、
最初に決定する際に
ていねいな考慮をおこなっておくのが得策でしょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
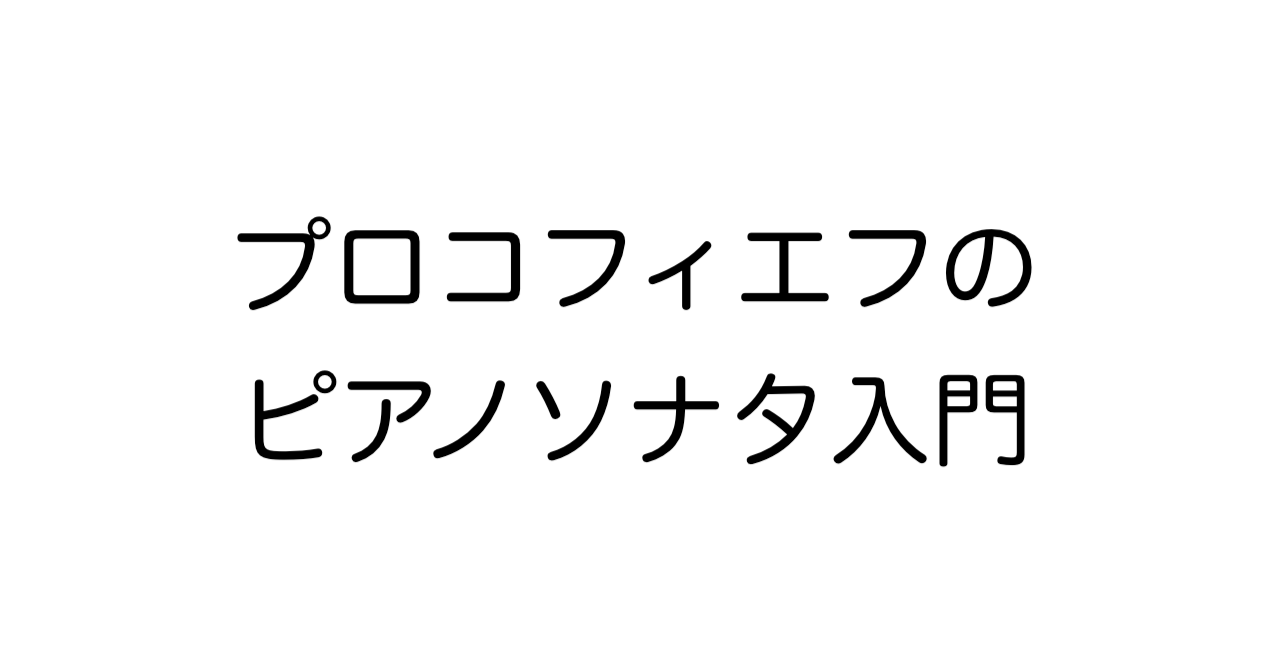

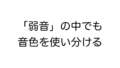
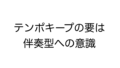
コメント