ピアノ作品に限らず
fp という表現は
さまざまな時代の作品で用いられています。
「音が大きいか、小さいか」で表現するのみでなく、
その表現が出てきた意味を考えることも大切です。
考えてみたことはありますか?
楽曲によって
fp にはさまざまな意図がありますが、
「遠近感を出すため」
と考えると
楽曲のイメージとマッチすることはよくあります。
つまり、
「 f で一瞬音像の近づいた表現がされ、p では遠いところで鳴っている表現になる」
これが瞬時におこなわれるわけなので
一瞬の音像の移行を
立体的な表現として感じることができるのです。
少し、遠近感そのものについて話をしましょう。
オーケストラでは
◉ 楽器ごとの音色の違い
などをはじめとして
あらゆる要素で遠近感を表現可能。
一方、ピアノでは
◉ ピアノという、ひとつの楽器が出せる音の中での音色幅
これを前提として
遠近感を表現していかないといけません。
したがって、
「打鍵の仕方」「ペダリング」
などの限られたテクニックで
音色をコントロールしていくことになります。
オーケストラよりも遠近感を出すための制約がある。
ひとりの奏者が「遠」も「近」も表現する。
だからこそ、
ピアノ演奏では特に
遠近感をイメージすること自体が大切になってくるのです。
そのイメージを持っていると
“無意識に” 音の出し方にコントロールが生まれるからです。
イメージがないところには距離感は生まれません。
生まれたとしても、
もう一度弾いた時に再現性がありません。
「出したい音をイメージして音を出す」
ということを忘れないでください。
そこから先、
「では、どのようなテクニックでそういう音が出せるのか」
という部分についても、
結局は出したい音が頭に鳴らないと
どうしようもないのです。
【ピアノ】一度の打鍵で fp を表現するためには
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
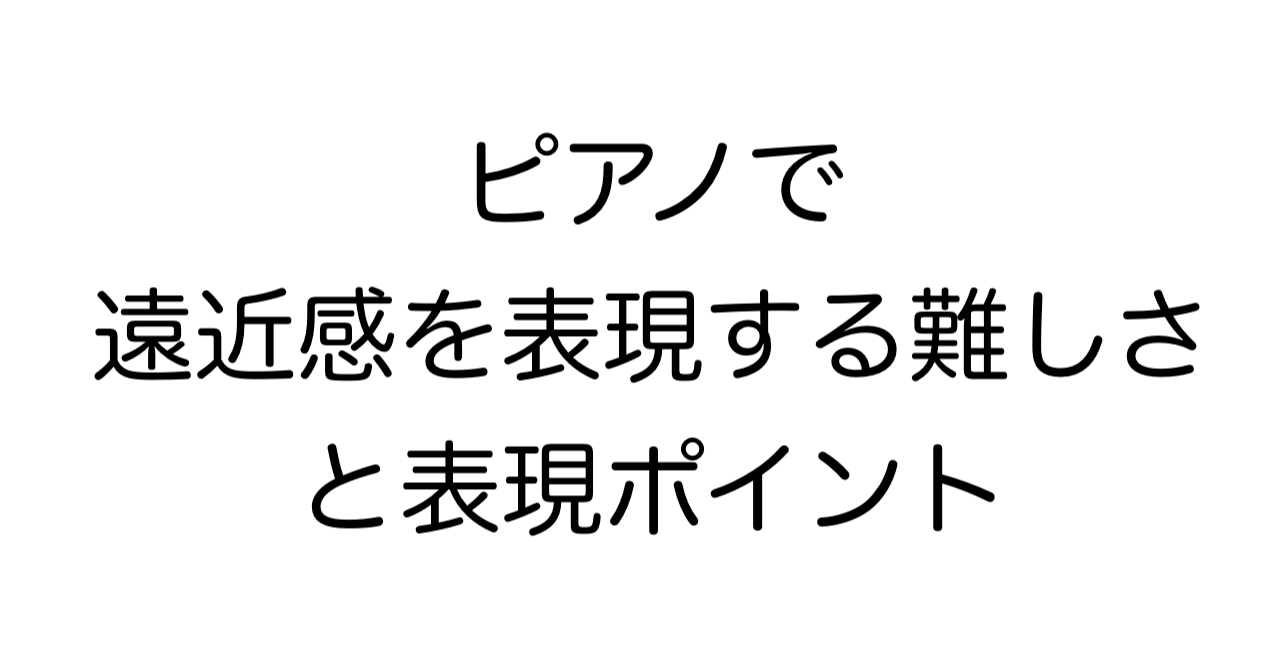
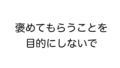
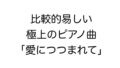
コメント