■シェーンベルク入門 & 無調音楽入門
♬ はじめに
「無調音楽」と聞くと
即座に拒否反応が起きてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
無調作品の中でも
取り組みやすいシンプルな作品を学習すれば
調性音楽とは違った良さを感じることでしょうし、
音楽の幅を広げることができます。
一度はまってしまうと
良い意味で抜け出せなくなるのです。
無理なく取り組めるシンプルすぎるピアノ曲を紹介しますので
あなたのピアノライフに
新たな1曲を追加してください。
♬ 無調音楽入門は、シェーンベルクのop.19で
無調音楽へ入門するときに最適のピアノ曲は
シェーンベルク「6つの小品 op.19(1911)」です。
1911年といえば、
ラフマニノフが「絵画的練習曲(音の絵)」、
ラヴェルが「高雅で感傷的なワルツ」
などの美しい旋律を持つ作品を書いていた頃ですから、
シェーンベルクは
当時としてはずいぶん時代を先取りしていたことになります。
「6つの小品 op.19」は
その名の通り、全6曲からなっている小品集。
無調音楽入門に最適の理由は
1曲1曲が ”短すぎる” からです。
もっとも小節数が多い第1曲でも17小節、
もっとも小節数が少ない第2曲、第3曲、第6曲にいたっては
たった9小節しかありません。
テクニック的には
「ブルグミュラー25の練習曲 中盤程度」から取り組めます。
したがって、
「曲尺」「難易度」
これら両方の視点で
非常に練習しやすい作品となっています。
無調に入門する学習者にとって最適の作品と言えるでしょう。
同時に、
シェーンベルクというイチ作曲家のピアノ曲入門にも最適。
もちろん音楽的には深さがあり、
そういった意味で
簡単な作品とは言えません。
言い換えれば、
「シンプルながらも、ずっと使えるレパートリーになる」
ということです。
♬ オススメの取り組む順番
全6曲のうち、第1曲が一番長い作品です。
(と言っても「17小節、演奏時間約1分半」ですが…。)
音楽的には第1曲と第6曲が特に深い内容。
これらを考慮すると、
以下の順序で練習するのがいいでしょう。
もちろん、
全音ピアノピースの難易度表でいう「C」程度の作品を
問題なくバリバリ弾ける方は
第1曲から順番に取り組んでも問題ありません。
♬ オススメの使用楽譜
楽譜は「Universal Edition(ユニヴァーサル・エディション)」を使用しましょう。
初版もこの出版社ですし、
op.19に取り組む専門家は
基本的にこの楽譜を使います。
◉ シェーンベルク : ピアノ作品選集/ウニヴァザール社
シェーンベルクはピアノソロ作品を「全5作品」作曲したのですが、
この楽譜集にはそれらのすべてが収録されています。
ちなみに、
シェーンベルクおよび、
その弟子の「ベルク」「ウェーベルン」をあわせて
「新ウィーン楽派」と呼びますが、
ベルクとウェーベルンは
ユニヴァーサル・エディションでアルバイトをしていたのです。
とても近しい出版社だということ。
今後、シェーンベルクも含め
新ウィーン楽派の作品に取り組む際、
ユニヴァーサル・エディションが手に入る場合は
迷わず選んでOKです。
ピアニストによる公式演奏動画があります。
◉ Schoenberg Sechs Kleine Klavierstücke, Op. 19
♬ おまけ : どうしてこんなにも曲尺が短いのか
何度も書きますが、
この作品(op.19)は1曲1曲がほんとうに短い。
シェーンベルクはなぜこんなにも短い作品を書いたのでしょうか。
実は、短すぎる作品はこれだけではないのです。
シェーンベルクが近い年代に書いたいくつかの作品に加えて、
弟子のウェーベルンも
1909年から驚くほど短い作品を作曲しています。
いろいろな理由が考えられますが、
「無調音楽の黎明期で、音楽思想や音楽語法を試行錯誤していた時期だったから」
というのが大きな理由のひとつとしてあるでしょう。
シェーンベルクはウェーベルンの短い作品に対して
「ひとつのため息で一巻の小説を書いた」
などというコメントを残しています。
このop.19にも通ずるところがありますね。
語り出せば長くなってしまうので、
今回はこのあたりでいったん筆を置きます。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
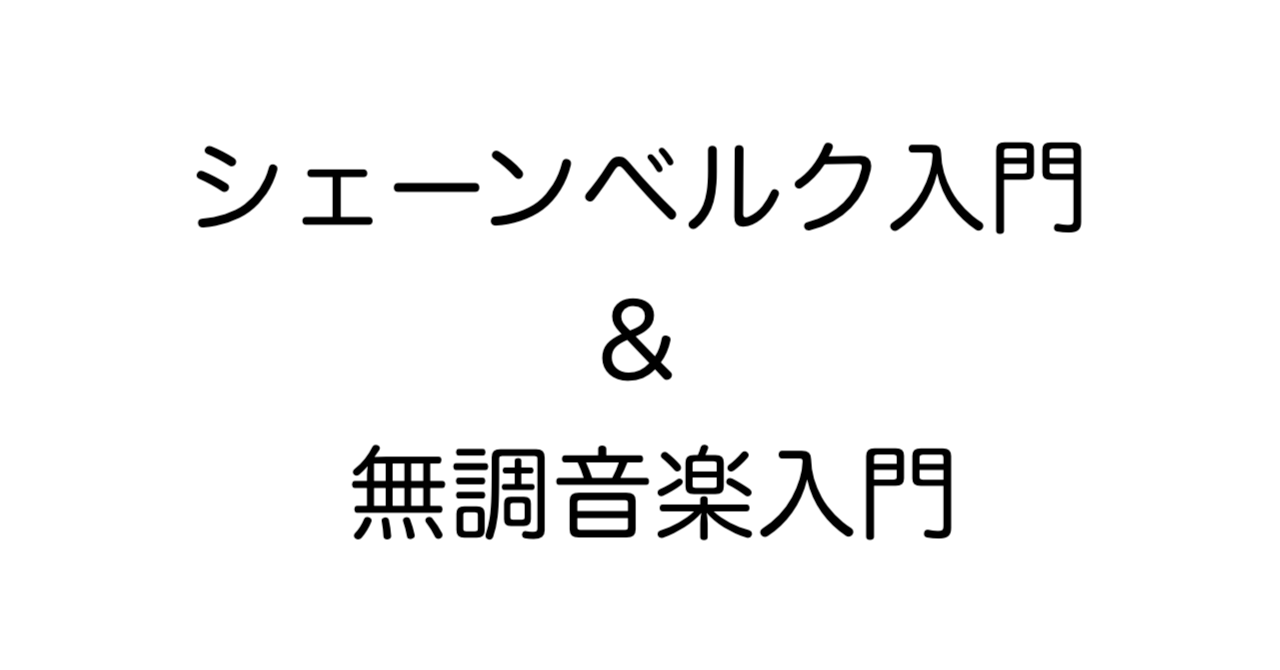

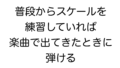
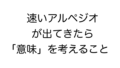
コメント