「譜読み」に鋭くなるためには、
「楽譜(五線記譜)というものの不完全さ」
を知る必要があります。
「音程」や「リズム」は比較的書き表せます。
「民族音楽のナマリ」や「極度のルバート」
などは楽譜にすることが困難ですが、
一般的なクラシック作品に出てくる内容でしたら
作曲家が思っていたであろうリズムが
私たちにも伝わってきますよね。
では、「楽譜の不完全さ」として
「楽譜に表しにくい要素」とは何でしょうか。
いくつかありますが、
代表的なものは「音色」です。
「音色」について楽譜(五線記譜)は強くありません。
現代曲の場合は、
楽譜に「言葉」で
音色についての指示が書き込まれている場合もあります。
しかし、近現代以前の作曲家による作品では
言葉による音色についての指示はあまり見られません。
例えば、
「ダンパーペダルの指示があるのに、音符にはスタッカートがついている場合」
このケースでしたら、
「空間的な音色が欲しいのだろうな」
などと予想はつきます。
しかし、
音程やリズムの指示に比べたら
非常に曖昧なものですよね。
このようにして、
まずは「楽譜(五線記譜)というものの不完全さ」を知ることで
譜読みの際に
◉ 何を読み取ればいいのか
◉ 何を想像に任せればいいのか
◉ 何を想像に任せればいいのか
などといったことに鋭くなり、
学習の幅が広がるのです。
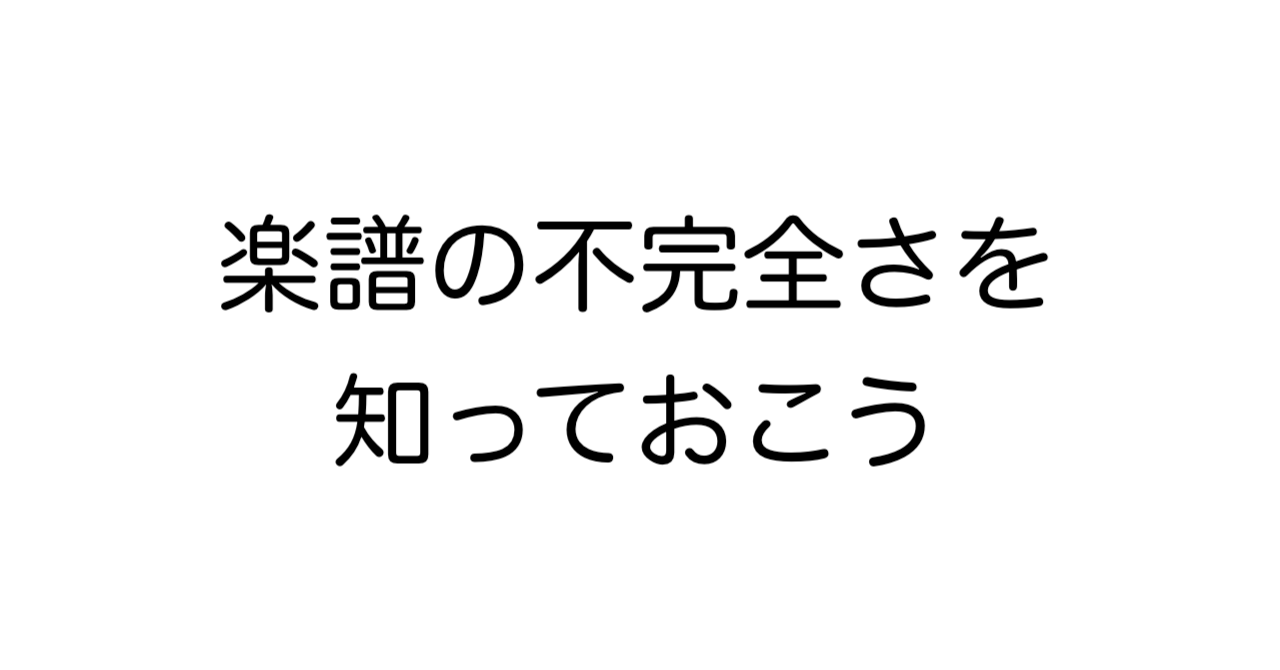
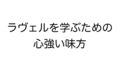
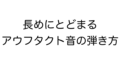
コメント