一般的にピアノの練習時間は
「質より量」
「量より質」
「量と質」
などと、人によって意見が様々ですね。
一方、そういった会話の中で「練習時間の管理の仕方」は
語られていないことがほとんど。
そこで今回は、
独学の大人の方が
どうやって毎日の練習時間を管理していくべきかを
4つの視点から提案していきます。
■「練習時間の管理方法」4つの視点
♬ 休憩するタイミングは「時間」で区切る
練習中の「休憩するタイミング」というのは
「時間」で区切るべきです。
「ピアノを弾く」という行動は
私たちが思っているよりもずっと
人間の身体にとって「日常的ではない動き」をしています。
自分ではそれほど疲れを感じていなくても
手や腕などへの負担はたまっています。
集中するとぶっ続けで練習してしまいがちですが、
手を故障しないためにも
必ず休憩時間を挟むべきです。
それに、これまでピアノに向き合ってきた経験から、
ほんとうに密度の濃い集中力は
「40〜50分程度」
しか続かないと自覚しています。
大人にとってはそう大差ないでしょう。
つまり、休憩を挟むことは
「集中による練習の質を上げる」
ということにもつながるのです。
ポイントとして、
初級の方は「15分〜30分に1回の休憩をとる」
中級以上の方は「最低でも50分に1回の休憩をとる」
このようにするといいでしょう。
間の休憩は「5〜10分程度」にしておき、
長すぎない方が
音楽へ向かう姿勢自体は保てるはず。
短くても必ず、
「上半身」と「頭」を休める時間をつくります。
もし、意欲的に
「たくさん練習したい」
という方であれば、
上記の時間を「セット」にすればいいのです。
例えば、
15分×数回
30分×数回
45分×数回
など。
「15分×数回」などでしたら、初中級の方でも取り組んでいけますよね。
一方、この区切り方は休憩するタイミングを決定するためのもの。
その日の練習全体は、
時間ではなく「曲数」で区切る方法をオススメしています。
次の項目で解説します。
♬ その日全体の練習は「曲数」で区切る
今取り組んでいる楽曲が1曲の方は
その1曲を練習すればいいのですが、
2曲以上に取り組んでいる方は、
ムリのない程度で
「今日はこの曲とこの曲に取り組もう」
などとピックアップして決めておき、
それらの練習が済めば
時間が多少短くても練習を終わりにする、
という管理の仕方は効率的。
というのも、
仮に「今日は1時間練習しよう」などと時間決めておいて
1時間経った時に区切りの良くないところだと
その日1日中、モヤモヤが残るからです。
曲で区切るようにしておくと
充実感をもったまま練習を終えられます。
この違いは非常に大きい。
♬ 基礎練習には時間をかけ過ぎなくても良い
練習時間での悩みどころは
「基礎練習の練習時間」だと思います。
結論から言うと、
時間をかけすぎる必要はありません。
特にハノンなどの基礎練習をはじから全部こなそうとしてしまうと、
毎日たくさん弾くことに注力してしまい、
ただの作業になってしまいます。
基本的には「最低限の基礎練習」のみをおこない、
むしろ楽曲に取り組んでいくことへ意識を向けます。
そして、
楽曲の中で表現したい内容のために必要なテクニックが出てきたら
そこで「逆引き辞書的に基礎練習に戻る」、
というのが順序としては効果的。
では、どうやって「最低限の基礎練習メニュー」を作ればいいのか。
ハノンを例に解説します。
オススメするのは、
「46番(トリル)」と「60番(トレモロ)」。
これは毎日行うことを勧めます。
「46番(トリル)」は3の指と4の指という
動きにくい指間を連続して使用するので良い訓練になります。
スケールなどで転んでいる時も、
実は「どこか隣り合った指間がもつれている」といったように、
特定のところに問題が発見される場合が多い。
「60番(トレモロ)」は通して弾いてみると
「親指の根元のふくらんだ部分の筋肉」
がものすごく疲れると思います。熱くなりますよね。
しかし、ありとあらゆる作品でトレモロは頻出しますし、
普段衰えがちな筋肉をしっかり動かしておく意味でも、
60番はていねいに練習すべきです。
どの番号でも同様ですが、
「今、どこの部分のトレーニングになっているのか」
を必ず意識して練習してください。
何となく毎日ハノンを触ってたら勝手に上達してた、何てことはあり得ません。
全調スケールやアルペジオに取り組む学習者が多いようですが、
まずは「46番(トリル)」と「60番(トレモロ)」を
徹底的に練習してみるといいでしょう。
実際のメニューとしては、1番から31番までの中から数曲抜粋し、
それに「46番(トリル)」と「60番(トレモロ)」を加える。
そして、
余裕があれば自分の弱点に合わせて辞書の逆引き的に他の番号をいくつか加える、
というのがオススメです。
いずれにせよ、
基礎練習は飽きないように工夫して練習できるかどうかがカギ。
♬ 通し練習は1曲につき1〜2回にとどめておく
「通し練習」の時間配分についても触れておきましょう。
通し練習というのは
ピアノ練習の中でもっとも体力と頭を使う練習です。
本番前は何回も「通し練習」をしたくなる気持ちも分かりますが、
集中した通しを、一曲につき1〜2回程度にして、
残りは部分練習にあてることをオススメします。
そのように決めておいたほうが、
「通し練習そのものへの集中度」もよりアップするでしょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
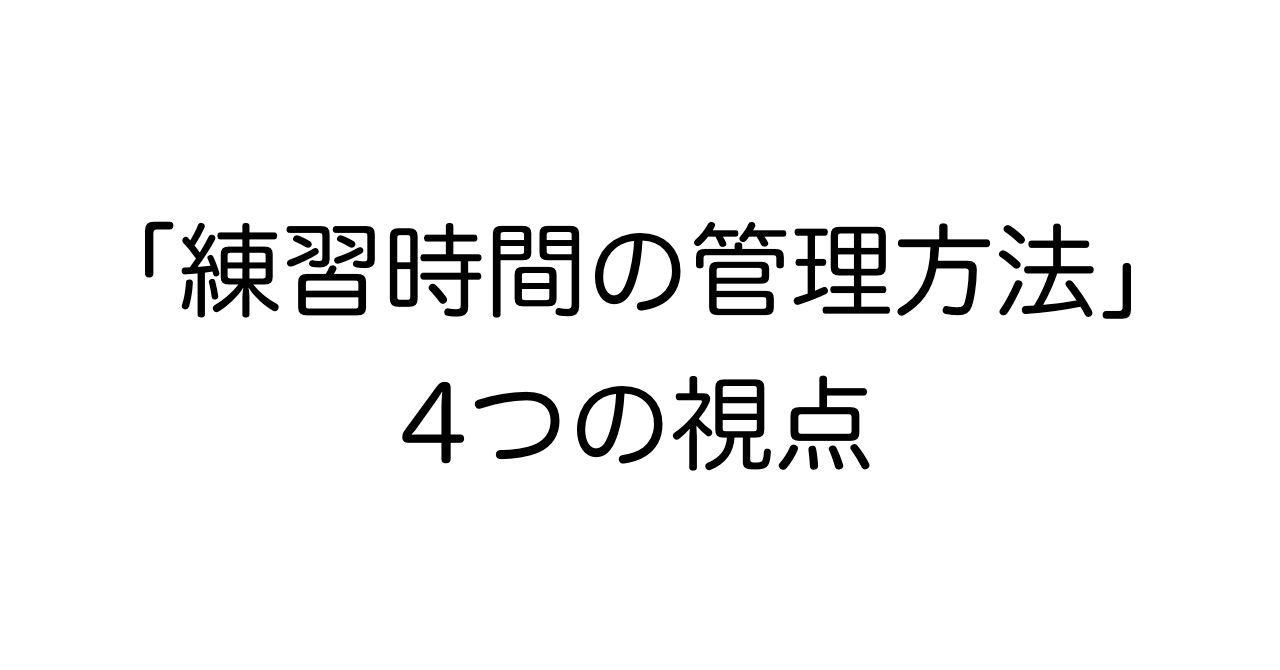

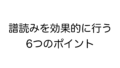
コメント