「譜読み」の重要性は強調してもしきれないほど。
「速く」読めるようになることも目指すべきですが、
むしろ「正しく読むこと」のほうをより重視すべきです。
なぜなら、譜読みの仕方によっては
「悪いクセ」がついてしまうから。
「アーティキュレーションを適当に読んでしまうクセ」
はもちろん、
「間違った音のまま読み、手に動きを覚えさせてしまう(クセ)」
これらのようなクセをつけてしまうと
のちほど修正するのに骨が折れます。
「一度覚えてしまったものを修正してクセを抜くのは、イチから譜読みするよりもたいへん」
この事実を忘れてはいけません。
そこで今回は、
「正しく」なおかつ、
その中で「できる限り速く」譜読みをするために必要な6つのポイントを
「全レベル共通」「中級者以上」
に項目分けして解説していきます。
■【ピアノ:レベル別】譜読みを効果的に行う6つのポイント
①【全レベル共通】短い単位に区切って読む
譜読みでは、
「短い単位に区切って何度も何度も同じところを読んでいく」
これが効果的。
効率よくおおむね弾けるところまでもっていくためには、
「今弾いたところを忘れないうちに、もう一度弾くこと」
こうすることで
記憶定着に直結するので有効なのです。
また、
このような方法で譜読みをすると
短い単位に集中できるので
「臨時記号の見落とし」
などにも気付きやすく、
正しい譜読みも目指せます。
②【全レベル共通】複数曲あるなら「皿回しによる譜読み」
同時にいくつかの楽曲の譜読みをする場合には、
「皿回しによる譜読み」
をオススメします。
つまり、1曲をまるまる終わらせてから次の曲へ移るのではなく、
「ある程度の単位を集中して読んだら別の曲を数小節読む、そしてそれを回していく」
ということ。
①でご紹介した、
「短い単位に区切って、何度も何度も同じところを読んでいく」
という方法をひとつの単位として
それらを回していくのです。
この方法をとることで
「飽きずに譜読みを続けられる」
というメリットがあります。
譜読みというのは、
学習者によってはいちばん気が乗らない過程かもしれません。
譜読み方法自体にバリエーションを持たせるべき。
③【全レベル共通】「繰り返し」のセクションは要注意
楽曲の中には「繰り返し」がたくさん出てきますね。
譜読みの段階で「繰り返し」を見つけたら
やっておくべきことがあります。
それは、
◉ 似ているけれども、やや変化が加えられているところ
これらをしっかりと区別して整理しておくということ。
そうすることで、
のちほど「暗譜」をする際に役に立ちます。
譜面を見て弾いている段階では
正直、こういったことを意識しなくても弾けてしまう。
一方、暗譜ではそうはいきません。
実際、ベートーヴェンの「ソナタ形式の楽章」などで
「再現部を提示部と同じように弾いてしまって先へ進めなくなってしまった」
という事例は、
かなり弾ける学習者にも起こりえること。
場合によっては
「音程自体はまったくそのまま繰り返しているけれども、ダイナミクスのみ変化している」
こういった例もありますので、
注意深く楽譜を読む必要があります。
音を読むだけでなく、
こういった細かなニュアンスも読み取っていくのが譜読みです。
④【中級者以上】事前に簡単なアナリーゼを
ここからの項目は
中級者以上の方が主な対象者です。
自分なりのやり方で構わないので
譜読みをするよりも前に簡単なアナリーゼをしておくことをオススメします。
「どこどこが何調に転調して…」
などといったことは
それほど演奏には直結しません。
むしろアゴーギクに直結する部分、
「音楽の区切りがどこにあるのか」
ということを理解できるとベターです。
ひとつだけ方法をご紹介しておきましょう。
構成の区切りをみていくときのポイントは
「線入れ」です。
書かれている「a tempo」の前に「線」を入れてみましょう。
a tempoの前というのは
「段落の切れ目」になっていることが多いので、
線を入れてみることで
構成を見抜くことができます。
楽曲によっては
線を入れなくても構成の切れ目を判別できると思いますが、
実は、ウェーベルンなどの無調以後の作品でも、
この「線入れ」は有効な場合が多いのです。
覚えておいて損はありません。
⑤【中級者以上】譜読みでは「運指決定」が重要
譜読みでは、
まず「運指(指遣い)」を決定し、
その後にさらっていきましょう。
クセがつく前に譜読みの早い段階で運指を考えておくのがポイントです。
「毎回決めた運指で演奏する」 というのが重要。
演奏する度に毎回運指が変わってしまうと
効率が良くありませんし
「暗譜」をする際に足をひっぱる原因にもなります。
「やりにくい」と感じる箇所があったら
その際は変更可能ですが、
その場合にも
「じゃあ、これでいく」というような「決定」が必要です。
運指の決定方法のヒントについては、
を参考にしてください。
⑥【中級者以上】「譜読み」と「曲想」を同時に
譜読みが完全に終わってから曲想をつけていく方も
少なからずいるようですが、
筆者は「同時におこなっていく」のをオススメします。
表現したい内容が変わるとテクニック自体が変わるので、
場合によっては
「運指決定」などが二度手間になってしまうことがあるからです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
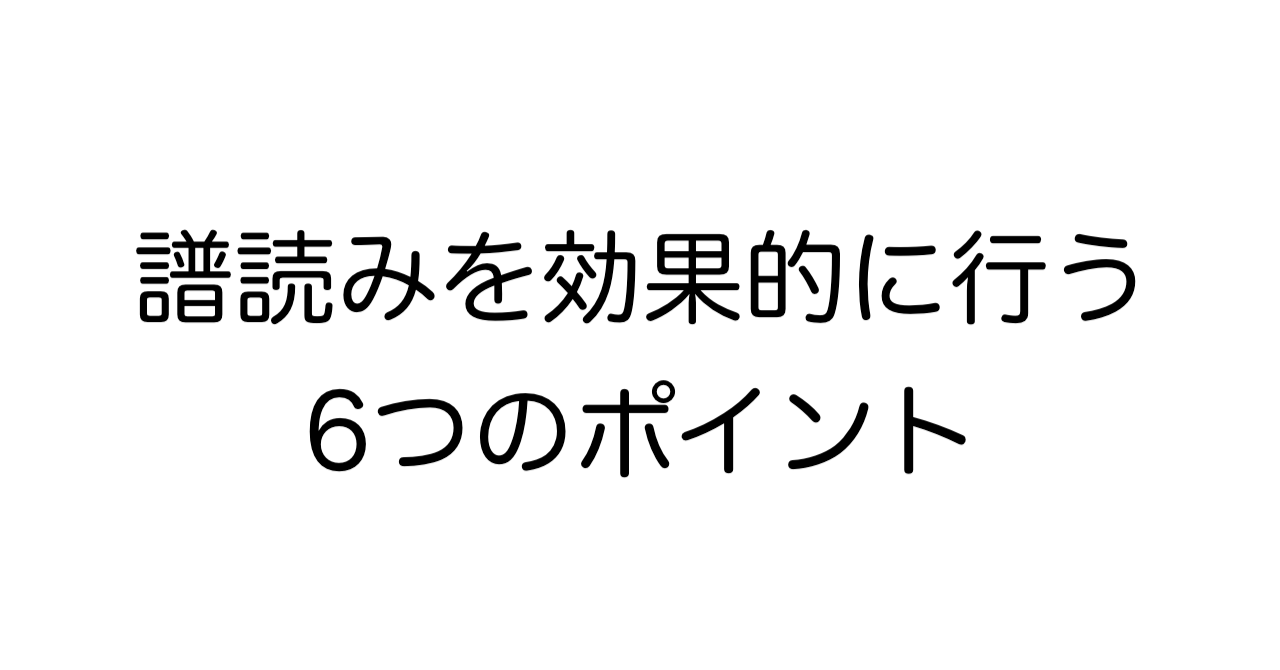
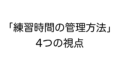
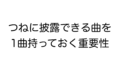
コメント